荒川院へのご予約
スタッフブログ

左腕の痺れは危険なサイン?考えられる原因と対処法を徹底解説
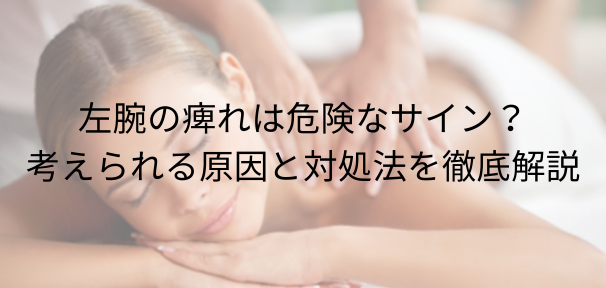
左腕の痺れとは?よくある症状の出方と感じ方
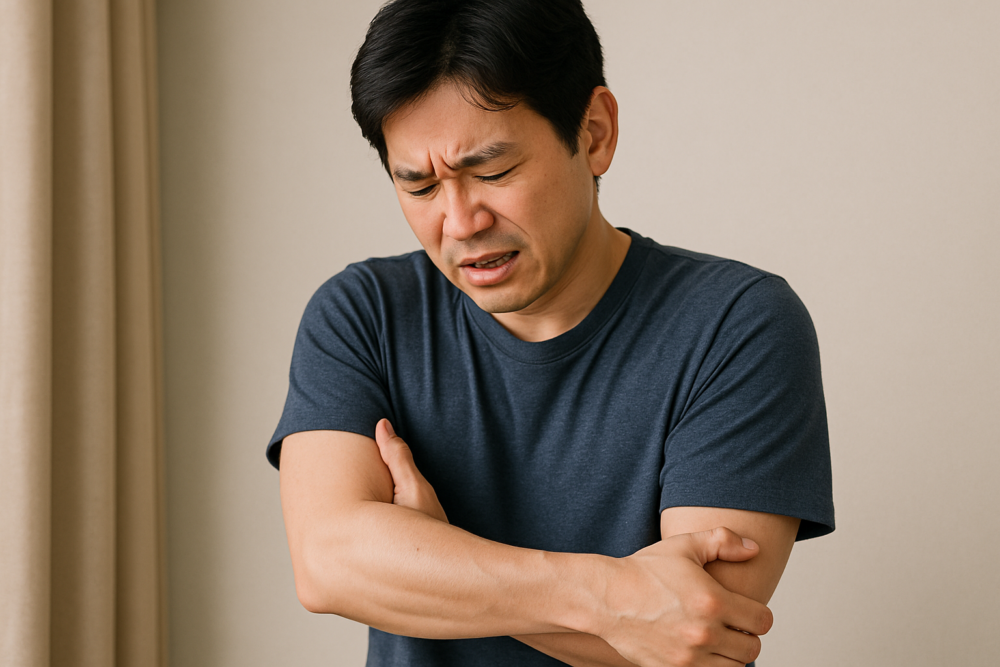
「最近、左腕がじんじん痺れるんだけど…」
こんなふうに感じたこと、ありませんか?日常生活の中で腕の感覚に違和感を覚えると、つい不安になるかと思います。とくに左側となると、「心臓と関係があるのでは?」と心配になる方も少なくないようです。
ここでは、左腕に現れる痺れの特徴や出方、そして右腕との違いについてお話していきます。
どんな痺れ方が多い?ビリビリ・ジンジン・脱力感など
まず、よくある症状としては「電気が走るようなビリビリ感」や「持続的なジンジンとした感覚」があります。これに加えて、力が入りにくい、細かい動作がしづらいといった“脱力感”を伴うこともあります。
例えば、
- 長時間スマホを使っていたあとに指先がしびれる
- 重い荷物を持った翌日に腕全体がだるく痺れる
など、原因はさまざまです。
当院では、こうした感覚の違いや範囲を丁寧に確認することで、頚椎(首)や胸郭、神経経路のどこにストレスがかかっているのかを検査で見極めていきます。
右腕との違いは?片側だけの痺れに注意すべき理由
「右ではなく左だけが痺れる」という場合、身体の片側に異常が起きている可能性があります。
特に左腕の場合、心臓に関連する循環器系の不調が背景にあることも考えられます。
一方で、首から出ている神経の通り道が筋肉や骨格のバランスの乱れによって圧迫され、片側だけに症状が出るケースも当院ではよく見られます。たとえば、胸郭出口症候群や頚椎由来の神経圧迫などが挙げられます。
当院では、手指の感覚テストや姿勢のチェックを通じて、左右差の原因を細かく分析し、痺れの背景にある根本的な原因を明らかにするよう心がけています。
どんなタイミングで出る?寝ている時・起きてすぐなど
「朝起きたら腕が痺れていた」「寝ている間に感覚がなくなっていた」
こうした訴えは非常に多く、寝姿勢や枕の高さ、呼吸の浅さなどが関係している可能性もあります。
とくに寝返りが少ない方や、肩を下にして眠る癖がある方は、腕の神経や血管が圧迫されやすくなります。当院では、こうした寝姿勢の分析や呼吸の深さ、肋骨の動きまで含めてチェックを行い、施術と合わせてセルフケア指導も行っています。
腕や肩周りのストレッチや、寝る前の簡単な呼吸エクササイズなどをご案内し、少しずつ症状の軽減を目指すようサポートしています。
#左腕の痺れ
#片側だけの症状
#朝に痺れる
#神経圧迫の検査
#整体での体の見直し
左腕が痺れる主な原因とは?

「左腕が痺れるときって、何が原因なんだろう…?」
そう感じたことはありませんか?実際、左腕の痺れにはいくつかの要因が関係していると考えられており、必ずしもひとつの原因に限られるわけではありません。ここでは、当院の見解や検査の考え方を交えながら、よくある原因についてご紹介していきます。
首の神経圧迫(頚椎症・ヘルニアなど)
まず代表的なものが、「首の神経圧迫」による痺れです。
頚椎のゆがみや椎間板の変性(いわゆるヘルニア)によって、神経が刺激され、腕や手指までしびれるケースが多く見られます。
「デスクワークやスマホ時間が長い」「猫背気味で首が前に出ている」などの姿勢のクセが原因となることもあります。
当院では、首まわりだけでなく、背骨の動きや肩甲骨のポジションなども含めて検査し、神経の通り道に無理がかかっていないかを細かくチェックしています。
心臓疾患(狭心症・心筋梗塞の前兆)との関連
左腕の痺れは、心臓の不調が背景にある場合もあるとされています。
特に「胸が締めつけられる」「息苦しい」といった症状を伴う場合は、狭心症や心筋梗塞など循環器系の異常が関係している可能性も否定できません。
そのような場合、整体ではなく内科的な検査が必要となることがありますので、当院でも必要に応じて医療機関への受診をご提案するケースがあります。
「いつもの痺れとはちょっと違う」と感じたら、無理せず専門の検査を受けてみることをおすすめしています。
末梢神経障害や血流障害(胸郭出口症候群など)
神経が圧迫されやすいポイントの一つが、「鎖骨まわり」。
ここを通る神経や血管が、筋肉や骨格の影響で締めつけられることで、腕全体に痺れや冷え、だるさが出ることもあります。
たとえば胸郭出口症候群という状態では、腕を上げる動作で痺れが強くなったり、首や肩に重さを感じたりする場合もあります。
当院では、鎖骨や肋骨の動き、呼吸の深さ、巻き肩の有無などを総合的に検査し、日常的な姿勢のクセも含めて調整を行っていきます。
一時的な圧迫・筋肉疲労による痺れ
一方で、「一時的な圧迫」や「筋肉の過緊張」による痺れもよく見られます。
たとえば寝ているときに腕を下敷きにしていたり、同じ姿勢で長時間作業をしていた場合などが典型です。
こうした場合、血流や神経の流れが一時的に滞り、痺れとして感じられることがあります。
当院では、筋膜リリースやストレッチの指導を通じて、回復を促しながら再発を防ぐための体の使い方もサポートしています。
#左腕の痺れ原因
#神経圧迫と頚椎症
#心臓疾患との関係
#胸郭出口症候群
#整体でできる対応
病院に行くべき痺れの見極めポイント

「ただの疲れかも…でもなんとなく不安」
左腕の痺れを感じたとき、受診すべきか迷う方は多いのではないでしょうか?
痺れが一時的なもので済むこともありますが、なかには早めの対応が必要なケースもあります。ここでは、当院の視点も交えて“受診の目安”をわかりやすくまとめてみました。
すぐ受診すべき症状(息苦しさ、胸痛、言葉が出ないなど)
「痺れだけじゃなく、胸が締めつけられる感じがする」
「息がしづらい」「言葉が出にくい」などの症状があるときは、なるべく早く医療機関へ相談することが望ましいです。
こうした症状は、心筋梗塞や脳梗塞など循環器・脳神経に関わる疾患の前兆である可能性もあります。特に、痺れと同時に顔や片足などにも違和感が出るような場合は、早急な検査を推奨しています。
当院では、問診の段階でこうした“見逃してはいけないサイン”に着目し、整体よりもまず医療機関での検査を優先していただくようお話しする場合もあります。
どの診療科を選べばよい?整形外科・内科・脳神経外科の目安
「どこに行けばいいか迷う…」という方も多いと思います。
痺れの原因が神経や骨格にあると考えられる場合は、整形外科が選ばれます。一方、心臓や血管の問題が疑われる場合は内科、または循環器内科の対象になります。
さらに、「言葉が出ない」「片側の手足が同時に動かしづらい」などの症状があるときは、脳神経外科が候補となります。
当院では、ご来院いただいた際に身体の状態を確認し、必要であれば医療機関をご案内するケースもあります。目的は、「いま何を優先すべきか」を見極めることにあります。
診察でよく行われる検査内容(MRI・レントゲン・心電図など)
病院では、症状に応じてさまざまな検査が行われます。
たとえば、首のヘルニアや神経圧迫が疑われる場合は、MRIやレントゲンによって神経の通り道の状態を確認するのが一般的です。心臓や血管に関わる問題があると判断されれば、心電図や血液検査、エコーなどが行われることもあります。
こうした検査で原因が明確になれば、当院でもその情報をもとに施術内容を調整したり、セルフケアのアドバイスをしたりすることが可能になります。
#痺れと病院受診
#整形外科か内科か
#すぐに検査すべき症状
#脳梗塞との見極め
#整体と医療の連携
当院での整体アプローチと検査の特徴

「病院では異常なしと言われたけど、左腕の痺れが気になる」
そんな声をいただくことがあります。当院では、単に痛みや痺れのある部位を見るのではなく、体全体の連動性を確認しながら原因を探っていくことを大切にしています。以下に、当院ならではの検査や施術のポイントをご紹介します。
首・肩・腕の連動性を重視した検査と原因特定
たとえば左腕に痺れが出ていても、実際に負担がかかっているのは首だったり、肩甲骨の動きに問題があったりするケースも少なくないです。
当院では、首から肩、腕にかけての「連動のパターン」を見ながら、動きのスムーズさや左右差、力の入り具合などを丁寧にチェックしていきます。
一見関係なさそうな部位が、痺れの原因になっていることもあるため、パーツごとではなく「体の繋がり」を読み取ることを大切にしています。
神経や血流を妨げる姿勢のクセ・筋肉の硬さへのアプローチ
「デスクワークが多く、姿勢が崩れがち」という方はとても多いです。
当院では、巻き肩・猫背・骨盤の傾きといった姿勢のクセが、神経や血流の流れを妨げていないかどうかを重点的に検査しています。
そのうえで、筋膜リリースや関節の調整などを用い、筋肉の硬さや動きの制限を和らげるよう施術を行っていきます。力まかせに押したり鳴らしたりせず、ゆるやかに整えていく手技が中心ですので、ご安心ください。
生活習慣・姿勢改善のアドバイスと再発予防
施術を受けて楽になったとしても、日々の生活で同じ動きや姿勢を続けてしまえば、再び痺れが戻ってしまう可能性もあります。
そこで当院では、再発を防ぐための生活習慣改善にも力を入れています。
たとえば、仕事中の座り方、スマホの持ち方、睡眠時の姿勢など…ちょっとした工夫でも体の負担を軽減することができます。
また、ストレッチや呼吸法など、自宅で続けやすいセルフケアもお伝えしています。「ただ施術するだけでなく、“自分で管理できる体”を目指す」というのが、当院の考え方です。
#整体での神経アプローチ
#首肩腕の連動性検査
#姿勢と筋膜への施術
#痺れの再発予防
#生活習慣の見直しサポート
自宅でできるセルフケアと再発予防のポイント

「整体に行って楽になったけど、また痺れが出てきた…」
そんな声をよく耳にします。実は、整体の施術と並行して、自宅でのセルフケアを継続することがとても大切です。ここでは、左腕の痺れ対策として自分でできるケアと、再発を防ぐための工夫についてご紹介します。
腕・肩まわりのストレッチとほぐし方
「1日中デスクワークで肩がガチガチ…」そんな方は要注意です。
腕の神経は首や肩を通っているため、このあたりの筋肉が硬くなると痺れが出やすくなります。
たとえば、肩を回すストレッチや、腕を伸ばして脇や胸の筋肉を緩める動きなどは比較的取り入れやすいかもしれません。
当院でも、施術の際にその方の姿勢や動きのクセを見たうえで、負担がたまりやすい部分に合ったセルフケアを提案しています。
ポイントは「がんばりすぎないこと」です。心地よい範囲で無理なく続けることが大切になります。
デスクワークや睡眠中の姿勢見直し
「気がついたら首が前に出ている」「腕を体に押しつけたまま寝ていた」
こんな姿勢のクセが、神経や血流を圧迫していることも多いです。
当院では、座っているときの腰や足の位置、モニターの高さなどをお聞きしながら、日常での負担を減らすための具体的なアドバイスを行っています。
また、枕やマットレスの高さが合っていないと、睡眠中に腕が痺れやすくなることもあるため、寝具の見直しも一つのヒントになるかもしれません。
長引くときは無理せず専門家へ相談を
「しびれがなかなか引かない」「以前より範囲が広がってきた」
こういった場合は、早めに専門家へ相談することがおすすめです。
当院では、施術だけでなく細かな検査や姿勢・動きの分析を通じて、根本原因を探ることを重視しています。そのうえで、必要があれば医療機関の受診をご案内し、適切なケアをご提案しています。
無理にセルフケアを続けることで、かえって状態が悪化することもあるため、「これ以上は自己判断がむずかしいな」と感じたら、一度ご相談いただければと思います。
#腕のストレッチ方法
#痺れ再発の予防法
#寝方と姿勢の工夫
#セルフケアのタイミング
#整体と日常改善の併用
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

廣瀬 知志
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


