荒川院へのご予約
スタッフブログ

膝が痛いスクワットの原因と正しいフォーム|膝痛を防ぐトレーニング法
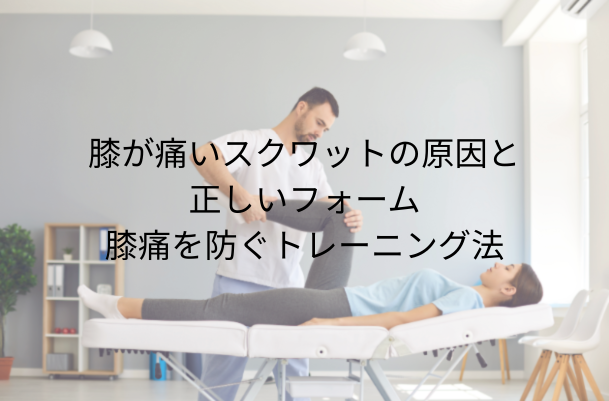
膝が痛くなるスクワットの主な原因

間違ったフォームが膝に負担をかける
「スクワットをすると膝が痛い…なんで?」という声、実はよく聞きます。これ、単に筋肉痛というより「フォームのミス」で膝の関節に負担がかかってることが多いんです。
膝が内側に入る「ニーイン」に要注意
鏡の前で自分のスクワットフォームをチェックしてみてください。しゃがむ時、膝が内側に入ってませんか?これ、「ニーイン」と呼ばれる現象で、膝関節の動きが不自然になり、痛みを引き起こす要因のひとつです。
この動きは、股関節や足の筋力のバランスが崩れているときによく見られます。特に太ももの内側と外側の筋力に差があると、膝がまっすぐに動きづらくなってしまいます。
股関節や足首の柔軟性も関係している
意外に見落とされがちなのが、「柔軟性不足」。特に股関節や足首の可動域が狭いと、膝が正しい軌道で動けなくなり、無理な方向に曲がってしまうことがあります。
股関節が硬いと骨盤ごと前傾し、膝がその影響を受けてしまうケースも少なくありません。足首も同様で、可動域が狭いと、かかとが浮いたり膝が前に出たりして膝に負担が集中します。
「膝が痛いスクワット」というキーワードで検索すると、同じような悩みを抱えている方が多く見つかります。正しいフォームを身につけることはもちろん、柔軟性を高めたり、膝まわりの筋肉を整えることもとても大切です。
無理して我慢して続けるのではなく、「なぜ痛むのか?」を冷静に考えて、ひとつひとつ原因を減らしていきましょう。
#スクワット膝痛
#フォーム改善
#ニーイン対策
#柔軟性がカギ
#正しい筋トレ知識
正しいスクワットフォームのポイント

スクワット、どこから曲げる?股関節から!
「スクワットって、ただしゃがめばいいんじゃないの?」って思ってたら、それはちょっと危険かもしれません。実は、動作の最初に曲げるのは“膝”じゃなくて“股関節”です。
正しいフォームでは、お尻を後ろに引くようなイメージで、まず股関節を折り曲げます。この動作を意識すると、膝への負担を減らすだけでなく、太もも裏やお尻の筋肉がしっかり使えるようになります。
膝とつま先の方向は「揃える」が基本
スクワット中、膝が内側に入ってしまうと「ニーイン」という状態になり、膝関節に無理な力がかかります。
それを防ぐためには、「膝とつま先の向きを同じ方向に揃える」ことが大切です。鏡の前でチェックしてみると意外とずれていた…なんてことも多いので、最初のうちは意識的に確認しながらやってみてください。
膝の位置は“つま先の後ろ”が目安
しゃがんだときに膝がつま先より前に出すぎると、膝蓋大腿関節に強い負荷がかかります。
もちろん体型や可動域の違いもあるので、必ずしも「前に出たらダメ」というわけではありませんが、膝がつま先より大きく出ていると感じたら、フォームを見直すサインかもしれません。とくに初心者のうちは、壁スクワットなどを使って、膝の位置を意識するのが効果的です。
スクワットはシンプルなようで奥が深いエクササイズ。だからこそ、フォームを整えるだけで膝痛を避けられる可能性が高まるとも言われています。
「痛みが出る前にできること」、それがフォームの見直しです。
#正しいスクワット
#膝痛予防
#フォーム改善
#股関節から動かす
#ニーイン防止
膝痛を防ぐためのストレッチとエクササイズ

スクワット前の“準備運動”が膝を守る
「スクワットで膝が痛くなるんです…」と悩んでいる方、フォームだけでなく“体の準備”も見直してみませんか?実は、股関節や足首の動きが悪かったり、体幹がうまく使えていないと、スクワット中に膝にかかる負担が増えることがあります。
そこで今回は、膝を守るために役立つ3つのエクササイズをご紹介します。
ヒップヒンジ:股関節の動きを整える基礎動作
ヒップヒンジは、スクワットに必要な「股関節から曲げる動き」を身につけるのに最適です。まっすぐ立った状態から、膝を軽く曲げながらお尻を後ろに突き出すようにして上体を前に倒します。
この動作を繰り返すことで、自然と股関節主導の動きが身につき、膝が過度に前に出るのを防止できます。慣れないうちは壁に背を向けて行うと、動作の感覚がつかみやすいかもしれません。
クラムシェル:中殿筋や梨状筋を鍛えて膝の安定感UP
「膝が内側に入るのが気になる…」という人には、クラムシェルがおすすめです。横向きに寝転がり、膝を曲げた状態で上側の膝をゆっくり開閉するエクササイズです。
この動きで鍛えられるのは、中殿筋や梨状筋といった、骨盤から大腿骨にかけて働く安定筋。これらがしっかり機能することで、膝のブレを抑えるサポートになります。
足首の柔軟性向上ストレッチで可動域を広げよう
足首が硬いと、しゃがんだときにかかとが浮いたり、膝が前に出やすくなります。そこで大切なのが、足首の可動域を広げるストレッチです。
おすすめは、壁に向かって立ち、片足を前に出して膝を壁に近づける「壁押しストレッチ」。無理のない範囲で続けていくことで、足首の柔軟性が高まり、スクワット時の安定性にもつながります。
スクワットで膝を守るには、「正しいフォーム+正しい準備」がセットで大事です。日頃からこれらのエクササイズを取り入れて、膝にやさしいトレーニングを心がけてみましょう。
#ヒップヒンジ
#クラムシェル
#足首ストレッチ
#膝痛予防トレーニング
#股関節から整える
膝に優しいスクワットのバリエーション

無理なく安全に始められるスクワットとは?
「膝が痛いけど運動は続けたい」そんなときに役立つのが、膝への負担を軽減できる“やさしいスクワット”のバリエーションがあります。フォームが崩れがちな初心者や、膝に違和感がある方でも取り入れやすい方法として、次の3つを紹介します
椅子を使ったスクワット:安心感と安定感のあるトレーニング
まず最初に試してほしいのが、椅子を使ったスクワット。方法はシンプルで、椅子の前に立ち、ゆっくり腰を下ろすだけ。完全に座るのではなく、椅子に軽くお尻を触れるくらいで戻るのがポイントです。
このやり方だと、しゃがみすぎによる膝の負荷を避けられる上に、バランスを崩しにくいので安心して行えます。動きに不安がある方には特におすすめのアプローチです。
壁を使ったスクワット:フォームが整いやすい
続いては、壁スクワット。背中を壁にぴったりつけた状態でスクワットすることで、姿勢が安定しやすくなり、自然と正しいフォームを意識しやすくなると言われています。
さらに、壁が支えになるため、膝がつま先より前に出づらくなり、膝関節への負担を抑える効果も期待されます。自宅の壁を使えば手軽にできるので、習慣化しやすいのもメリットの一つです。
ミニスクワット:浅くても効果的
「深くしゃがむのがこわい…」という方には、ミニスクワットがおすすめです。これは、浅く腰を落とすスクワットで、可動域は少ないですが、しっかり太もも前面の筋肉が使えます。
膝を曲げる角度を浅めに設定することで、違和感のある部位に負担をかけすぎず、トレーニングの導入としても効果的です。無理せず始めたいときの選択肢として、ぜひ取り入れてみてください。
スクワットといえば膝に負担がかかるイメージがあるかもしれませんが、やり方次第では膝にやさしく、安全に続けられる方法もあります。まずは自分に合ったバリエーションから始めて、徐々に慣らしていくのがポイントです。
#椅子スクワット
#壁スクワット
#ミニスクワット
#膝にやさしい運動
#正しいスクワット選び
膝痛がある場合の注意点と対処法

痛みを感じたら、まずは無理をしないことが大切
「スクワット中に膝がズキッとしたんだけど…続けてもいいのかな?」
そんなときは、迷わずいったんストップしてください。痛みがある状態で無理に運動を続けると、膝への負担がさらに増し、状態が悪化する可能性があります
まずは運動を中断し、膝を安静に保ちましょう。そして不安がある場合は、無理せず専門の先生に相談するのが安心です。
自分のフォーム、本当に合ってる?
膝に痛みを感じる原因のひとつに、「フォームの崩れ」があります。
特にスクワットのような反復動作では、少しのズレが蓄積され、膝関節に偏った負担がかかることもあります。
鏡の前で自分のフォームをチェックしてみたり、スマホで撮影して確認するのもおすすめです。膝がつま先より前に出すぎていないか、ニーインしていないかなど、一度見直してみましょう。
体幹トレーニングで姿勢を整える
「体幹って腹筋のこと?」と思われがちですが、実は背中・骨盤・腰回りを含む“胴体全体”を指します。この部分がしっかり働くと、スクワット時に軸がブレにくくなり、膝への余計な負担も減らせます。
プランクやドローイン、バランスボールを使ったトレーニングなどが体幹の強化に最適です。いきなりハードなトレーニングをする必要はないので、できることから少しずつ取り入れてみましょう。
スクワットは正しいやり方で行えば、膝にも優しいエクササイズになります。ただし、痛みが出たときには無理せず、原因を見極めながら対処していくことが大切です。
#膝が痛いときの対応
#スクワットの見直し
#フォーム改善
#体幹トレーニング
#安全に運動するために
この記事を書いた人

谷口 綾
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもお伺いしながら、最適な計画をご提案します。


