荒川院へのご予約
スタッフブログ

膝のつるような痛みが続く原因と対処法|放置NGな症状とは?
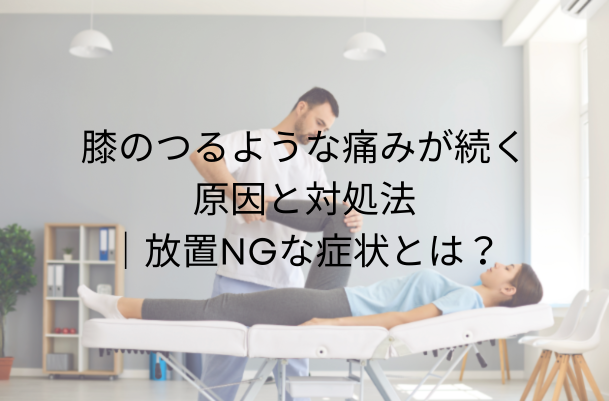
膝に“つるような痛み”が出るのはどんな時?

運動中や階段の上り下りで感じる痛み
「歩いていると急につったような感覚がきたんです…」。そんな風にご相談いただくことがあります。運動中や階段の上り下りでは、太ももやふくらはぎなどの筋肉が急激に使われることで、膝周辺に“つる”ような痛みを感じることがあります。特に、運動不足の方や、筋力のバランスが崩れている方に多く見られる傾向です。
当院では、こうしたケースではまず膝関節だけでなく、股関節・足関節との連動性もチェックします。例えば「もも裏が硬い」「足首の可動域が狭い」といった要素が痛みにつながっていることも多く、当院の検査ではそれらの細かなズレを丁寧に見ていきます。
施術では、筋膜リリースや関節モビライゼーションを組み合わせ、動作の再学習までサポートします。
就寝中や安静時に突然起こるケース
「夜中に急に膝がつって目が覚めた…」という声も少なくありません。運動とは関係なく、就寝中や安静時に出る“つるような痛み”は、筋疲労の蓄積や水分・ミネラル不足、自律神経の乱れなどが関係している場合があります。
日中の姿勢や歩き方のクセが、知らないうちに膝の筋肉に負担をかけていることもあります。当院では、生活習慣や仕事中の動き、睡眠中の姿勢に至るまでヒアリングし、「なぜそのタイミングで症状が出るのか?」を多角的に考えます。
必要に応じて、血流を促すための温熱ケアや、夜間の緊張をゆるめるストレッチの指導も行っています。
痛みとともにしびれや力が入らない場合
もし、膝の“つるような痛み”に加えて「しびれがある」「踏ん張れない」といった症状がある場合は、神経系の影響が考えられます。例えば、腰椎の神経圧迫や坐骨神経のトラブルなどが膝周辺に放散しているケースもあります。
こういった場合、膝自体に原因がないこともあるため、当院では膝だけでなく骨盤・腰椎まで評価を広げていきます。神経の通り道に制限がないか、筋の緊張パターンに異常がないかを確認したうえで、必要な部位にアプローチしていきます。
症状の再発を防ぐため、セルフケアとしては股関節や体幹を中心にしたエクササイズを提案しています。
#膝のつるような痛み
#筋肉と神経のバランス
#夜間の膝の痛み対策
#整体的な全身評価
#セルフケアと生活改善
考えられる原因|筋肉・神経・関節のどこが問題?

太ももやふくらはぎの筋疲労・けいれん
「階段の途中で膝のあたりがつる感じがして…」。こういったご相談は意外と多いです。特に、普段あまり運動をしていない方が急に動いた時などに、太ももやふくらはぎの筋肉が疲労し、けいれんのような反応を起こすことがあります。
この状態は一時的な筋疲労とも言われていますが、姿勢のクセや歩き方のアンバランスが背景にある場合もあります。たとえば、膝関節だけでなく骨盤の傾きや股関節の硬さが筋肉の負担を増やしている可能性があります。
当院では膝だけを見るのではなく、体全体の動きやバランスから原因を探ります。そして、筋膜リリースや関節モビライゼーションを通じて過度に負荷がかかっている部位をゆるめ、再発を防ぐためのセルフケアもご案内しています。
坐骨神経痛や脊椎由来の神経圧迫
「膝がつるような痛みに加えて、足がしびれる感覚もあるんです」。そんな時に考えられるのが、腰からくる神経圧迫の影響です。特に坐骨神経は、腰椎や椎間板の問題で圧迫を受けると、膝やふくらはぎまで痛みやしびれが広がることがあります。
このような場合、膝に原因があるとは限らず、根本的には腰や骨盤周辺のバランスが関係しているケースが考えられます。当院では神経の通り道に制限がないかどうかも評価し、必要に応じて体幹や骨盤の安定性にもアプローチします。
セルフケアとしては、腰部のストレッチや神経滑走を目的としたエクササイズも重要なポイントです。
変形性膝関節症や半月板損傷との関連
年齢とともに膝の痛みが出るケースでは、変形性膝関節症や半月板の摩耗も視野に入れる必要があります。「なんとなく膝がひっかかる」「動かすと違和感がある」というような声からも、関節内部の問題が見えてくることがあります。
これらは画像検査が必要となりますが、当院では触診や動作分析を通じて、関節の可動性や荷重のかかり方などからリスクを見極めています。施術では、過緊張した筋肉を緩めながら、動作のクセを調整していきます。
正しい荷重バランスを覚えることで、膝への負担を減らす工夫もお伝えしています。
ミネラル不足や脱水も要注意
意外と見落とされがちですが、水分不足やミネラル(特にマグネシウム・カリウム)の欠乏も、膝の“つり”に影響すると考えられます。特に夏場や発汗が多い時期、食生活が偏っている方は要注意です。
「運動してないのに足がつる」と感じる場合、体の内側のバランスを見直す必要もあります。当院では、施術だけでなく食事・水分の取り方に関するアドバイスも行っており、必要に応じて生活習慣の改善指導も含めてご提案しています。
外側と内側の両面からサポートすることで、再発しづらい体づくりを目指しています。
#膝のつる原因
#筋疲労と神経圧迫の関係
#関節の摩耗と姿勢バランス
#ミネラル不足による体の反応
#整体的アプローチで再発予防
放置してはいけない症状の見分け方

しびれや感覚異常がある場合
「つっただけだと思っていたのに、足先がしびれてきた…」。そんなご相談をいただくことがあります。
膝に“つるような痛み”があり、さらにしびれや感覚の鈍さを感じる場合、それは単なる筋肉の問題ではなく、神経に関係するトラブルの可能性も考えられます。特に坐骨神経の圧迫や、腰椎からの神経障害などが影響しているケースがあります。
当院では、痛みの出ている部位だけでなく、腰や骨盤の状態まで確認し、神経の走行に沿って圧迫やねじれがないかを丁寧に見ていきます。また、神経系の過敏さをやわらげるための神経モビライゼーションや、筋肉のアンバランスを整える施術も行っています。
同じ部位に繰り返し起こるつり
「また同じ場所がつってしまった…」。一度ならまだしも、同じ箇所に何度も“つる”ような痛みが出る場合は、日常動作や姿勢に問題が潜んでいるかもしれません。
たとえば、座っている時の姿勢が偏っていたり、歩き方に左右差があると、一部の筋肉ばかりが使われ続けて疲労しやすくなります。その結果として、同じ場所での痛みが繰り返される傾向があります。
当院では、施術前にカウンセリングや動作チェックを行い、体の使い方のクセやアンバランスを把握します。そのうえで、筋膜や関節の調整をしながら、再発を防ぐ体の使い方までサポートしています。
夜間や安静時にも症状が出るとき
「運動したわけでもないのに、夜中に突然膝がつった」。こんなケースでは、筋肉の緊張だけでなく、自律神経の乱れや代謝バランスの崩れも関係している可能性があります。
特に、日中のストレスや疲労がたまっていると、夜になって体がうまくリラックスできず、筋肉の過剰な収縮が起きやすくなることがあります。また、水分やミネラル不足も影響する可能性があるため、生活習慣の見直しも必要です。
当院では、体の外側だけでなく、内側(自律神経・栄養バランス)にも目を向けた施術やアドバイスを行っています。必要があれば、睡眠姿勢や枕の使い方、水分の取り方までご提案しています。
#膝のしびれと神経の関係
#同じ部位に繰り返す痛み
#夜間の膝痛の原因
#整体でできる根本的アプローチ
#生活習慣の見直しで再発予防
つるような膝の痛みを軽減する対処法

ストレッチやアイシングなどのセルフケア
「膝がつったように痛くなるとき、どうすればいいのか…」。まず試してほしいのが、筋肉をゆるめるストレッチと一時的なアイシングです。
例えば、ふくらはぎや太ももの裏を伸ばすストレッチは、過緊張した筋肉を緩和し、再び痛みが出るのを防ぐ効果が期待できます。また、急性の痛みがある場合には冷やすことで炎症を抑える目的があります。ただし、冷やしすぎや長時間のアイシングは逆効果となることもあるため、時間やタイミングを見ながら行うのが大切です。
当院では、検査の中で“どの筋肉が硬くなっているか”“関節がどう動いているか”を細かく評価したうえで、個別に最適なセルフケア方法をご提案しています。
ミネラル・水分の補給で内側からサポート
「運動していないのに、膝がつる感じがする…」。このような場合、体の内側に目を向けてみることも大切です。マグネシウムやカリウムなどのミネラル不足、水分の不足は、筋肉のけいれんを引き起こしやすい要因として知られています。
とくに、汗をかく季節や食生活が偏りがちな方は、こまめな水分補給とバランスの良い食事を心がけたいところです。水だけでなく、ナトリウムやカルシウムなどもバランスよく摂取することが筋肉の働きをサポートすることができます。
当院では、こうした内側の要因も含めて、症状の背景をカウンセリングで丁寧に探り、生活習慣の改善も含めたケアプランをお伝えしています。
膝に負担をかけない生活動作の工夫
「また膝がつったらどうしよう…」と不安になって動きがぎこちなくなる方も少なくありません。ですが、日常生活で膝にかかる負担を軽減する工夫を取り入れることで、不安を減らすことが可能です。
例えば、階段を使うときは手すりを活用する、長時間立ちっぱなしを避ける、正しい歩き方を意識する…といったちょっとした意識の変化が、膝への負荷を和らげるポイントになります。
当院では、動作評価によって負担のかかるクセを洗い出し、正しい体の使い方を再教育するリハビリ的アプローチも行っています。また、自宅でできる簡単なエクササイズや、靴・椅子選びなどのアドバイスも含めてお伝えしています。
#膝のセルフケア対策
#筋肉ストレッチとアイシング
#ミネラルと水分補給の重要性
#日常動作の見直しで予防
#整体で学ぶ正しい体の使い方
つるような膝の痛みが続くときは専門家へ

何科に行くべき?整形外科と整体の違い
「膝が何度もつるように痛むけど、どこに行けばいいのか迷ってしまう…」。そんな風に感じたことはありませんか?
このようなケースではまず、骨や関節の損傷がないかを確認するために整形外科での画像検査が有効です。骨折や半月板損傷、神経圧迫などの有無を確認することが第一ステップになります。
一方で、画像に異常がなかった場合、「もう様子をみましょう」と言われてしまう場合もあるかと思います。そうしたときに整体という選択肢があります。整体では、筋肉や関節の動きのクセ、姿勢や生活動作のバランスを細かく評価し、痛みの“背景”を探っていきます。当院もこのアプローチを大切にしています。
当院での検査・原因特定のアプローチ
当院では、カウンセリングと動作評価からスタートします。「いつ」「どんな動きで」「どの場所に」痛みが出るのかを具体的にヒアリングしながら、膝だけでなく股関節・足首・体幹との連動性まで確認します。
例えば、膝がつるように痛む原因が、実は腰や骨盤の不安定さにあることも少なくありません。
関節モビライゼーションや筋膜リリースといった施術に加え、再発しにくい体の動かし方やクセの修正までを一人ひとりに合わせて行っています。見逃されやすい“負担の積み重ね”を掘り下げるのが、当院の強みです。
再発予防のための施術とセルフケア指導
一時的に痛みを和らげるだけでなく、「なぜつるような膝の痛みが出るのか」という根本に対するアプローチを行うことで、再発のリスクを軽減することができます。
当院では施術と並行して、日常の歩き方や座り方、立ち上がるときのクセなどもチェックしながら、セルフケア指導をしています。ストレッチや筋力トレーニングだけでなく、靴の選び方や椅子の高さなども実は大切なポイントです。
3ヶ月間の中で「自分の体を理解し、自分で管理できる」ことを目指すプランもご用意しています。施術後も“自分の体の扱い方”を身につけることで、再発予防につながると考えています。
#膝のつりが続くときの対処
#整形外科と整体の違い
#膝の原因を全身から探る
#日常動作とセルフケアの大切さ
#再発しづらい体づくりサポート
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

廣瀬 知志
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


