荒川院へのご予約
スタッフブログ

足の冷えと病気|冷えの原因となる5つの疾患と対策法を解説
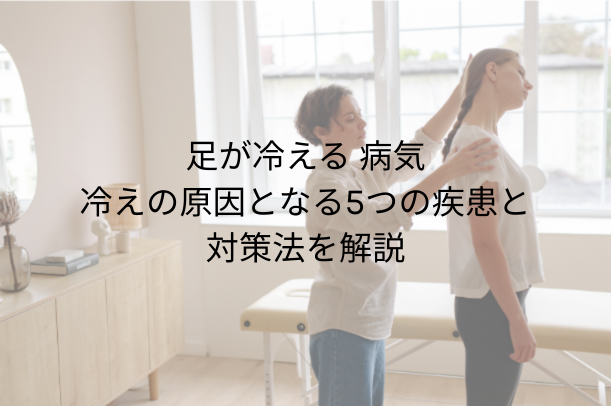

足が冷えるのは病気のサイン?見逃せない症状とは
足の冷え、ただの冷え性と思っていませんか?
「最近、足先が冷たくて眠れないんだよね…」
「冬だけじゃなくて、夏でも足が冷える気がするんだ」
こんな会話、聞いたことありませんか?実は、足の冷えは単なる冷え性ではなく、体からの重要なサインかもしれません。
足の冷えが示す可能性のある病気
足の冷えが続く場合、以下のような病気が関係していることがあります。
- 閉塞性動脈硬化症(ASO)
動脈が狭くなり、血流が悪化することで足が冷たく感じることがあります。 - バージャー病(閉塞性血栓血管炎)
手足の動脈に炎症が生じ、血管が細くなることで冷えを感じることがあります。 - レイノー病
寒さやストレスで血管が収縮し、指先が白くなったり冷たく感じたりすることがあります。 - 甲状腺機能低下症
代謝が低下し、体温調節が難しくなることで冷えを感じることがあります。 - 自律神経失調症
ストレスや生活習慣の乱れにより、自律神経のバランスが崩れ、血流が悪化することがあります。
これらの病気は、足の冷えだけでなく、しびれや痛み、色の変化などの症状を伴うことがあります。
どんな症状に注意すべき?
- 足先の色が白や紫に変わる
血流が悪化している可能性があります。 - 歩くと足が痛くなるが、休むと楽になる
間欠性跛行と呼ばれる症状で、閉塞性動脈硬化症の特徴です。 - 足のしびれや感覚の低下
神経障害が進行している可能性があります。 - 足の傷が治りにくい
糖尿病などの影響で、血流が悪化していることがあります。
まとめ
足の冷えが続く場合、単なる冷え性と考えず、他の症状と合わせて注意深く観察することが大切です。特に、色の変化や痛み、しびれなどがある場合は、早めに医療機関で相談することをおすすめします。
#足の冷え #閉塞性動脈硬化症 #バージャー病 #レイノー病 #健康管理
足の冷えと関連する主な疾患

閉塞性動脈硬化症(ASO)
閉塞性動脈硬化症は、動脈の壁にコレステロールや脂肪が蓄積し、血管が狭くなることで血流が悪化する病気です。特に下肢の動脈に多く見られ、50歳以上の男性に多いとされています。主な症状としては、歩行中に足が痛くなり、休むと楽になる「間欠性跛行」があります。進行すると、安静時にも痛みを感じるようになり、最悪の場合、足の潰瘍や壊疽を引き起こすこともあると言われています。
バージャー病(閉塞性血栓血管炎)
バージャー病は、主に若年男性に多く見られる疾患で、喫煙との関連が強いとされています。小〜中型の動脈や静脈に炎症と血栓が生じ、血管が閉塞することで、足の冷えやしびれ、痛みを引き起こすことがあります。進行すると、指や足先に潰瘍や壊疽が生じることもあると言われています。
末梢動脈疾患(PAD)
末梢動脈疾患は、心臓や脳以外の動脈に動脈硬化が生じ、血流が悪化する病気です。特に下肢の動脈に多く見られ、足の冷えやしびれ、歩行時の痛みなどの症状が現れることがあります。進行すると、足の潰瘍や壊疽を引き起こすこともあると言われています。
レイノー病
レイノー病は、寒さやストレスに反応して、指やつま先の血管が収縮し、血流が一時的に減少する病気です。これにより、皮膚が白くなり、その後青紫色、赤色に変わる特徴的な色の変化が見られます。冷えやしびれ、痛みを感じることもあります。
糖尿病性神経障害
糖尿病性神経障害は、糖尿病の合併症として発症することがあり、神経が障害されることで、足の冷えやしびれ、痛みを引き起こすことがあります。進行すると、足の感覚が鈍くなり、傷や潰瘍ができても気づかないことがあり、感染や壊疽を引き起こすこともあると言われています。
甲状腺機能低下症
甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンの分泌が低下することで、代謝が低下し、体温調節が難しくなる病気です。これにより、全身の冷えや疲労感、体重増加などの症状が現れることがあります。足の冷えもその一つで、特に女性に多く見られると言われています。
自律神経失調症
自律神経失調症は、ストレスや生活習慣の乱れにより、自律神経のバランスが崩れることで、様々な症状が現れる病気です。血流の調節がうまくいかなくなり、手足の冷えやしびれ、動悸やめまいなどの症状が現れることがあります。足の冷えもその一つで、特に女性に多く見られると言われています。
#足の冷え #閉塞性動脈硬化症 #バージャー病 #レイノー病 #健康管理
足の冷えを引き起こすその他の要因

ストレスや自律神経の乱れ
「最近、仕事のプレッシャーでイライラしっぱなしで…」
「夜もなかなか眠れなくて、朝起きても疲れが取れないんだ」
こんな日々が続くと、体の調子も崩れてきますよね。特にストレスが溜まると、自律神経のバランスが乱れやすくなります。自律神経は体温調節にも関与しているため、その働きが不安定になると、手足の血流が悪くなり、冷えを感じることがあります。実際に、自律神経失調症の症状の一つとして、手足の冷えが挙げられています。
喫煙や過度なアルコール摂取
「一日の終わりに一杯飲むのが楽しみでさ」
「タバコを吸うとリラックスできるんだよね」
そんな習慣が、知らず知らずのうちに体に影響を及ぼしているかもしれません。喫煙は血管を収縮させ、血流を悪化させることがあります。また、過度なアルコール摂取も血管の拡張と収縮を繰り返すことで、血流の安定を妨げる可能性があります。これらの習慣が続くと、手足の末端まで十分な血液が行き渡らず、冷えを感じることがあると言われています。
筋力の低下や運動不足
「最近、運動する時間がなくて…」
「階段を上るだけで息切れしちゃうんだ」
そんな日常が続くと、筋力が低下しやすくなります。特にふくらはぎの筋肉は、血液を心臓に戻すポンプのような役割を果たしています。この筋肉が衰えると、血流が滞りやすくなり、足先の冷えを感じることがあります。また、筋肉は熱を産生するため、筋力の低下は体温の維持にも影響を及ぼす可能性があります。
低血圧や貧血
「立ち上がるとふらっとすることが多くて…」
「最近、顔色が悪いって言われるんだ」
こんな症状がある場合、低血圧や貧血の可能性があります。低血圧は血液を送り出す力が弱く、手足の末端まで血液が届きにくくなることがあります。また、貧血は酸素を運ぶヘモグロビンが不足することで、全身の血流が悪化し、冷えを感じることがあります。これらの状態が続くと、手足の冷えだけでなく、倦怠感や立ちくらみなどの症状も現れることがあります。
#足の冷え #自律神経の乱れ #喫煙と冷え #筋力低下 #低血圧と貧血
足の冷えに対するセルフケアと生活習慣の改善

「足の冷え、どうにかしたいけど何から始めればいいの?」
そんなお悩みを抱える方へ、日常生活で取り入れやすいセルフケアと生活習慣の改善方法をご紹介します。
適度な運動やストレッチ
「運動って苦手なんだけど…」という方も、簡単なストレッチやウォーキングから始めてみませんか?特に、ふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」とも呼ばれ、血液を心臓に戻すポンプの役割を果たしています。この筋肉を鍛えることで、血流が促進され、足の冷えの改善につながります。
体を温める食事の摂取
「食事で体を温めるって、具体的にどうすればいいの?」体を温める食材を意識的に取り入れることがポイントです。例えば、しょうがやにんにく、ねぎなどの香味野菜は体を内側から温める効果があるとされています。また、ビタミンEを多く含むアーモンドやかぼちゃ、アボカドなども血行を促進すると言われています。
ビタミンEの積極的な摂取
「ビタミンEって、どんな食材に含まれているの?」ビタミンEは、血管を広げて血流を促進する働きがあるとされています。アーモンドやアボカド、かぼちゃなどに多く含まれており、これらの食材を積極的に摂取することで、冷えの改善が期待できます。
入浴や足湯の活用
「シャワーだけで済ませがちなんだけど、やっぱり湯船に浸かった方がいいの?」ぬるめのお湯(38〜40℃)にゆっくりと浸かることで、体の芯から温まり、血行が改善されます。また、足湯も手軽にできる冷え対策としておすすめです。足首までお湯に浸けるだけでも、全身が温まる感覚を得られるでしょう。
衣類や暖房器具の工夫
「寒さ対策って、何をすれば効果的なの?」首・手首・足首の「三首」を温めることが効果的とされています。これらの部位は血管が皮膚の近くを通っているため、温めることで全身の血流に影響を与えます。また、レッグウォーマーや腹巻き、暖房器具を上手に活用することで、冷えを防ぐことができます。
#足の冷え #セルフケア #生活習慣改善 #ビタミンE #温活
医療機関を受診すべきタイミングと診療科の選び方

足の冷えが長期間続く場合や痛みを伴う場合の受診の目安
足の冷えが長期間続く場合や、痛みを伴う場合は、以下のような症状が現れることがあります。
- 足の色が青白くなる
- 歩行中に足が痛くなり、休むと楽になる(間欠性跛行)
- 足のしびれや感覚の低下
- 足の傷が治りにくい
これらの症状が現れる場合は、早めに医療機関で相談することをおすすめします。特に、足の冷えが2週間以上続く場合や、日常生活に支障をきたす場合は、専門の診療科を受診することが望ましいでしょう。
循環器内科や心臓血管外科など、適切な診療科の選定方法
「どの診療科を受診すればいいのか分からない…」という方も多いのではないでしょうか。足の冷えに関連する主な診療科は以下の通りです。
- 循環器内科
動脈硬化や血流障害など、血管に関する疾患を専門としています。足の冷えが血流の悪化によるものである場合、循環器内科での検査が有効とされています。 - 心臓血管外科
血管の手術や治療を専門とする診療科です。重度の血流障害や血管の閉塞が疑われる場合、心臓血管外科での対応が必要となることがあります。 - 神経内科
足の冷えに加えて、しびれや感覚の低下がある場合、神経の障害が関与している可能性があります。このような症状がある場合は、神経内科での検査が推奨されています。 - 整形外科
腰椎椎間板ヘルニアなど、骨や関節の異常が原因で足の冷えやしびれが生じることがあります。過去に腰を痛めた経験がある方や、腰痛を伴う場合は、整形外科での診察が適しています。
まずは、かかりつけの内科医に相談し、症状に応じて適切な診療科を紹介してもらうのも一つの方法です。また、症状が複数の診療科にまたがる場合は、総合診療科や地域の医療連携センターを活用することで、適切な診療科への案内を受けることができます。
#足の冷え #受診の目安 #診療科の選び方 #循環器内科 #心臓血管外科
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

笠井 将也
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


