荒川院へのご予約
スタッフブログ

膝のサポーター/スポーツ時に効果的な選び方と当院独自ケア完全ガイド
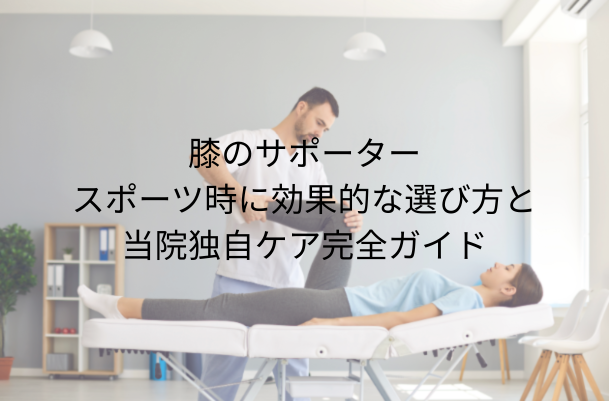
膝サポーターの基本知識とタイプ別比較

スポーツに使うなら、膝サポーターの違いを知ることから
「スポーツのとき膝がグラグラするんだけど、どのサポーターが合うの?」
この質問、実はとても多いんです。膝サポーターって一見どれも同じに見えるかもしれませんが、実は目的や構造によって種類がしっかり分かれています。
まず大きく分けて「筒型(スリーブタイプ)」「ベルト型」「スプリング(ヒンジ)付きタイプ」の3種類があります。
筒型サポーター:軽度のサポートが必要な方へ
筒型は伸縮性のある素材で作られていて、膝全体をやさしく包むタイプ。動きやすさを重視しつつ、軽い圧迫感で安心感を与えてくれます。
「まだ痛みはないけど、違和感がある」
「ウォーキング中に少し不安がある」
そんな方にはぴったりです。
ただし、強いサポートはないため、激しい運動や関節が不安定な方には不向きかもしれません。
ベルト型サポーター:圧迫力と安定感を両立
ベルト型は、自分で圧迫の強さを調整できるのが特徴です。膝蓋骨(お皿)の周囲をしっかり支える設計になっているものが多く、ジャンプ系スポーツやランニングをする方に使われることが多いです。
特に、ジャンパー膝や腸脛靭帯炎といったスポーツ障害が疑われる場合、このタイプが使いやすいと感じる方も多いようです。
当院でも、こうした膝障害の方には、まず関節のねじれや大腿四頭筋の硬さ、荷重バランスをしっかり検査し、必要に応じてサポーターの種類をご提案しています。
スプリング付き(ヒンジ)タイプ:しっかり固定したいときに
「膝をねじって痛めたことがある」
「不安定感が強くて、スポーツ中に膝が抜けそうになる」
そういったケースでは、金属またはプラスチックの補強が入ったタイプが検討されることがあります。
ただし、固定力が高い分、動きづらさを感じることもあるため、使用場面やタイミングは慎重に選ぶ必要があります。
当院では、膝のねじれやズレ、筋膜の滑走性を検査で確認した上で、固定力のあるサポーターを一時的に使いつつ、根本的には筋・関節・神経のバランスを整える施術を並行して行っています。
目的別で選ぶと失敗しづらい
膝サポーターは「予防」「痛みの軽減」「リハビリ補助」など目的によって選ぶべきタイプが変わります。
選び方を間違えると、かえって膝の動きが悪くなったり、筋力低下につながったりすることがあるため注意が必要です。
そのため、当院では症状のある部位だけでなく、姿勢や歩行・立ち上がりといった動作から膝の負担の原因を探し、必要なら運動指導やセルフケア指導もあわせて行っています。
「ただ巻けば安心」というわけではないからこそ、今の自分の膝の状態を把握した上で、正しいサポーター選びをしたいですね。
#膝サポーターの種類
#スポーツ向け膝ケア
#整体的視点での選び方
#膝の安定と予防
#当院の検査と施術方針
スポーツ別おすすめ&装着ポイント

スポーツによってサポーターの使い方も変わる?
「ランニングとバスケットボールじゃ、使うサポーターも違うの?」
はい、実はけっこう違います。膝への負担のかかり方って、競技によってかなり違います。
例えば、長距離ランナーとバレーボール選手では、膝にかかる「衝撃」や「ひねり」の方向が全然違います。それに合わせて、適したサポーターの選び方や装着位置にもコツがあります。
ランニング:腸脛靭帯や膝蓋靭帯に負担がかかるなら
長距離を走る人は、腸脛靭帯炎(ランナー膝)や膝蓋靭帯炎になりやすいと言われています。こうした症状があるときは、横方向への安定性を高めるためにベルト型のサポーターが用いられることが多いです。
当院でも、ランナー膝の方にはまず股関節や足首の動きを評価し、結果によってサポーターの使用を検討します。必要な場合は、股関節や膝のねじれ改善を目的とした施術と並行して使ってもらうケースもあります。
バスケット・バレーボール:ジャンプ動作が多いなら
ジャンプや着地を繰り返す競技では、膝蓋骨周囲や前十字靭帯に負荷がかかりやすいです。この場合、膝蓋骨を中心に安定させるパッド付きベルトタイプやヒンジ付きサポーターが使われることがあります。
とはいえ、強い固定をしすぎると動きにくさやフォームの崩れにもつながる可能性があるため、当院では膝単体ではなく「体全体のバランス」の視点から検査・評価を行います。
サッカーや格闘技:スピード+接触がある競技
横の動き、タックルや接触、急なターンが多い競技では、膝の内側・外側の靭帯にかかる負荷が強くなりやすいと考えられます。
このような場合、スプリング付きの強固なサポーターが使われることもありますが、当院では必要以上に固定しすぎないことを重視しています。まずは荷重ラインや姿勢のクセを分析して、そもそもなぜ負担が偏っているのかを探っていきます。
装着のポイントと注意点
サポーターは、ただ巻けばいいというものではありません。圧が強すぎると血流が悪くなるし、位置がズレていると効果が出づらくなります。
当院では、必要に応じて装着方法の指導も行っています。簡単に見えるけれど、正しい使い方をすることで「安心してプレーができた」と感じられるようになる方も少なくありません。
#スポーツ別膝サポーター
#ランナー膝とジャンパー膝
#競技特性と膝への負担
#当院の動作評価と施術
#正しいサポーター装着方法
当院(整体oasis)が重視する検査ポイント

サポーターの前に「どこに負担がかかっているか」を見極める
「このサポーターを巻いておけば大丈夫ですよ」
そう言われて、なんとなく使っている方もいるかもしれません。でも、ちょっと待ってください。
本当にそのサポーター、今のあなたの膝に合っているでしょうか?
実は膝に痛みが出ているとき、その原因が膝そのものにあるとは限りません。
当院では、膝の痛みを引き起こす根本原因を探るために、膝だけでなく「股関節」「足関節」「骨盤」「体幹」など、全体のバランスをチェックするようにしています。
荷重バランスとねじれをチェック
膝のねじれって、自覚しにくいんです。
でも、このねじれがある状態でサポーターだけで補おうとしても、動作のクセや姿勢の悪さが改善しなければ、再発するリスクが高くなります。
たとえば、当院では以下のような項目を細かくチェックしています:
- 立位での左右荷重の差
- 膝蓋骨や脛骨の捻じれ具合
- 足部のアーチ(扁平足や過回内)の状態
- 大腿四頭筋やハムストリングスの左右差や硬さ
- 股関節の可動域や骨盤の傾き
これらを組み合わせて、膝への負担のかかり方を全体から分析しています。
施術は筋膜・関節・神経にアプローチ
検査の結果、膝関節そのものに問題がある場合もあれば、原因が別の部位にあるケースも少なくありません。
たとえば、腸脛靭帯の緊張が強くて膝の外側に痛みが出ている場合、腰部や殿部の筋緊張にアプローチすることもあります。
当院では、
- 筋膜リリースで筋肉や靭帯の緊張を緩める
- 関節モビライゼーションで膝蓋骨や脛骨の動きを改善する
- 神経モビライゼーションで神経の滑走性を整える
といった複数のテクニックを組み合わせ、膝の負担を減らす施術を行っています。
セルフケアの指導で“再発しづらい体”を
「施術で楽になったけど、またすぐ戻るんですよね…」
そう感じてしまうのは、日常動作のクセが変わっていないからかもしれません。
当院では、セルフケアの指導も重要視しています。
膝を守るためのストレッチや、正しい立ち方・歩き方、階段の上り下りの動作までアドバイスしています。
こうした習慣が身につくと、サポーターに頼りすぎず、膝を自分で守れる体に近づいていきます。
#膝のねじれと痛みの関係
#膝以外の原因もチェック
#筋膜と関節のアプローチ
#神経の滑走性改善
#サポーターに頼りすぎないケア
当院の施術ステップ&セルフケア

サポーターだけじゃなく、施術で動きやすい膝へ
「サポーターをつけてれば安心だけど、外すと不安…」
そんなお悩み、実際によく耳にします。
膝サポーターはあくまでサポート役であって、根本的な改善のためには“体そのものを整える”ことが重要だと考えています。
当院では、膝の痛みや違和感のある方に対して、段階的な施術とセルフケア指導をセットで行うのが基本の流れです。
ステップ①:筋膜リリースで硬さを取る
まずは、大腿四頭筋やハムストリングス、腸脛靭帯などの筋膜の硬さを緩めていきます。
スポーツ後の筋疲労や過緊張により、筋膜の滑走性が悪くなると、関節へのストレスが増加します。
当院では、皮膚や筋膜の動きの悪さを丁寧に触診しながら、リリースを行っていきます。
ステップ②:関節のゆがみや捻じれを調整
次に、膝蓋骨や脛骨、さらには股関節・足関節など周辺関節のアライメントを整えます。
膝にかかる負荷を減らすためには、関節が本来あるべき位置でスムーズに動くことが大切です。
当院では、関節モビライゼーションや骨格調整により、無理のない範囲で整えていく施術を行っています。
ステップ③:動作改善と筋力の再教育
膝にかかる負担は、「立ち上がり」「しゃがみ」「ジャンプ」など日常動作にも隠れています。
そのため、ただ柔らかくして終わるのではなく、正しい動作パターンを再教育するステージも設けています。
ジャンプ時の着地の仕方や、歩き方のクセなどを分析して、動き方そのものを改善する指導も含めてサポートしています。
ステップ④:自宅でできるセルフケアを伝える
施術後は、「どうやってこの状態をキープするか」がとても大事です。
当院では、ストレッチやセルフ筋膜リリース、簡単な筋トレなど、自宅で続けられるケア方法もわかりやすくお伝えしています。
特に、サポーターを使っている方には「どのタイミングで外すか」や「再発予防の目安」なども丁寧に説明するようにしています。
#整体でできる膝サポート
#筋膜リリースの重要性
#膝のアライメント調整
#動作改善トレーニング
#自宅ケアでサポーター卒業へ
サポーターとの併用で効果アップする方法

サポーターは「補助」、体のケアは「基盤」
「このサポーターがあると安心なんですよね」
そのように感じるのは自然なことです。ですが、サポーターはあくまで補助的な役割。体の使い方や関節の状態が変わらなければ、サポーターに頼らざるを得ない状態が続いてしまうことがあります。
だからこそ、当院では施術やセルフケアと併用することで、サポーターの効果を最大限に活かす方法をおすすめしています。
正しく巻くことで本来の効果が発揮される
意外と多いのが「位置がズレてる」「締めすぎてる」「緩すぎて意味がない」といったケース。
実際、当院に来られる方でも、装着方法が不適切なために効果を感じられていない例をよく見かけます。
当院では、施術後に必要であればサポーターの装着位置や圧のかけ方、使用時間の目安まで細かくご説明しています。
その場しのぎではなく、膝の動きや状態に応じた使い方をすることで、より快適な日常が目指せるようになります。
「動ける膝」を育てる時間と役割分担
例えば、「今日は長距離を歩く予定がある」「ジャンプ系の練習がある」という日はサポーターを装着する。
一方で、「軽めの運動の日」や「日常生活」ではなるべく外して体を使う練習をしていく。
このように、日々の過ごし方に応じてサポーターを上手に使い分けていくことで、次第に「なしでも大丈夫」に近づいていくことができます。
当院では、関節や筋肉の状態に合わせた「卒サポート」計画を一緒に考えることも可能です。
成功事例から見える“卒サポーター”のヒント
「半年後にはサポーターを外してマラソンに出られた」
「部活の試合でも違和感がなかった」
そんな声も、少しずつ聞こえてきています。
共通しているのは、「体の使い方」や「ケアの習慣」がしっかり身についているということ。
サポーターをきっかけに、体のことを見直すチャンスにしていく。そんな考え方で取り組んでいけたら、より前向きなスポーツライフが待っているかもしれません。
#サポーターの正しい使い方
#卒サポートを目指す施術
#ケアと併用で安心
#膝に優しい習慣づくり
#整体的アプローチと運動の両立
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

笠井 将也
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


