荒川院へのご予約
スタッフブログ

ランナー膝 湿布で痛み緩和!効果的な使い方と当院独自アプローチ
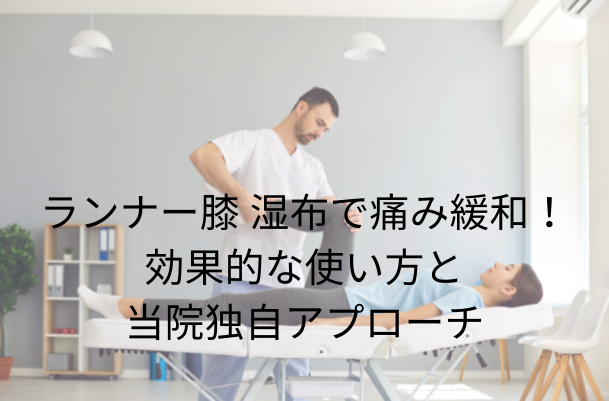
1.ランナー膝とは?湿布の役割と限界

ランナー膝の正体とは?
「最近、走ったあとに膝の外側が痛むんです…」
ランナーの方からよく耳にするこの訴え、多くの場合「ランナー膝」と呼ばれる腸脛靭帯炎の可能性があります。
腸脛靭帯とは、太ももの外側にある丈夫な筋膜の一部で、骨盤から膝下にかけて走っています。ランニングなどの反復動作により、この靭帯が膝の外側の骨と擦れ合い、炎症を起こすことが「ランナー膝」の主な原因と言われています。
走りすぎ、ウォームアップ不足、筋力のアンバランス、靴の不適合、フォームの問題などが引き金になるとされており、スポーツ初心者だけでなく、ベテランランナーにも起こり得る症状です。
湿布を貼ると本当に効果があるの?
「湿布を貼ればラクになる気がするけど、それで本当に大丈夫?」
そんな疑問を抱いたことはありませんか?
湿布には「冷湿布」と「温湿布」がありますが、実際に冷やしたり温めたりする効果は限定的で、「冷たく感じる」「温かく感じる」という感覚刺激が中心です。
冷湿布は痛みの初期や熱感のあるときに使われることが多く、局所の血流や神経の反応を一時的に緩和する働きがあるとされています。一方、温湿布は慢性的なこわばりや血行不良に使われることが多いですが、「温める」というより「温かく感じる」だけで、体の深部まで温める力はあまり期待できないとも言われています。
つまり、湿布は“痛みを紛らわせる”ことには有効でも、“根本的な改善”にはつながらないというのが実際のところです。
当院の考える湿布の使い方とその限界
当院(整体oasis)では、湿布は一時的な炎症の鎮静や、検査前に痛みの場所を確認するための参考材料として捉えています。
例えば、初回来院時には患者様の訴えと湿布の貼付部位を照らし合わせながら、立位や片脚立ち、膝屈伸などの動作を通じて、実際にどの動きで腸脛靭帯にストレスがかかっているのかを評価します。
その上で、当院では膝だけでなく、
- 股関節周囲の筋肉(特に大殿筋や中殿筋)
- 骨盤のアライメント(左右差や傾き)
- 足部の着地バランス(アーチ構造の崩れ)
などを含めた“体全体”の状態をチェックし、湿布に頼るのではなく「負担を減らす体の使い方」へと導く施術を行います。
湿布はあくまで“対症的な手段のひとつ”に過ぎません。根本から改善したいと考える方には、専門的な検査と施術が必要です。
#ランナー膝
#湿布の効果
#腸脛靭帯炎
#整体でのアプローチ
#根本改善の考え方
2.湿布の適切な貼り方・タイミング

貼る場所は“膝の外側”がポイント
「膝のどこに湿布を貼ればいいんですか?」
患者さんからよくいただくご質問のひとつです。
ランナー膝(腸脛靭帯炎)の主な痛みの場所は、膝の外側。特に、膝のお皿の少し下から外側上顆(がいそくじょうか)と呼ばれる骨の出っ張り付近に痛みが集中します。
そのため、湿布を貼る際はこの“膝外側のライン”を意識することが大切です。縦長の湿布を使って、痛みの中心を覆うように貼ることで、炎症を和らげる効果が得られやすいともされています。
ただし、「なんとなく痛いから全体に貼る」「膝裏にも貼っておこう」という貼り方では、必要な場所に成分が届きにくくなる可能性もあるため、痛みの部位をしっかり把握することが前提になります。
湿布は“急性期”や“運動直後”に活用を
「貼るタイミングはいつがいいですか?」という点についても、意外と見落とされがちです。
ランナー膝の痛みが出た直後や、腫れぼったさ・熱感がある時期(いわゆる急性期)には、冷湿布の使用が効果的だとされています。走ったあとに膝がズキズキと痛むようなケースでは、早めの対応が鍵になります。
一方で、慢性化して痛みはそこまで強くないけれど“違和感が残る”という場合には、湿布よりも温熱やマッサージ、ストレッチなど、血流を促すケアが適しています。
また、湿布は連続して長時間使いすぎると皮膚がかぶれたり、逆に回復を遅らせる可能性も指摘されています。使う頻度や貼る時間にも注意が必要です。
当院の検査ステップと湿布の使い方
当院(整体oasis)では、痛みが出ている方に対しては、まず湿布の貼付部位や感覚の変化を参考にしながら問診・触診を行います。
「どの動きで痛みが出るのか」
「いつから、どのくらいの頻度で感じるのか」
「湿布を貼るとどの程度ラクになるのか」
こうした情報を元に、腸脛靭帯だけでなく、
- 股関節周囲の筋の緊張
- 骨盤や下肢のアライメント
- 足底の荷重バランス
などを多角的に評価します。
検査の一環として、Grasping test(腸脛靭帯の圧痛評価)や動的な歩行分析も取り入れ、「なぜそこに負担が集中するのか」を見極めるのが当院の特徴です。
湿布だけで対処しきれない場合も多いため、根本的な負担の分散とセルフケアの提案まで、一貫してサポートしています。
#湿布の貼り方
#ランナー膝のセルフケア
#急性期の対応法
#膝外側の痛み対策
#整体での膝ケア
3.当院の検査ポイントと施術方針

「膝が痛い=膝だけが原因」とは限らない
「ランナー膝って膝だけの問題じゃないんですね…」
初めてご来院いただいた方が、検査後によく驚かれます。
当院では、ランナー膝に対するアプローチを“膝単体”では考えていません。膝に痛みが出ている場合でも、根本的な原因はもっと上の部位――たとえば、股関節周りの筋肉や骨盤の歪みに隠れているケースが多いです。
だからこそ、膝が痛いという声に対しても、全体の動きや姿勢、筋肉のバランスを丁寧に確認していくのが当院のスタンスです。
当院の検査ではここを見ます
まず、静止時と歩行時の姿勢をチェックします。ここでは、O脚傾向がないか、脚の長さに差がないかといった骨格のバランスを観察します。
次に、触診と動作確認で筋肉の硬さや左右差を確認。特に重要なのが、
- 臀筋(大殿筋・中殿筋)の硬さや機能低下
- 大腿筋膜張筋の緊張具合
- 腸脛靭帯の圧痛ポイント
といった部位です。
そして、Grasping testをはじめとする局所的な検査を組み合わせ、痛みの発生メカニズムを総合的に評価します。
「どこに負荷が集中しているのか?」
「どの筋肉がうまく使えていないのか?」
こうした視点で原因を“見える化”していくことで、施術の精度が格段に上がると考えています。
冷やすより、血流を促す施術を重視
痛みがあると「まず冷やしたほうがいい」と思いがちですが、慢性的な炎症や筋緊張が原因となっているランナー膝では、冷却よりも血流を改善するケアが有効になります。
当院では、以下のようなアプローチを組み合わせて施術を行います。
- 臀筋や腸脛靭帯への筋膜リリース
- 大腿筋膜張筋の癒着除去や緩和
- 骨盤・股関節のアライメント調整
- 下肢全体の連動性を高めるモビリティアプローチ
これらを通じて、膝への負担を“結果的に減らす”ことを目指しています。
さらに、施術のあとにはセルフケアの指導や再発予防のエクササイズも取り入れ、来院時だけでなく「日常でどう過ごすか」にもアプローチしています。
#ランナー膝の検査方法
#整体の根本アプローチ
#筋膜リリース
#骨盤調整
#股関節の可動域改善
4.自宅でできるセルフケアと再発予防

ストレッチは“夜の習慣”にするのがコツ
「ストレッチっていつやればいいですか?」
この質問に対し、当院では「就寝前」や「入浴後」をおすすめしています。
特にランナー膝に関わる腸脛靭帯や臀筋は、硬くなりやすい部位。日中の活動で負荷がかかった筋肉を、リラックスしたタイミングでじっくり伸ばすことで、血流も促されやすい状態になります。
仰向けで片膝を胸に引き寄せるストレッチや、横向きに寝たまま上側の脚を後方に引いて太ももの前側を伸ばす動きは、無理なく取り入れやすいメニューです。
「きついことをする」のではなく、「続けられることを習慣にする」ことが、長い目で見たときの再発予防につながると考えています。
筋トレは“弱点補強”と“体の連動”がカギ
「膝の痛みなのに筋トレが必要なんですか?」と疑問を持つ方もいますが、腸脛靭帯への負担が過剰になる背景には、体幹や股関節周りの筋力不足が関係していることも少なくありません。
当院では、以下のような簡単な筋トレを自宅でも実践していただいています。
- ヒップリフト(仰向けでお尻を持ち上げる)
- 仰向け膝回し(股関節の可動域改善)
- サイドレッグレイズ(中殿筋の強化)
これらの動きを通じて、膝を支える筋群全体の協調性を引き出すことが目的です。回数よりも「ゆっくり、正しく動かす」ことを意識すると効果が高まりやすくなります。
入浴と冷やさない習慣で“回復体質”へ
慢性的な筋緊張や疲労感が抜けないと感じている方には、冷却よりも“温め”を取り入れた生活を推奨しています。
たとえば、
- 38〜40℃のぬるめのお湯で15〜20分ほど入浴する
- 湯船に浸かりながらストレッチを軽く行う
といったシンプルな工夫で、筋肉の柔軟性や血流の改善が期待できます。
冷房の効いた部屋で過ごすことが多い季節には、特に体を冷やさない意識が大切です。
ランニングフォームとシューズの見直しも重要
フォームや道具も、実は再発予防において見逃せないポイントです。
膝への負担を和らげるために、
- 踵からの着地でなく、ミッドフット着地を意識する
- シューズのクッション性やフィット感を確認する
といった視点で見直していくことが有効です。
当院ではランニングフォームや足底の荷重バランスについても、必要に応じて動画解析やインソールの相談などを通じてアドバイスを行っています。
#臀筋ストレッチ
#ヒップリフトで筋力強化
#冷やさず温める習慣
#ランニングフォームの改善
#自宅ケアで再発予防
5.当院が考える根本改善までのロードマップ

まずは“湿布”で一時的な痛みの緩和を
「とりあえず湿布を貼っておきました」という方は少なくありません。確かに、腫れや熱感がある時期には、湿布やアイスパックによる冷却が役立つ場面もあります。
当院では、湿布を「痛みの場所を明確にするための目印」や「マッサージ前の準備」として活用することもあります。とくに急性期には、局所の感覚過敏を和らげる目的で一時的に使うこともあります。
ただし、湿布だけで根本的な負担軽減にはつながらないため、あくまで“最初の一歩”として考えています。
次に行うのは“原因に迫るための検査と施術”
湿布で一時的に和らいだとしても、痛みの“元”が残っていれば、再発するリスクは高くなります。
当院では、まず問診と動作観察、触診によって、体全体のバランスを把握します。特に大殿筋や中殿筋、大腿筋膜張筋の状態、骨盤の傾き、脚長差などをチェックし、負担が集中しているポイントを明確にしていきます。
そのうえで、
- 臀筋や腸脛靭帯への筋膜リリース
- 骨盤や下肢のアライメント調整
- モビリティ改善のための関節アプローチ
といった施術を組み合わせ、痛みの発生要因に包括的にアプローチします。
この流れを通じて、自然とセルフケアの意識も持ちやすくなっていくのが、当院の大きな特徴です。
再発予防のカギは“継続的なチェックとケア”
施術で一度楽になったとしても、日常生活の中で少しずつ歪みや筋バランスが戻ってしまうことがあります。
だからこそ、当院では「月に1回程度の定期チェック」をおすすめしています。姿勢や可動域の変化、筋緊張の状態などをチェックしながら、今の状態にあったセルフケアや生活習慣の調整を一緒に見直していきます。
「不調が起こる前に予防する」
そんな視点を持てると、ランニングの継続や仕事のパフォーマンス維持にもつながりやすくなります。
#湿布の正しい使い方
#根本改善アプローチ
#筋膜リリースとアライメント調整
#再発予防の定期チェック
#整体とセルフケアの連携
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

瑞慶山 良二
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


