荒川院へのご予約
スタッフブログ

打撲にサポーターは効果的?専門家が解説する正しい使い方と注意点
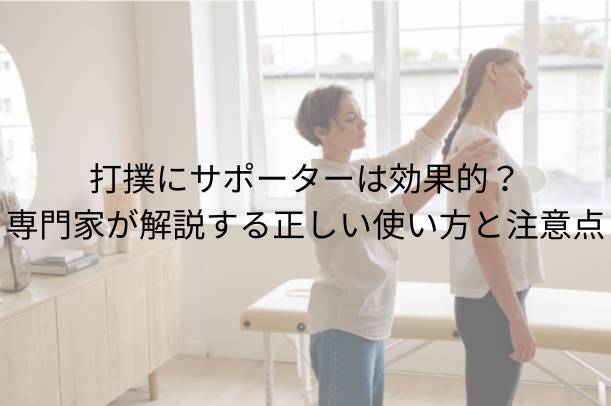
目次
打撲とは?その症状と治癒過程

打撲って、そもそもどんな状態?
「転んだあと、じんじん痛む」「ぶつけたところが青くなった」——そんな経験、誰にでもあると思います。これは典型的な“打撲”の症状です。打撲とは、外部から強い衝撃を受けたときに、骨ではなく皮膚や筋肉、血管などの軟部組織が損傷してしまった状態を指します。
よくあるのが、家具の角に足をぶつけたり、スポーツ中に他人と接触して転倒したりしたとき。骨折や脱臼とは異なり、明確な変形がないことが多いため軽視されがちですが、打撲もれっきとしたケガのひとつです。
打撲の主な症状は?
「痛いけど我慢できるから」と放置しがちですが、打撲は以下のような症状を伴います。
- 打った部位に鈍痛がある
- 内出血によって皮膚が青紫色に変色する
- 押すと痛みが強くなる
- 腫れが生じる
- 関節や筋肉を動かしにくくなる
特に太ももや腕など、筋肉の多い部位は強く打つと“筋挫傷”といって筋肉が裂けるようなケースもあるため、注意が必要です。
治癒の流れ:打撲はどうやってよくなる?
打撲の回復過程は、大きく3段階に分けて考えられています。
- 炎症期(受傷直後〜約72時間)
痛みや腫れが強く、内出血が進行する時期。安静とアイシング(冷却)が基本とされています。 - 修復期(3日目〜2週間程度)
体が損傷を修復しはじめる時期。腫れが落ち着き、皮膚の色が徐々に黄色や緑に変わっていくのが特徴です。 - 再生期(2週間以降)
損傷した組織の再生が進み、痛みや可動域制限も徐々に軽減していきます。軽いストレッチやリハビリを取り入れることが効果的とされています。
当院の見解と対応について
整体oasisでは、打撲に対して「痛みのある部位だけを施術する」という短絡的なアプローチではなく、衝撃の影響が出ている周辺の筋膜や神経の状態を広く検査し、体全体のバランス調整を重視しています。
- 【検査】筋膜の滑走障害、関節の可動性、神経系の緊張などを総合的にチェック
- 【施術】深層筋アプローチ、筋膜リリース、神経モビライゼーションなどを組み合わせ
- 【セルフケア】腫れが引いてからの軽いエクササイズや、リンパの流れを促すストレッチなどを指導
とくに回復期には、サポーターを活用しながら適度な運動や生活習慣の見直しを行うことで、より早く機能回復へ向かいやすくなります。
#打撲の症状
#腫れと内出血のメカニズム
#炎症期と修復期の違い
#整体的アプローチ
#セルフケア指導付き
サポーターの基本的な役割と効果

サポーターって、どんな役割があるの?
「打撲したらサポーターを使ったほうがいいの?」と疑問に思ったことはありませんか?サポーターは、患部を安定させたり、痛みを和らげたりするための補助具です。具体的には、以下のような効果が期待されています。
- 関節や筋肉の保護:外部からの衝撃を和らげ、再度の怪我を防ぐ。
- 圧迫による腫れの軽減:適度な圧迫が血流を調整し、腫れを抑える。
- 保温効果:患部を温め、血行を促進する。
- 動きの制限:過度な動きを防ぎ、安静を保つ。
打撲に対するサポーターの効果と使用時の注意点
打撲後の痛みや腫れを和らげるために、サポーターの使用が推奨されることがあります。しかし、使用する際にはいくつかの注意点があります。
- 効果的な使用タイミング:急性期を過ぎた後の回復期に使用するのが望ましい。
- 適切な圧迫の重要性:過度な圧迫は血流障害を引き起こす可能性があるため注意が必要。
- 長時間の使用は避ける:筋力低下や依存を防ぐため、必要な時だけ使用する。
- サポーターの選び方:患部の部位や症状に応じた適切なサポーターを選ぶ。
整体oasisのアプローチと施術方法
整体oasisでは、打撲に対して以下のようなアプローチを行っています。
- 多角的な検査:筋肉、関節、神経、生活習慣などを総合的に評価。
- 施術方法:筋膜リリース、関節調整、神経モビライゼーションなどを組み合わせた個別対応。
- セルフケア指導:自宅でできるストレッチやエクササイズの指導。
- 再発予防:生活習慣の改善や姿勢指導を通じて再発を防ぐ。
サポーター選びのポイント
サポーターを選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
- サイズの確認:適切なサイズを選ぶことで、効果的なサポートが得られます。
- 素材の選択:通気性や保温性など、使用目的に合った素材を選びましょう。
- 装着感の確認:長時間の使用を考慮し、快適な装着感のものを選ぶことが大切です。
#サポーターの役割
#打撲の回復
#整体oasisの施術
#セルフケア指導
#サポーター選びのポイント
打撲に対するサポーターの効果と使用時の注意点

「サポーターって、いつ使えばいいの?」——タイミングが肝心です
打撲をしたあと、痛みや腫れがあると不安になりますよね。「早く回復したいから」とサポーターをすぐに巻いてしまう方も多いですが、実はそれが逆効果になることもあるんです。
一般的に、サポーターが効果的とされるのは「回復期」に入ってから。つまり、打撲直後の強い腫れや内出血が落ち着き始めたころです。初期段階では、冷却(アイシング)と安静が重要とされています。
使用する際に気をつけたいポイント
- 圧迫しすぎないこと
サポーターは適度な圧迫が理想です。きつく巻きすぎると血流が悪くなり、かえって治りにくくなります。 - 長時間つけっぱなしにしない
サポーターを長く着けたままだと、筋肉が怠けてしまうこともあります。日中だけ使って、夜間は外すといった工夫が必要です。 - 清潔を保つ
汗などで蒸れると皮膚トラブルの原因になるので、こまめに洗濯し、装着部位の肌も清潔に保ちましょう。 - 違和感があればすぐ外す
装着後にしびれや痛みが出るようなら、使用を中止するのが無難です。
整体oasisが考える「サポーターの使いどころ」
当院では、サポーターを「万能な道具」としてではなく、「あくまで補助的な役割」として捉えています。筋膜の緊張や神経の過敏状態が続いている場合は、サポーターだけでは不十分なケースもあるからです。
そのため、まずはしっかりと状態を検査し、どのタイミングでどのような使い方をすれば効果的なのかを個別にアドバイスしています。
- 【検査】関節のズレや筋膜の癒着、神経の伝達異常を丁寧に評価
- 【施術】患部周辺だけでなく全身の連動も考慮した筋肉・関節アプローチ
- 【アドバイス】適切なタイミングでのサポーター使用、セルフストレッチや歩行指導の併用
施術と併用しながらサポーターを取り入れることで、よりスムーズな回復が期待できます。
#サポーター使用のタイミング
#圧迫の注意点
#打撲と回復期
#整体oasisの個別指導
#セルフケアとの併用
整体oasisの打撲に対するアプローチと施術方法

「湿布だけで様子見…で大丈夫?」——根本的な改善には理由があります
打撲と聞くと、「そのうち治るから放っておけばいい」と思われがちです。ですが、強い衝撃を受けた部分には、筋肉や筋膜の微細な損傷、神経の過敏、関節のずれが隠れていることも珍しくありません。
当院・整体oasisでは、表面的な痛みだけに着目せず、体の内側で何が起きているかを総合的に評価することを大切にしています。
整体oasisで行う検査の特徴
まずは、痛みの根本を見極めるために、丁寧な触診と動作チェックを行います。
- 筋肉や筋膜の硬さの確認
- 関節の可動性やアライメント(配列)のチェック
- 神経の興奮状態や圧迫の有無を評価
- 生活習慣や体の使い方の傾向もヒアリング
例えば「打撲による内出血はおさまったのに、なぜか痛みが続く」というケースでは、筋膜や神経系への影響が残っている場合があります。そのような見落とされがちな原因まで掘り下げて対応しています。
施術方法の一例
状態に合わせて、以下のような施術を組み合わせて行います。
- 筋膜リリース:癒着した筋膜を解放し、動きをスムーズに
- 神経モビライゼーション:神経の滑走性を高めて過敏状態を軽減
- 骨盤・関節調整:全身のバランスを整え、自然治癒力の働きをサポート
いずれも、ボキボキしない、痛みを伴わない優しい手技が基本です。
施術だけでは終わらない——セルフケアまで一貫サポート
当院では「受け身の改善」ではなく「再発させない体づくり」を目指しています。施術後には以下のようなセルフケアも丁寧に指導しています。
- ストレッチや軽めのエクササイズ
- 回復に向けた日常の動作の工夫
- サポーターやテーピングの使い方
「自分でも回復のプロセスに関われる」ことは、体だけでなく気持ちの安定にもつながります。
#整体的アプローチ
#根本改善の検査
#筋膜と神経の調整
#再発予防の指導
#丁寧なヒアリング
打撲回復のためのセルフケアと日常生活での注意点

「打撲は自然に良くなる」って思っていませんか?
確かに軽度の打撲であれば、何もしなくても数日で痛みが引いてくるケースはあります。ただし、早く改善を促したい場合や再発を防ぎたい場合、適切なセルフケアを行うことで回復のスピードが変わります。
整体oasisでは、日常の中でも無理なく取り組めるセルフケアを段階的に提案しています。
回復を早めるRICE処置の基本
打撲直後の急性期には、以下の処置が有効とされています(※参考:一般的な応急対応)。
- Rest(安静):無理に動かさず、患部に負荷をかけない
- Ice(冷却):氷や冷却パックで15〜20分冷やし、腫れを防ぐ
- Compression(圧迫):軽く圧迫することで出血や腫れを抑制
- Elevation(挙上):心臓より高い位置に上げて血流をコントロール
※ただし、冷やしすぎや長時間の圧迫は逆効果となることがあるため注意が必要です。
慢性化を防ぐためのセルフストレッチ
急性期を過ぎたら、関節の可動域を維持・改善するための軽いストレッチや運動が効果的です。整体oasisでは以下のような方法を提案しています。
- 太ももの前後を伸ばすストレッチ
- 膝を曲げ伸ばしする可動域エクササイズ
- ふくらはぎのマッサージで循環促進
「無理なく・気持ちよく伸ばせる範囲で」がポイントです。痛みを我慢して行う必要はまったくありません。
日常生活で気をつけたいポイント
- 同じ部位をぶつけないよう注意する
- 普段よりも歩幅を小さめにする
- 片足ばかりに体重をかけないように意識する
- 違和感があればすぐに施術者に相談する
早くよくしたい気持ちはわかりますが、「少し良くなってきたから大丈夫」と動きすぎてしまうと、かえって長引いてしまうこともあります。
整体oasisからのアドバイス
当院では、施術だけでなく「自分の体に目を向けること」を重視しています。施術後には、体の動かし方や日常での注意点を一人ひとりに合わせてご案内します。
「体の扱い方を知ること」は、痛みの予防にもつながる大切な要素です。
#打撲後のセルフケア
#ストレッチで回復促進
#RICE処置の基本
#整体oasisの生活指導
#再発予防の意識作り
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

笠井 将也
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


