荒川院へのご予約
スタッフブログ

肩甲骨の出し方|埋もれた肩甲骨を浮き出させるセルフケアと整体のポイント
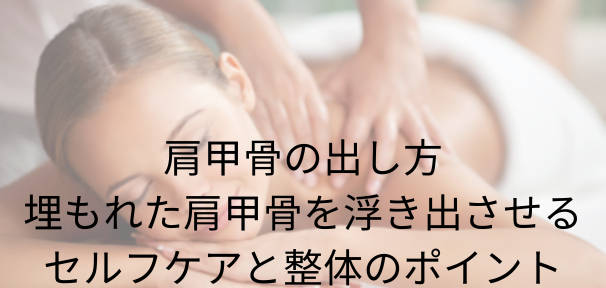
1.肩甲骨が埋もれる原因とは?

そもそも「肩甲骨が埋もれる」ってどういう状態?
「最近、肩甲骨が動かしづらい気がする」「背中が丸くなってきたかも…」そんなふうに感じたことはありませんか?
実はその感覚、肩甲骨が“埋もれている”サインかもしれません。
肩甲骨が埋もれるとは、筋肉や脂肪、姿勢のクセによって肩甲骨の可動域が狭くなり、見た目にも背中に張りついたような状態になることをいいます。肩甲骨まわりの筋肉が硬くなったり、逆に使われなくなって弱ってしまうことで、動きの悪さや違和感が出てくることもあるようです。
よくある原因① 長時間のデスクワークやスマホ操作
パソコン作業やスマートフォンの使用が長時間におよぶと、前かがみの姿勢になりがちです。この前傾姿勢が続くと、肩甲骨は外側に広がったまま固定され、背中の筋肉が使われにくくなってしまいます。
特に現代人は、仕事でもプライベートでも画面を見る時間が長くなっていますよね。その結果、自然と猫背になり、肩甲骨の可動性がどんどん失われるとも言われています。
よくある原因② 筋力の低下とアンバランス
もう一つ見落としがちな原因が、「筋力のアンバランス」です。肩甲骨の動きには、僧帽筋、菱形筋、前鋸筋など多くの筋肉が関わっています。これらが弱っていたり、一部だけが過剰に緊張していたりすると、スムーズな動きを妨げてしまうのです。
たとえば、胸の筋肉(大胸筋)が硬くなって縮こまっていると、肩甲骨が内側に引き寄せられず、背中側に埋もれたような状態になります。
整体oasisの見解とチェックポイント
当院では、肩甲骨の可動域の低下や姿勢の歪みは「体幹バランスの崩れ」と関連していると考えています。
具体的には、以下のようなチェックポイントを重視して評価します:
- 肩甲骨の位置(左右差・高さ)
- 背骨と肩甲骨の距離感
- 肋骨の動きと肩甲骨の連動性
- 筋肉の左右バランス(特に広背筋や前鋸筋)
施術では、筋膜リリースや関節モビリゼーションを用いながら、肩甲骨が自由に動ける土台づくりを目指します。また、ストレッチや軽めの運動を通して、セルフケアもお伝えしています。
放置すると起こるかもしれないこと
肩甲骨が埋もれた状態をそのままにしておくと、肩こりや首の痛みだけでなく、頭痛や腕のしびれにつながることもあります。早い段階で肩甲骨の状態に気づき、整えておくことが予防の第一歩です。
#肩甲骨の埋もれ
#猫背姿勢
#筋力低下
#肩こり予防
#整体アプローチ
2.肩甲骨の状態をセルフチェックする方法

肩甲骨の可動性、普段どれくらい意識していますか?
「肩甲骨、ちゃんと動いてますか?」と言われても、なかなかピンとこない方が多いと思います。実際、自分の肩甲骨がスムーズに動いているのか、埋もれているのかって、普段の生活では意識しづらい部分ですよね。
でも、チェック方法は意外とシンプルです。道具も不要で、壁さえあればすぐに確認できます。さっそくやってみましょう。
簡単!壁を使った肩甲骨セルフチェックの手順
- 壁に背をつけて立ちましょう
かかと・お尻・背中・後頭部を壁につけた「良い姿勢」で立ちます。 - 両腕を肩の高さまで前方に伸ばします
手のひらは床に向けるようにします。 - そのままゆっくり腕を上に上げていきます
腕と肩の角度を確認しながら、無理のない範囲で動かします。
角度で見る肩甲骨の状態の目安
- 60〜90度まで上がる:肩甲骨の動きや筋肉の柔軟性が保たれています。
- 0〜60度までしか上がらない:肩甲骨周囲の筋肉が硬くなっていたり、関節の動きが制限されている可能性があります。
左右で動きに差がある場合も、筋力のアンバランスや姿勢の歪みが影響していると考えられます。
整体oasisではこう見ます
当院では、こうした簡易的なセルフチェックだけでなく、
・肩甲骨の可動域(前方・上方・回旋動作)
・肩関節と肋骨の連動性
・肩甲胸郭関節の滑走性
・筋膜の張力バランス
など、複数の視点から評価します。
特に、肩甲骨が“動かない”のではなく“動きたくても動けない状態”になっている方が多く、筋肉だけでなく、関節や神経との連動性も含めて見ていくことが大切だと考えています。
セルフチェックを活かすには
このチェックを定期的に行っておくことで、肩甲骨まわりの変化に気づきやすくなります。もし動かしづらさを感じたり、違和感が続くようであれば、無理に動かそうとせず、専門家に相談されるのが安心です。
当院では、施術前にこうした動作チェックを通して、原因を明らかにしながら最適なケアをご提案しています。
#肩甲骨チェック
#肩甲骨の出し方
#猫背改善
#肩の柔軟性
#整体セルフケア
3.肩甲骨を浮き出させるためのセルフストレッチ

肩甲骨って、意識しないと意外と動かせない?
「ストレッチしても肩こりが楽にならない…」そんなときは、肩甲骨まわりの柔軟性が低下しているサインかもしれません。
肩甲骨は、背中側で自由に動く“浮き骨”とも呼ばれ、姿勢や肩の動きに大きく関係しています。
ただ、日常生活の中で意識して動かす機会が少ないため、少しずつ可動性が失われていく方が多いようです。
毎日できる簡単ストレッチ① 両手を前に伸ばして引き上げる
- 背筋を伸ばして立ちます
- 両手を組んで前方へまっすぐ伸ばします
- そのまま斜め上に向かってゆっくりと腕を持ち上げていきましょう
この動きで、肩甲骨が外側に引っ張られ、背中全体が気持ちよく伸びるのを感じられると思います。深呼吸をしながら10秒キープし、数回繰り返すのがポイントです。
毎日できる簡単ストレッチ② 壁を使って片手伸ばし
- 壁の横に立ち、片手を肩の高さで壁に添えます
- 手を壁につけたまま、体を少し前傾させます
- 胸や脇がじんわり伸びているのを感じたら10秒キープ
肩甲骨の内側〜外側にかけてストレッチされるため、縮こまりがちな前側の筋肉にもアプローチできます。
整体oasisの視点とストレッチへのアドバイス
当院では、肩甲骨を“動かせる状態”をつくることを第一に考えています。
ただ伸ばすだけではなく、以下のような点にも注目しています。
- 呼吸と筋膜の連動性(呼吸が浅いと肩甲骨も動きづらい)
- 骨盤・肋骨・肩の連動(上半身だけでなく土台の安定が必要)
- 筋肉の滑走性や可動域の左右差(特に前鋸筋や広背筋の硬さ)
当院の施術では、ストレッチと並行して、こうした深層部分にもアプローチしながら全身のバランスを整えています。施術後に自宅でできるストレッチ方法も丁寧にお伝えしています。
ストレッチは“習慣化”がカギ
ストレッチは1回やって終わりではなく、続けることで効果を実感しやすくなります。朝の目覚めや夜のリラックスタイムに取り入れるのがおすすめです。
「肩甲骨が動きやすくなると、なんだか呼吸もしやすくなった」
そんな声をいただくことも多く、日常の快適さにもつながっています。
#肩甲骨ストレッチ
#猫背対策
#肩こり予防
#可動域改善
#整体セルフケア
4.整体oasisの独自アプローチ

「肩甲骨が動かない原因」を1つの視点だけで判断しない理由
「肩甲骨が動きにくい」「いつも同じ場所がこる」…
そんな症状の背景には、筋肉だけでなく、骨格の歪みや神経伝達の乱れ、栄養・生活習慣といったさまざまな要素が絡んでいます。
整体oasisでは、症状の“見える部分”だけではなく、全体のバランスや動きの連動性に注目して検査・施術を行っています。
当院が重視する検査ポイントとは?
まずは以下のようなポイントを丁寧にチェックします:
- 肩甲骨の位置と可動域(上下・内外・回旋)
- 肋骨と肩甲骨の動きの連動性
- 筋膜の滑走性、筋肉の硬さや左右差
- 姿勢(特に骨盤・胸郭・頸椎のバランス)
- 呼吸の深さと横隔膜の働き
肩甲骨が“うまく使えていない”原因を多角的に探ることで、的確なアプローチができると考えています。
一人ひとりに合わせた施術と考え方
当院では、国家資格を持つセラピストが触診を行い、個々の体の状態に応じた施術を行います。具体的には、以下のような手技を組み合わせて施術を構成します:
- 筋膜リリース
- 肩甲胸郭関節のモビリゼーション
- 呼吸に合わせた肩甲骨アプローチ
- 広背筋や前鋸筋の調整
- 骨盤・胸郭のアライメント修正
これらの施術を通して、肩甲骨が本来持っている自由な動きを取り戻していくことを目指しています。
施術だけで終わらせない“再現性”のあるケア
施術後には、日常生活に取り入れられるセルフケア方法や、意識すべき姿勢のポイントもお伝えしています。
・短時間でできる肩甲骨ストレッチ
・呼吸を深めるリズム運動
・座り姿勢や腕の位置の見直し
などを実践することで、再発を防ぐ土台づくりにもつながっていきます。
「専門家に任せきり」ではなく、「自分の体を自分でも守れる状態」に導くことを大切にしています。
#肩甲骨整体
#肩甲骨の可動域
#整体アプローチ
#国家資格セラピスト
#肩こり根本改善
5.日常生活でのセルフケアと注意点

肩甲骨ケアは「日常のちょっとした習慣」から
「肩甲骨の柔軟性って、どうやって保てばいいの?」
よくいただくご質問のひとつですが、答えはとてもシンプルです。特別な道具や激しい運動は必要なく、日々の“ちょっとした意識”を積み重ねていくことが大切と言われています。
たとえば、長時間同じ姿勢を続けないこと。これだけでも肩甲骨まわりの硬さを防ぐひとつの方法になります。
姿勢を整えるだけでも肩甲骨は動きやすくなる?
実は、肩甲骨が固まってしまう原因の多くが「姿勢の崩れ」なんです。特に、猫背気味の姿勢や、前かがみでのスマホ操作が習慣化している方は要注意。
椅子に座るときは、お尻を深く入れて、骨盤を立てる意識を持つと自然と背筋が伸び、肩甲骨も正しい位置に戻りやすくなります。
こまめなストレッチで“肩甲骨リセット”
・両手を肩に添えて肘を大きく回す
・手を後ろで組んで胸を開く
・肩甲骨を意識して上下にゆっくり引き上げる
こうした動きは1分もかからずできるものばかり。朝起きたとき、仕事の合間、寝る前などに取り入れてみてください。大切なのは「毎日少しずつ続けること」です。
こんなときは無理せず専門家に相談を
もしストレッチや姿勢改善を試してみても、「違和感が消えない」「動かすと痛みがある」といった場合には、無理をせず専門家に相談されることをおすすめしています。
整体oasisでは、施術前に必ず体の状態を確認し、どの部分に負荷がかかっているのか、どんなクセが影響しているのかを丁寧に見極めます。そして、施術と並行して、生活習慣に応じたセルフケア方法もアドバイスいたします。
「気づいて、動かす」それが何よりの予防法
肩甲骨は“動かさないとどんどん動かなくなる”と言われています。
だからこそ、ちょっとした違和感に気づいたタイミングでセルフケアを始めることが大切です。
毎日の中に少しだけ時間を作って、自分の体と向き合う習慣をつけていきましょう。続けるうちに、きっと肩まわりが軽くなってくるはずです。
#肩甲骨ケア
#姿勢意識
#ストレッチ習慣
#セルフメンテナンス
#肩こり対策
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

瑞慶山 良二
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


