荒川院へのご予約
スタッフブログ

顎のストレッチでスッキリ!あごのこり・痛みを和らげる簡単セルフケア法とは?
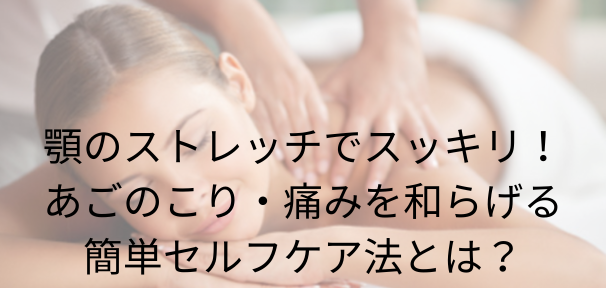
目次
1.顎のストレッチが注目される理由とは?

最近、「顎がだるい」「口が開けにくい」といった声をよく耳にしませんか?
それ、実はあご周辺の筋肉が固まってしまっているサインかもしれません。
「でも、ストレッチって肩とか腰の話じゃないの?」と思う方も多いと思います。
実は、顎まわりも肩や首と同じように、筋肉が集まり、日常の動きの影響を受けやすい部位なんです。
とくに最近は、食いしばりやスマホ操作が増えたことで、あごの筋肉に負担がかかるケースが増えてきています。
こういった背景もあり、「顎のストレッチ」が注目されているのだとか。
口を大きく開けたり、舌を使った動きを取り入れたりと、実はシンプルな動きでもあご周辺の筋肉がじわっとほぐれていく感覚が得られることがあるようです。
当院(https://athletic.work)では、顎の違和感を感じている方に対して、あご単体だけでなく、首や背中、噛み癖なども含めた全身のバランスから状態をチェックします。
顎まわりだけをゆるめても一時的にしか楽にならないケースが多いため、姿勢や筋膜のつながりをふまえたアプローチが必要だと考えています。
「これくらい大丈夫」と思っていても、放っておくと頭痛や首こりにつながることもあるので、できる範囲でのセルフケアは意外と大事かもしれません。
あご周りが固くなると起こる不調とは?
「朝起きたら、口が開きづらい…」そんな経験、ありませんか?
実はこれ、顎の筋肉がこわばってしまっている状態かもしれません。
よくある症状としては、
- 口が開けづらい、あくびをすると痛い
- 顎の周辺がだるい、重たい
- 頬のあたりがピクピクする
- 食事のとき片側ばかりで噛んでしまう
- 頭痛や肩こりがなかなか取れない
といったものがあります。
顎まわりの筋肉は、顔だけでなく首や肩ともつながっているため、放っておくと別の部位にまで影響が出てしまうこともあると言われています。
さらに、無意識に食いしばっている方や、仕事で長時間パソコン作業をする方ほど、こうした状態が続きやすい傾向があります。
当院では、顎に関係する筋膜の緊張や姿勢の崩れ、呼吸の状態なども含めて確認しながら、整体施術を行います。
また、顎を支える首〜胸にかけてのラインが固くなっているケースも多いため、局所だけでなく全身からアプローチすることで、根本的な改善をめざしています。
現代人に増えている「顎のこり」の原因
「昔はこんなことなかったのに…」
最近になって顎まわりが気になるようになった、という声も少なくありません。
その背景には、以下のような現代的な生活習慣が関係していると考えられています。
- 長時間のスマホやパソコン操作(うつむき姿勢)
- ストレスによる食いしばりや歯ぎしり
- 柔らかい食事中心で噛む回数が減少
- 無意識のうちに片側ばかりで噛む癖
- 寝ている間の枕の高さや姿勢のくせ
こういった要因が積み重なることで、あごまわりの筋肉が固まり、こりや痛みにつながる場合があるそうです。
また、顎関節症などを抱えている場合、セルフケアでは対応が難しいケースもあります。
そのため、当院では「まずどこに原因があるのか?」という視点から、触診や姿勢・動きのチェックを通して原因を見極めたうえで、必要に応じてストレッチや整体を行っています。
ひとつひとつは些細なことでも、積み重ねると違和感や不調として現れてくることがあるため、「最近、少し気になるな」と思ったタイミングで見直してみるのもよいかもしれません。
#顎ストレッチ
#口の開けづらさ対策
#食いしばりケア
#整体アプローチ
#スマホ首との関係
2.セルフでできる!基本の顎ストレッチ3選

「顎が固いな…」と感じたとき、すぐにでもできるのがセルフストレッチです。
でも、「具体的にどんな動きをすればいいの?」と迷う方も多いと思います。
ここでは、自宅やオフィスでも気軽にできる顎まわりのストレッチを3つご紹介します。どれもシンプルな動きなので、ぜひ試してみてください。
口をゆっくり開閉するストレッチ
これは、あご周辺の筋肉をやさしく動かすための基本的なストレッチです。
方法としては、以下のような流れになります。
- 背筋を伸ばしてイスに座る
- ゆっくりと口を縦に開け、限界の手前で止める
- そのまま3秒キープして、またゆっくり閉じる
- これを5〜10回繰り返す
ポイントは「勢いをつけないこと」。あくまでゆっくり、痛みの出ない範囲で動かすことが大切です。
舌を使った顎まわりほぐし
顎とつながっている「舌の筋肉」を使うことで、深部の筋肉までアプローチしやすくなります。
- 舌先を上あごの前歯の裏につける
- 舌を上に押しつけるようにして3秒キープ
- 力を抜いて、舌をリラックスさせる
- これを5回ほど繰り返す
地味な動きですが、首〜顎まわりの深層筋がじんわりほぐれる感覚があるかもしれません。
首〜あご下の筋肉を伸ばすストレッチ
首の前側やあご下の筋肉も、顎の動きに大きく関わっています。
- あごをゆっくり上に向けて、天井を見る
- 下唇を上に突き出すようにして3秒キープ
- ゆっくり元の位置に戻す
- これを5回ほど繰り返す
この動きは、首の前面からあごにかけてのラインにじわっと伸びを感じやすいストレッチです。
慣れないうちは無理に引っ張らず、気持ちよさを感じる範囲で行ってくださいね。
当院(https://athletic.work)では、こうしたセルフケアの指導も、検査結果に応じて個別に行っています。
例えば「片方だけ固い」「左右の動きが違う」といった場合、一般的なストレッチではかえってバランスを崩す可能性もあるため、体の状態を把握したうえで調整していくことが大切だと考えています。
「なんとなく動かしてみたけど、いまいち効果を感じない…」
そんな方には、体の連動性や姿勢も含めたアドバイスが必要かもしれません。
#顎ストレッチ方法
#舌筋トレーニング
#首の前側を伸ばす
#セルフケア指導
#整体と組み合わせるケア
3.ストレッチだけじゃない!顎の不調を和らげる日常習慣

「ストレッチしてみたけど、すぐ戻っちゃう気がする…」
そんなふうに感じたことはありませんか?
実は、顎のこりや痛みは一時的な筋肉の緊張だけではなく、毎日の何気ない習慣によっても影響を受けていると言われています。
ここでは、あごまわりの不調を和らげるために意識したい日常習慣を紹介します。
無意識の「食いしばり」を防ぐには?
「集中しているとき、気づいたら奥歯をぐっと噛んでる…」という方、意外と多いのではないでしょうか?
食いしばりは、知らず知らずのうちにあごの筋肉に大きな負荷をかけていることがあると言われています。
対策としては:
- リラックス時に上下の歯を軽く離す意識をもつ
- 舌を上あごに軽く触れさせておくことで筋緊張を予防
- ガムなどを無意識に噛み続ける癖を見直す
- デスクワーク中の手の位置や姿勢を調整する
当院では、こうした「無意識の食いしばりパターン」を見つけるために、問診とあわせて首〜あごの動き方や、顔まわりの筋肉の使い方も観察しています。
施術によって筋肉をゆるめるだけでなく、日常の行動を見直すアドバイスもお伝えしています。
スマホ姿勢や噛み癖の見直しも重要
長時間のスマホ使用による“うつむき姿勢”は、首から顎にかけての筋肉を常に引っ張る状態をつくるため、顎のこりや違和感につながることがあるそうです。
また、片方ばかりで食事を噛む癖があると、左右の筋肉バランスが崩れて、顎のズレや噛み合わせの変化を引き起こす可能性もあると言われています。
日常で意識したいポイントとしては:
- スマホの画面をなるべく目線の高さで見る
- 食事は左右均等に噛むように意識する
- 枕の高さや寝姿勢にも注意する
当院では、姿勢のクセや体の使い方を全体から見直しながら、顎まわりの不調にアプローチしています。
「なんとなく違和感がある」「なぜか再発する」という方は、こうした生活習慣にも目を向けてみると、ヒントが見つかるかもしれません。
#食いしばり防止
#スマホ首と顎の負担
#噛み癖改善
#姿勢チェック
#整体的セルフケア
4.顎の違和感が長引く場合はどうする?

「しばらくストレッチを続けてみたけど、あまり変わらないかも…」
そんなときは、セルフケアだけで対応するのが難しい状態かもしれません。
あごまわりの不調には、軽度の筋肉のこりから顎関節症などの症状までさまざまなケースがあり、原因によって対処方法も変わってくることがあると言われています。
ここでは、セルフケアで改善が見られないときの目安や、相談先の選び方についてお伝えします。
セルフケアで改善しない時に考えられること
セルフストレッチや生活習慣の見直しをしてもなかなか変化が感じられないときは、次のようなことが関係している可能性があります。
- 顎関節自体のゆがみやズレ
- 骨格のバランス不良による筋肉の過緊張
- 首〜肩の筋膜ラインの強い癒着
- 神経の圧迫や噛み合わせの問題
とくに、口を開けると「カクッ」と音がしたり、痛みが強くなったりする場合は、自己判断せずに一度専門家に相談することがすすめられています。
当院では、まず姿勢や動きのクセ、筋肉のバランス、顎関節の可動域などを丁寧に検査したうえで、「どこに問題があるか」を見極めていきます。
必要に応じて、首や胸郭の動き、呼吸の状態も確認しながら施術計画を立てていくことが多いです。
病院や整体など、相談先の目安
では、「どこに行けばいいの?」と迷ったとき、どんな判断基準があるのでしょうか?
- 顎の動きに制限がある・音が鳴る・痛みが強い場合 → 歯科や口腔外科など医療機関での診察が優先
- 全体的にだるい、重い、違和感が取れない場合 → 整体などで体全体のバランスを整える選択肢も
当院では、顎の不調で来院された方の多くが「他の整体で首だけほぐされたけど変わらなかった」「痛いところしか見てもらえなかった」とおっしゃいます。
そのため、局所にとらわれず、頭〜首〜背中〜骨盤にかけてのつながりや、日常姿勢まで含めた施術を大切にしています。
また、施術後はご自身でもできるセルフケアをお伝えしているので、「何をすればいいかわからない」と感じている方でも、続けやすい環境を整えています。
#顎の痛みが続くとき
#整体と病院の違い
#セルフケアの限界
#顎関節の動きチェック
#当院の検査ポイント
5.当院での整体アプローチとセルフケア指導の例

「どこへ行っても同じ」「マッサージでは良くならなかった」
そんなお声をいただくこともありますが、当院では“顎だけを見る”のではなく、“体全体の使い方やクセを観察する”ことを大切にしています。
顎の不調がある方の多くは、実は首・背中・骨盤など、他の部位の影響を受けているケースも多いと言われています。
ですので、「痛い部分を緩める」だけでは、根本的な改善につながらない場合があるのです。
姿勢から整える整体施術
当院のアプローチは、まず姿勢チェックから始まります。
正面・側面・背面から立ち姿を確認し、頭の位置、肩の高さ、重心のバランスなどを見ながら、どこに負担が集中しているのかを検査していきます。
特に多いのは「頭が前に出ている姿勢」や「片方に傾いた姿勢」。
これらが習慣化していると、顎まわりの筋肉に常に負荷がかかり、こりやズレにつながる可能性があります。
そのため、背骨や骨盤のポジションを調整することで、顎への余計な緊張を減らしていくのがポイントです。
筋膜や関節の調整による顎まわりの改善
顎関節まわりは、咀嚼筋(そしゃくきん)や舌骨筋群などの細かい筋肉が複雑に関係しています。
当院では、筋膜リリースや関節モビライゼーションなどの手技を使って、緊張の強い部分や癒着している部分に対して丁寧に施術を行います。
「パキッ」と鳴らすような施術ではなく、あくまでソフトで丁寧な手技を重視しており、顎の動きに関連する首〜鎖骨〜胸のラインまで広範囲を調整していくスタイルです。
ご自宅で継続できるストレッチ指導
施術のあとは、再発予防や維持のためのセルフケアも重要です。
当院では、その方の体の使い方や筋肉のバランスに応じて、簡単に取り組める顎まわりのストレッチや姿勢改善エクササイズをお伝えしています。
たとえば、
- 寝る前に顎をゆるめる深呼吸法
- 舌とあごを使った筋活性エクササイズ
- 首の前側をやさしく伸ばすストレッチ
など、短時間でもできる内容を中心にご提案しています。
「その場しのぎではなく、長期的に改善したい」
そんな方にこそ、当院の整体アプローチは向いているかもしれません。
#整体アプローチ
#姿勢から整える
#筋膜リリース
#顎ストレッチ指導
#根本改善サポート
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

瑞慶山 良二
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


