荒川院へのご予約
スタッフブログ

手の痺れの原因は?よくある症状と受診の目安をわかりやすく解説
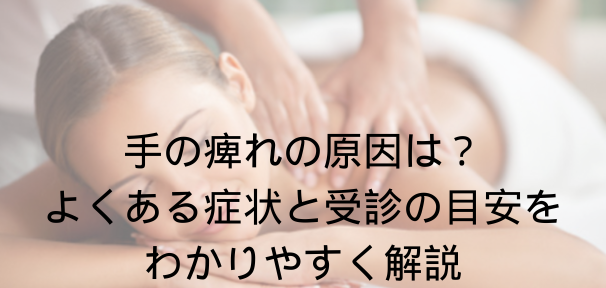
手の痺れとは?よくある症状のパターンと特徴

「手がピリピリする」「指先がジンジンする」──こんな感覚、経験したことはありませんか?
手の痺れといっても、その感じ方は人それぞれ。電気が走るような「ビリビリ」、虫が這うような「チクチク」、しびれと同時に脱力感や重だるさを伴う場合もあります。
実はこれ、神経のどこで刺激や圧迫が起こっているかによっても症状の出方が変わってくるといわれています。
たとえば、長時間パソコンを使ったあとに手がジーンとするケースでは、首や肩まわりの緊張が関係している可能性があります。
また、冷えによって血流が悪くなっている場合でも、似たような感覚が出やすいとされており、季節や体調によって波がある方も少なくありません。
当院では、表面的な感覚だけで判断せず、手だけでなく肩・背中・首の連動を確認しながら、筋膜の状態や関節の可動性、神経の流れなどを細かくチェックしています。
これにより、「一見ただの疲れかな?」という違和感の中にも、体全体のバランスの崩れが隠れていることが見えてくる場合があります。
片手だけ?両手?指のどこに出るかで違う可能性も
「右手だけが痺れる」「小指から薬指にかけてジンジンする」など、痺れの出方には偏りがあります。
実は、この“どこに出るか”が状態を見分けるうえでとても大切なポイントなんです。
たとえば、小指や薬指だけがしびれる場合は、肘の内側を通る「尺骨神経」が関係している可能性があるといわれています。
一方で、親指~中指にかけてのしびれなら、「手根管症候群」と呼ばれる状態が疑われるケースも。
また、両手の対称的なしびれがある場合は、首の骨や神経への圧迫や、全身の代謝やホルモンバランスの影響も考えられるそうです。
当院では、問診だけでなく、首の可動域テストや筋力チェック、腕を特定の位置に保ったときの神経反応テストなどを組み合わせて、原因の見極めを行います。
ご自身では気づきにくい姿勢の癖や、神経の滑走性の低下なども、実際に触れてみると見えてくるものがあるんです。
セルフケアとしては、首や肩甲骨まわりをやさしく回すストレッチを取り入れてみるのもひとつの手。
ただし、強く押したり無理に伸ばしたりするのではなく、「少し気持ちいい」と感じる程度を意識して行うのがポイントです。
#手の痺れの種類
#ビリビリジンジンの感覚
#指の部位ごとの違い
#神経と姿勢の関係
#整体でのチェックポイント
手の痺れの主な原因とは

手がしびれると、「何か大きな病気なのかな…」と不安になってしまうこともありますよね。でも、実際には日常の些細な習慣や筋肉の緊張が関係していることも少なくありません。ここでは、代表的な原因を3つの視点から整理してお伝えします。
首や肩のこり・神経の圧迫によるもの
「デスクワークが続いた後に、指先がジーンとする…」
こんな経験はありませんか?
これは、首まわりや肩の筋肉がこって、神経を圧迫している状態かもしれません。
特に、首の骨(頸椎)のゆがみや関節の可動性低下があると、神経の通り道が狭くなり、腕や指先にしびれが出ることがあri
ます。
当院では、首や肩の可動域検査、肩甲骨の位置、筋膜の滑り具合などを丁寧にチェックしながら、どこで神経の圧迫が起きているかを見極めていきます。
首だけでなく、腕の使い方や猫背といった姿勢のクセも、神経の通り道を狭くする要因になるため、全体のバランスを見ながらアプローチしています。
脳や神経の疾患に関係するケース
片側の手だけでなく、同じ側の足もなんとなくしびれるような場合、脳の中枢が関わっている可能性もあります。
脳梗塞や一部の神経疾患では、初期症状として手のしびれが出ることも報告されています。
もちろん、こうした重篤な病気は誰にでも起こるわけではありませんが、「手だけでなく他の部位もしびれている」「ろれつが回らない」「力が入らない」などの症状がある場合は、速やかに専門の医療機関での検査がすすめられています。
当院では、重篤な病気の可能性が疑われる場合は、連携している医療機関をご案内し、安心して検査が受けられるような体制も整えています。
糖尿病・更年期・ストレスなど全身状態との関係
しびれというと「神経」や「筋肉」の問題と思いがちですが、実は内科的な背景が関係していることも。
たとえば、糖尿病による末梢神経障害や、女性ホルモンの変化による自律神経の乱れ、ストレスによる血流低下なども、しびれの一因といわれています。
当院では、体の状態や生活背景もヒアリングしながら、「外から見える問題」と「中からくる不調」の両面に目を向けています。
その上で、血流や筋肉の緊張に配慮した施術や、呼吸・睡眠・水分摂取のセルフケアについてもご案内しています。
体質や日々の習慣も含めて整えていくことで、症状が少しずつ落ち着いていく方もいらっしゃいます。
#手のしびれ原因
#首肩こりと神経圧迫
#脳神経疾患との関係
#内科的な背景の影響
#全体バランスを整える整体アプローチ
どんなときに病院へ行くべき?来院の目安と診療科の選び方

「これくらいのしびれなら大丈夫かも…」と様子を見ているうちに、実は状態が進行してしまっていた…というケースもゼロではありません。
とはいえ、すぐに医療機関を受診すべきか、自分でケアできる程度か、判断が難しいこともありますよね。
ここでは、来院の目安や注意したいサイン、どの診療科に相談すればいいのかといった点を整理してみましょう。
放っておくと危険なしびれの特徴
しびれは一時的なものもありますが、以下のような特徴がある場合は注意が必要といわれています。
- 手以外の場所(顔や足など)にもしびれが広がっている
- 力が入りづらく、ペンを握る・ボタンを留めるといった動作がしづらい
- 言葉が出にくい、めまい、ふらつきなどが併発している
- 安静にしていてもしびれが続く、夜間に悪化する
こうした症状がある場合、神経の障害や脳の病気などの可能性も考えられるとされており、早めの専門的な検査がすすめられています。
整形外科・脳神経内科など科目ごとの特徴
手のしびれで相談できる科は複数ありますが、選び方のポイントとしては「しびれがどこから来ているか」をある程度推測することです。
- 首や肩のコリが強く、腕~指先にかけて出る場合:整形外科や神経整形
- 左右差のないしびれや、全身的なだるさもある場合:内科や神経内科
- めまいや言語障害もある場合:脳神経外科や脳神経内科
当院のような整体院では、来院時の状態を丁寧に確認したうえで、必要に応じて医療機関の受診をおすすめするケースもあります。
無理に施術を進めることはありませんので、ご安心ください。
急ぐべき症状とセルフチェックのポイント
「これは急いだほうがいいのか…?」と迷ったときは、以下のセルフチェックをしてみましょう。
- 朝起きたときから強いしびれがある
- 手の感覚がなく、触っても鈍い
- 握力が極端に落ちている
- 片側の顔や足もおかしい気がする
ひとつでも当てはまるものがあれば、早めの受診がすすめられています。
また、当院では手のしびれを引き起こす筋肉や関節の状態を検査しながら、神経への負担が少ない動きや姿勢を一緒に見つけていきます。
一時的な緩和だけでなく、再発防止を視野に入れたサポートを行っているのが特徴です。
#しびれ受診の目安
#放置はNGなサイン
#整形外科と脳神経内科の違い
#セルフチェックで判断
#整体でできる早期対応
整体ではどこをチェックしてアプローチする?

「しびれ=神経の問題」と思われがちですが、実はそれだけでは見えてこないこともあります。
特に当院では、手のしびれがどのような経路で起きているのかを探るために、体全体のつながりを丁寧にチェックしていきます。
筋肉や関節、姿勢のクセまで、さまざまな視点から確認することで、根本的な原因を見極めることが目的です。
姿勢・関節・神経の流れをみる視点
まず確認するのは、姿勢と関節の使い方です。
たとえば、猫背や巻き肩があると、首~肩の前面で神経が圧迫されやすいポジションになります。
このようなケースでは、手だけでなく、姿勢全体のバランスに着目して施術を進めていくことが重要です。
さらに、神経が通るルート(首〜肩〜腕〜手指)で、どの部分に“引っかかり”があるのかも確認します。
可動域や動きの滑らかさ、左右差などを手技で探りながら、神経の流れに影響している部分を特定していきます。
首・肩まわりの可動域や筋膜の癒着を確認
手のしびれが出ているとき、多くの方は首・肩・胸郭まわりに何らかの緊張やこわばりを抱えています。
当院では、まず首の回旋テストや肩の挙上動作など、関節の動きと筋肉の反応を丁寧に確認。
さらに筋膜が癒着して動きにくくなっていないか、手を使ってチェックします。
筋膜の滑走性が悪いと、神経の滑りも悪くなり、しびれや違和感を生む要因になるとも言われています。
そのため、ただ筋肉をほぐすだけでなく、筋膜リリースや関節モビライゼーションなどを組み合わせた多角的なアプローチを行います。
当院の考え方|根本原因に合わせた個別ケアの例
しびれの原因はひとつではありません。
そのため当院では、「しびれが出ている場所」ではなく「しびれを引き起こしている背景」に着目しています。
たとえば──
- 姿勢の崩れによって首に負担がかかっている方には、骨格ラインを整える整体
- 肩まわりの使いすぎで神経が圧迫されている方には、関節と筋膜の調整+腕の使い方指導
- 呼吸が浅くなっている方には、肋骨・横隔膜の調整や呼吸法のアドバイス
など、その方に合わせた内容で進めていきます。
また、セルフケアについても、姿勢の意識や呼吸・簡単な体操など、自宅でも継続できる内容をご提案しています。
#整体でのチェックポイント
#神経の通り道の確認
#筋膜と可動域のバランス
#姿勢改善としびれの関係
#根本からのアプローチが大切
自分でできる予防とセルフケア

手のしびれが出たとき、「すぐに何かできることはないかな?」と考える方も多いと思います。
日常の中で意識できるケアを取り入れるだけでも、症状の緩和や予防につながる可能性があります。
ここでは、自宅でも無理なく取り組めるセルフケアをご紹介します。
簡単なストレッチや姿勢改善
首や肩まわりの緊張を和らげるストレッチは、しびれ対策の基本です。
とはいえ、無理に大きく動かす必要はありません。たとえば…
- 肩をすくめてからストンと落とす動作を数回繰り返す
- 耳と肩の距離を意識しながら、首をゆっくり左右に倒す
- 両肩を後ろに軽く回して、肩甲骨の動きを感じる
など、日常生活の合間に取り入れられるシンプルな動きが効果的です。
また、スマホやパソコン使用時の姿勢も重要なポイントです。
画面を目線の高さに近づける、腕を体の近くで支えるなど、体に負担をかけない工夫をしてみましょう。
生活習慣の見直しで再発を防ぐ
しびれは体の「サイン」とも言われており、姿勢や動き方以外の要因も関係している可能性があります。
- 水分不足
- 睡眠の質の低下
- 冷えやストレスによる血流の悪化
こうした生活習慣の乱れが神経や筋肉に影響を与えることもあると考えられています。
当院では、施術だけでなく、日々の生活リズム・呼吸・睡眠・食事などの面からもアドバイスを行っています。
体の内側と外側、両面から整えていく意識が大切です。
一時的な症状と向き合う心構え
手のしびれが出たとき、「何か重大な病気では?」と不安になる方もいらっしゃいます。
ですが、まずは慌てず、体の声に耳を傾けることが大切です。
しびれが長く続く・悪化するようであれば医療機関に相談することも重要ですが、
一方で、「疲労」「ストレス」「寝姿勢の偏り」などが原因の一時的なしびれもあります。
整体では、そういった**“気付きづらい要因”にもアプローチし、再発しにくい体づくりをサポート**していきます。
ご自身の体の状態を知ること、そしてそれに合ったケアを行うことが、しびれ対策の第一歩です。
#手のしびれセルフケア
#肩と首のストレッチ
#姿勢改善と予防法
#生活習慣の見直し
#整体と日常ケアの両立
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

瑞慶山 良二
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


