荒川院へのご予約
スタッフブログ

50肩の治し方|自然に治るは本当?早く楽になるための正しい対処法と注意点
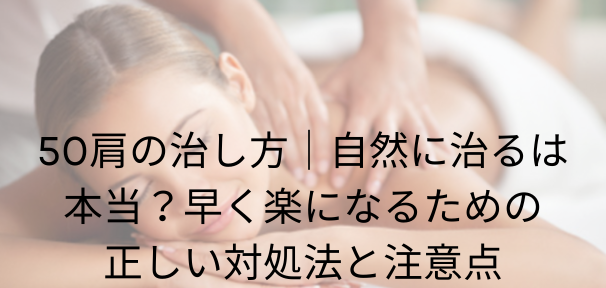
目次
50肩とは?治し方の前に知っておきたい基礎知識

医学的には「肩関節周囲炎」と呼ばれる状態
「50肩」って聞くと、年齢のせいかな?と感じる方も多いかもしれません。でも、実は正式には「肩関節周囲炎」と呼ばれていて、肩まわりの関節や筋肉、靭帯などの組織が炎症を起こすことで、痛みや動かしづらさが出る状態を指します。
当院(https://athletic.work)では、単に肩の可動域だけを見るのではなく、姿勢や肩甲骨・背骨・骨盤など、体全体のバランスをチェックしています。というのも、肩の動きは肩単体では完結せず、他の部位との連動が大きく関係しているからです。特に猫背や巻き肩などがあると、肩関節への負担が増えやすいと考えられます。
発症から完治までには段階がある
「朝起きたら突然痛くなった」「夜になるとズキズキして寝られない」といった話をよく耳にしますが、50肩には進行の段階があります。
まずは急性期(炎症期)。この時期はズキズキとした痛みが強く、少し動かしただけでもつらいと感じることがあります。次に拘縮期(凍結期)では、痛みは少し落ち着くこともありますが、動きがどんどん制限されていきます。そして回復期に入ると、少しずつ動かせる範囲が広がってくるようになります。
それぞれの段階で適切なケアや対応が変わるため、当院では触診によって痛みの質や可動域、筋肉の緊張状態を丁寧に確認し、段階に応じた施術方針を組み立てていきます。
自然治癒もあるが時間がかかることが多い
「ほっといてもそのうち良くなるよ」と言われた、という方もいるかもしれません。たしかに自然に改善に向かうケースもあるとは言われていますが、半年から1年以上かかることも珍しくありません。
特に長期間放置すると、関節が固まりすぎてしまったり、痛みをかばって他の部位にまで負担が出ることもあります。そのため当院では、早い段階での「動かせる範囲を維持するための施術」や、セルフケアのアドバイスを大切にしています。
自宅でもできるストレッチや姿勢改善の方法をお伝えし、無理のない範囲で肩の動きをサポートすることが、結果的に回復を早める可能性につながると考えています。
#五十肩の基礎知識
#肩関節周囲炎の理解
#自然改善には限界も
#段階別アプローチが重要
#姿勢から見直す整体ケア
50肩の治し方|自宅でできるセルフケアと生活の工夫

急性期は「冷やす・安静」が基本
「肩がズキズキ痛む…少し動かすだけでもつらい…」という時期は、無理に動かすことがかえって悪化につながることもあると考えられています。このような**急性期(炎症が強い時期)**は、肩を冷やして炎症を落ち着かせたり、できるだけ安静に過ごすことが勧められるケースが多いようです。
当院でも、問診と触診により炎症の程度を確認し、動かすべきタイミングかどうかを見極めた上で、施術内容を調整しています。炎症が強い場合は、肩そのものにアプローチせず、関連する筋肉の緊張を緩める施術を行うこともあります。
慢性期・回復期は「温め+ストレッチ」が効果的
痛みが少し落ち着いてきたら、温めて血流を促すケアや、軽めのストレッチが回復をサポートすることがあります。ただし、無理に動かしすぎると逆効果になる可能性もあるため、痛みの出ない範囲で行うのがポイントです。
当院では、肩だけでなく、肩甲骨の動きや背骨の柔軟性にも着目しながら、個別にストレッチの種類やタイミングをご提案しています。たとえば、壁に手をついて肩を開く動作や、タオルを使った肩甲骨周りの動きなど、簡単で続けやすいセルフケアを取り入れています。
日常生活で避けたいNG動作とは?
せっかくケアをしていても、日常の動作で無意識に肩へ負担をかけてしまっていることがあります。たとえば、高い棚に腕を伸ばす動作や、重たい荷物を同じ手で持ち続けるなどがそれにあたります。
また、デスクワークで猫背になっていると、肩の位置が前に出やすくなり、回復の妨げになることもあります。当院では、そうした生活習慣のクセも丁寧に伺いながら、具体的な改善アドバイスをお伝えしています。
施術の効果を持続させるには、普段の姿勢や動作を見直すことが欠かせないと考えています。
#五十肩のセルフケア
#急性期は冷やして安静
#慢性期は温めとストレッチ
#肩への負担を減らす生活
#当院オリジナルのケア提案
整体・整骨院でのアプローチ|痛みや可動域の回復を早めるには

50肩の状態に応じた施術の流れ
「整体ってどんなことをするんですか?」「痛みがあるのに動かして大丈夫なんですか?」という質問をよくいただきます。当院では、いきなり肩を揉んだり、無理に動かしたりするようなことはしていません。まずは触診を通して、どの段階にあるのかをしっかり見極めるところから始めます。
たとえば、炎症が強く出ている時期は、肩関節そのものにはあえて触れず、首や背中、肩甲骨まわりの筋肉の緊張をやわらげるアプローチを行うことがあります。逆に、動きが悪くなっている拘縮期・回復期には、肩の可動域を広げるための軽いモビリゼーション(関節の動きを助ける施術)を組み込むこともあります。
肩だけでなく姿勢や全身バランスもチェック
50肩といっても、原因が「肩そのもの」にあるとは限りません。実は、姿勢のクセや猫背、骨盤の傾き、体の使い方などが影響しているケースも少なくないんです。
当院では、肩の痛みがどこから来ているのかを「全体のバランス」から考えることを大切にしています。施術前には立ち姿勢や歩き方、腕の上げ方などを細かくチェックし、「なぜ今この症状が出ているのか」を丁寧に探っていきます。
施術後に意識したいセルフケアとの併用法
施術で可動域が少し広がったとしても、日常でのクセや使い方が変わらなければ、またすぐに元に戻ってしまう可能性があります。だからこそ、ご自宅でできるストレッチや姿勢の意識が重要なんです。
当院では、施術後にその方に合った簡単で無理のないセルフケア方法をご紹介しています。たとえば、壁を使って行う肩甲骨の動き改善エクササイズや、寝た状態でできる肩まわりの緩やかな運動など、「続けやすいこと」を重視してお伝えしています。
整体はあくまでサポート役。日々の生活で少しずつ体を整えていくための「土台づくり」を一緒に行っていけたらと思っています。
#整体での50肩アプローチ
#肩だけに注目しない検査法
#体全体のバランスからケア
#段階ごとの施術が大事
#セルフケアとの併用がカギ
50肩は放置しても改善する?そのリスクと注意点

自然に改善するケースとそうでないケースの違い
「放っておけばそのうち良くなるらしいよ」と耳にしたことがある方も多いかもしれません。たしかに、50肩は時間の経過とともに自然に軽快することがあると言われています。ただし、それがすべての方に当てはまるわけではありません。
炎症が軽度であったり、日常生活の中で肩を適度に動かす習慣がある方は、比較的スムーズに回復していく傾向もあるようです。一方で、動かさないことで関節が固まりやすくなったり、痛みをかばうことで他の筋肉に負担がかかるパターンも見られます。
関節拘縮や筋力低下といった二次的な問題も
長期間にわたって肩の動きを制限していると、「関節拘縮(かんせつこうしゅく)」という状態に陥る可能性があるとされています。これは、関節が固まり動かせなくなる状態で、改善にもより時間がかかることがあります。
また、動かさないことで肩周囲の筋肉が弱くなったり、反対側の肩や首・背中にまで緊張が波及するケースもあります。当院では、50肩をきっかけに姿勢や筋肉の使い方のクセまで見直すことが、再発防止にもつながると考えています。
「半年以上痛みが続く」「夜間痛が強い」は要注意サイン
「肩の痛みが半年以上続いている」「夜寝ているときにもズキズキする」というような症状がある場合、自己判断での放置は避けたほうがよいかもしれません。
このようなサインは、炎症が長引いていたり、他の疾患が関係している可能性もあるからです。当院では、痛みの部位や可動域、生活習慣などを細かく確認したうえで、適切な施術やセルフケアをご提案しています。
「様子を見ていたけど、やっぱり気になる…」という方も、遠慮なくご相談いただけたらと思います。
#50肩の自然改善に要注意
#放置はリスクになることも
#関節拘縮と筋力低下の防止
#夜間痛は受診のサイン
#肩のケアは早めが安心
再発予防と快適な肩の使い方|姿勢・筋肉の使い方を見直そう
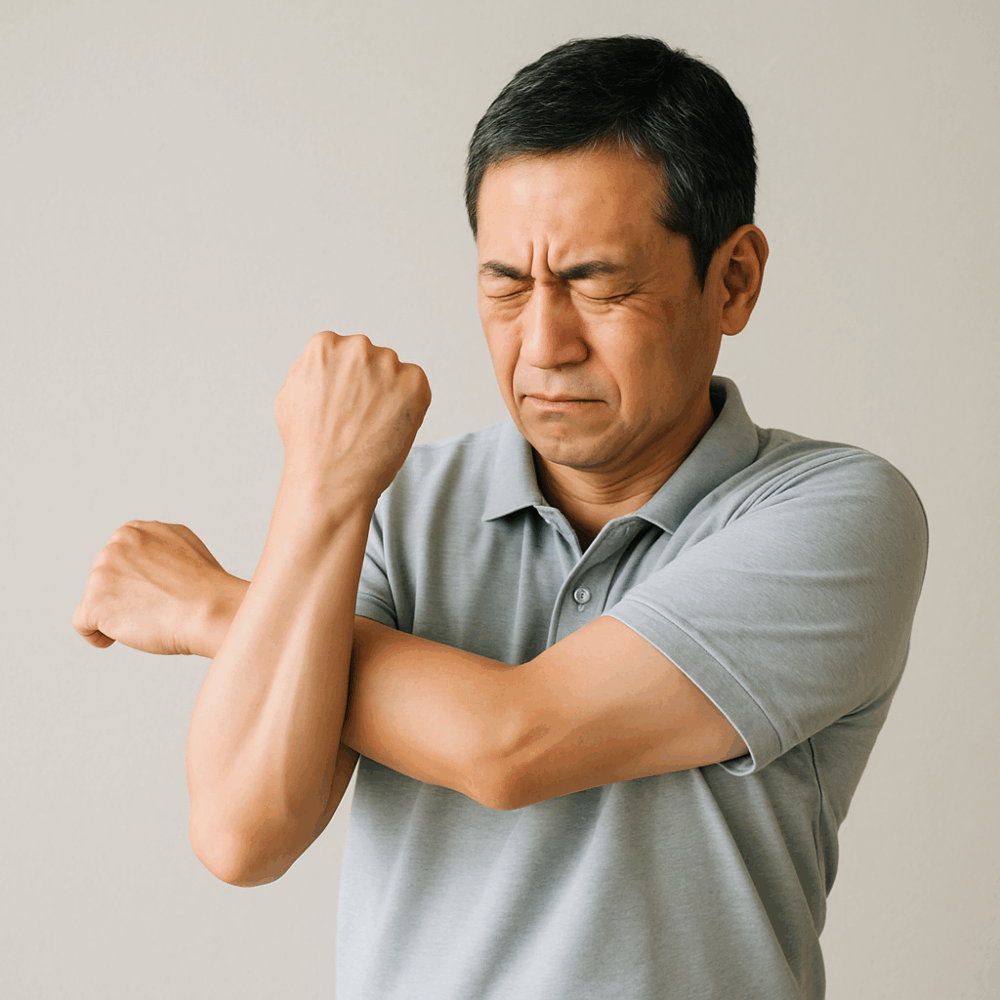
肩関節の動きに関わる筋肉・関節とは
「肩の動きが悪い」と聞くと、肩そのものだけに原因があるように感じるかもしれません。でも実際は、肩甲骨・鎖骨・胸郭・背骨・骨盤など、複数の関節や筋肉が関わっています。特に肩甲骨と肋骨の間の動き(肩甲胸郭関節)や、背中〜腰にかけての柔軟性が関係していると言われています。
当院では、肩の痛みがある方でも全身の動きや連動性を確認する検査を行います。腕を上げたときに背中や腰が硬くて一緒に動いていないか、肩甲骨の可動に左右差がないか、など細かくチェックして、根本的な原因を探っていきます。
肩こりや猫背が引き金になることも
「姿勢が悪いだけで肩が痛くなる?」と感じるかもしれませんが、これはよくあるケースです。猫背になると肩が前に巻き込みやすくなり、肩関節の動きが制限されるとされています。これが長期間続くと、肩まわりの筋肉や関節に負担が蓄積し、結果的に50肩のような状態に進行することもあるようです。
実際に、肩の可動域よりも姿勢の改善で症状が軽くなる方も少なくありません。当院では、施術と並行して「正しい姿勢の感覚」をつかむためのサポートも行っています。
日常生活で意識したい肩のケア習慣
肩を守るには、日常的に無理のない範囲で肩を動かす習慣や、正しい姿勢をキープする意識が大切です。たとえば、スマホやパソコンの位置を見直す、荷物を左右バランスよく持つなど、ちょっとしたことでも肩への負担は変わってきます。
また、肩の可動域を保つための簡単なストレッチや、朝・夜にできる体操を取り入れるのもおすすめです。当院では、来院時の施術に加えて、自宅で再現できるセルフケアメニューもお渡ししています。これにより、整体に通わなくなった後も、自分で体を整える力が身につきやすくなると考えています。
#肩の再発予防は姿勢から
#全身の連動がカギ
#肩甲骨と背中の柔軟性が重要
#セルフケアで改善をサポート
#日常の姿勢を見直すことが第一歩
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

瑞慶山 良二
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


