荒川院へのご予約
スタッフブログ

右胸の下が痛い:原因から対処法まで分かる完全ガイド
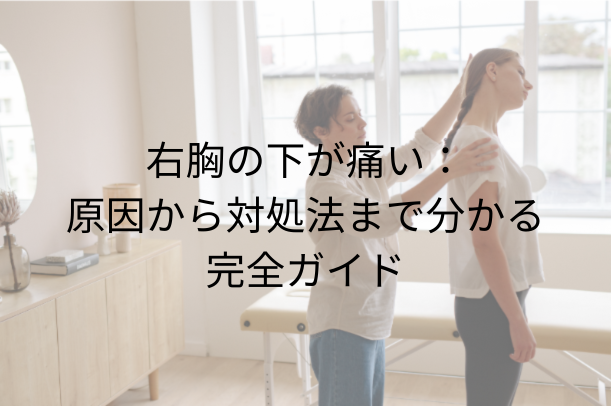
1.症状の特徴とチェックポイント

右胸の下に違和感や痛みを感じたとき、その原因は一つではないと言われています。例えば「ズキズキする」「圧迫感がある」「深呼吸で強くなる」など、痛み方や状況の違いによって考えられる要因が変わってきます。
日常の生活動作や食後、就寝前など、痛みが強く出やすいタイミングを振り返ることも、体の状態を把握する手がかりになるとされています。
痛みの出る場所と範囲
「右胸の下」といっても、実際には肋骨の下部・みぞおちに近い部分・わき腹寄りなど、人によって感じる箇所が微妙に異なります。押すと局所的に痛む場合は筋肉や関節に負担がかかっているケースが考えられる一方で、奥深くに鈍い痛みを感じる場合には内臓由来の可能性が示唆されることもあると言われています。
痛みの性質を観察する
鋭い痛みなのか、じんわり続くのか、あるいは呼吸に合わせて強くなるのか。こうした性質の違いが、筋肉や神経、消化器系、呼吸器系などの区別をつけるポイントになりやすいと考えられています。また、咳やくしゃみ、体をひねったときに痛みが増すなら肋間神経や筋肉が関係している場合もあるようです。
当院での考え方と検査ポイント
当院では「筋・神経・関節・内臓・自律神経」といった多角的な視点から体を確認する方針をとっています(整体oasis ホームページ 参照)。国家資格を持つ施術者が、姿勢や動作のクセを含めて検査し、どの部分に負担が集中しているかを確認します。例えば、胸郭の動きが硬い方は呼吸筋に緊張が見られることがあり、その場合は可動域を広げる施術を行いながら、セルフケアとして胸を開くストレッチや呼吸法を提案しています。
セルフチェックとセルフケア
自分でできる確認方法としては、①軽く押してみる、②呼吸に合わせて痛みが強まるか試す、③体をねじったときの変化を見る、などがあります。もし姿勢の影響が大きいと感じた場合は、座り方を正す、肩甲骨周りを動かすストレッチを取り入れるといった工夫が役立つとされています。ただし、強い痛みや長引く違和感があるときは、早めに専門的な確認を受けることが安心につながると考えられます。
2.考えられる主な原因(部位別・系統別)
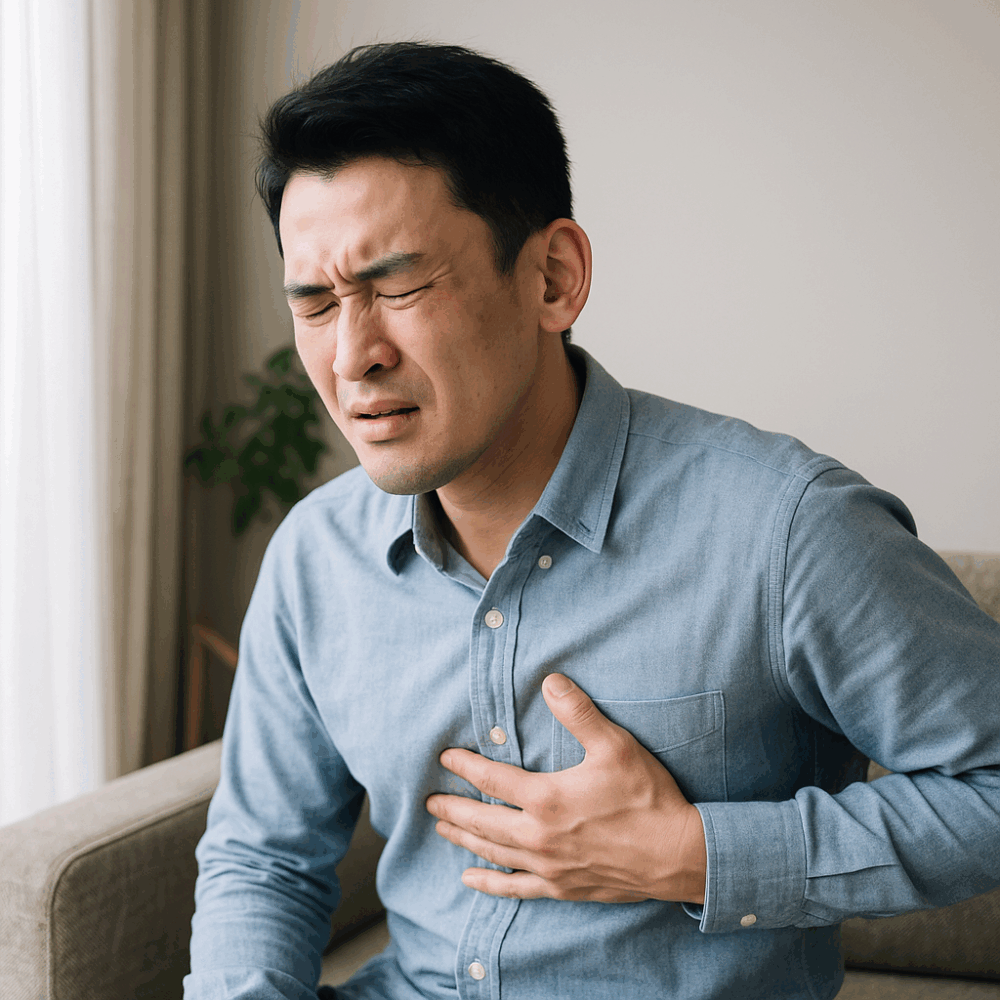
右胸の下に痛みを感じる場合、その背景にはさまざまな要因が関わっていると言われています。筋肉や関節などの体の外側から、臓器や神経といった内側まで、幅広く考えておく必要があります。ここでは代表的な原因を系統別に整理してみます。
筋肉や関節・神経によるもの
スポーツや長時間の同じ姿勢で、肋間筋や腹筋に負担がかかると炎症や緊張が起きやすくなります。また、肋間神経痛や肋軟骨炎といった症状では、呼吸や体をひねる動きで痛みが強まることがあります。押したときに鋭い痛みが走る場合は、こうした体の外側の組織が関係していることが多いとされています。
呼吸器や胸膜の影響
咳や深呼吸で痛みが増すときには、肺や胸膜に関わるトラブルが考えられます。胸膜炎や肺炎、気胸といった疾患では、鋭い痛みとともに呼吸困難や発熱を伴うこともあるため注意が必要とされています。急な強い痛みと息苦しさを同時に感じるときは、早めの専門的な確認がすすめられることもあります。
消化器や肝胆系の関わり
胆石や胆のう炎などは、右胸の下から右上腹部にかけての痛みとして感じられる場合があります。食後に痛みが出やすい、吐き気を伴うといった特徴がみられることもあります。また胃や食道の不調が右側に関連して違和感を生じさせることもあると言われています。
心臓や血管に由来するケース
狭心症や心筋炎など、心臓に関わる不調が胸の右側に出ることもあります。冷や汗や動悸を伴う場合は特に注意が必要とされており、左胸だけでなく右側に症状が出る場合がある点も見落とさないことが大切です。
その他の要因
帯状疱疹のように神経に沿って痛みや発疹が現れる病気や、強いストレスが原因で一時的に胸のあたりに不快感が出るケースもあります。まれではありますが、こうした要因も考えられるため、症状が長引いたり繰り返す場合には慎重に観察する必要があるとされています。
3.症状別の見分け方(鑑別ポイント)
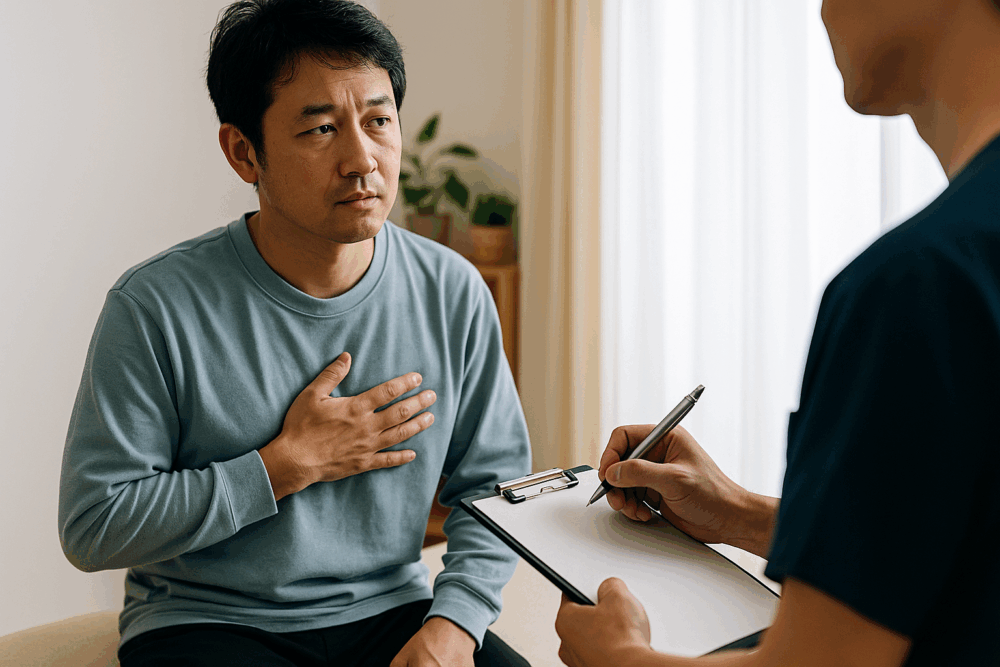
右胸の下の痛みは、いくつかの特徴からある程度の傾向を推測できると言われています。もちろん正確な判断は専門的な検査が必要ですが、日常的に観察できるポイントを知っておくことは役立つことがあります。
押すと痛むかどうか
軽く押したときに痛みが強くなる場合は、筋肉や肋骨、神経の影響が関わっている可能性があります。特に肋間神経痛や筋膜の緊張では、姿勢や動作によっても変化することが多いとされています。
呼吸や体の動きとの関連
深呼吸や咳、体をひねったときに痛みが増す場合は、胸郭の動きや呼吸器の負担が関わっていると考えられます。胸膜や肺に関連した疾患では、この特徴がはっきりと出やすいことがあります。
食後や時間帯による違い
食後に痛みが出やすいときは、消化器や胆のうの影響が考えられるとされています。夜間や就寝中に違和感が強まる場合は、胃や食道の逆流が関わることもあるようです。
強い痛みや全身症状を伴う場合
冷や汗、動悸、吐き気などを伴う場合には、心臓や循環器系の関与が疑われることがあります。このようなサインがあるときは、早めに専門的な確認を受けることがすすめられると言われています。
当院での確認の工夫
当院(整体oasis)では、姿勢や呼吸の深さ、筋肉の張り具合などを多角的に確認し、どの要素が痛みにつながっているかを整理する方針をとっています。胸郭の柔軟性や肋骨まわりの動きをチェックし、必要に応じてセルフケアとして胸を広げるストレッチや呼吸法を提案しています。
4.病院来院・検査・施術の目安

右胸の下の痛みは一時的な体の負担から起こる場合もありますが、中には内臓や循環器など重大な疾患が背景にあることもあると言われています。そのため、どのような状況で医療機関を検討すべきかを知っておくことは大切です。
来院を検討すべきサイン
・痛みが強く、数日たっても改善しない
・冷や汗・吐き気・呼吸困難を伴う
・体を休めても鈍痛や圧迫感が続く
・夜間や安静時にも症状が増す
こうした場合は、自己判断せず早めに医療機関で確認することがすすめられています。
検査の流れと内容
来院時には問診や触診で痛みの部位・性質を確認したあと、必要に応じてレントゲンやエコー、血液検査、心電図、CTなどが行われることがあります。どの検査を選ぶかは症状や疑われる疾患によって異なります。
当院での施術との違い
当院(整体oasis)では、医療機関の検査と併用しながら、筋肉・関節・神経・内臓といった多角的な観点で体を検査しています。施術では胸郭や肋骨の動きを取り戻すアプローチを行い、呼吸のしやすさや姿勢バランスを整えるようにしています。医療機関で「異常なし」とされた場合でも、筋肉や関節の不調が残っているケースは多いため、体の構造的な調整が役立つと考えられています。
再発を防ぐための工夫
施術後は、セルフケアとして胸を開くストレッチ、呼吸法、日常生活での姿勢改善を継続することが重要です。これにより、再び同じ部位に負担がかかりにくい体づくりを目指すことができます。
5.まとめと安心のためのポイント
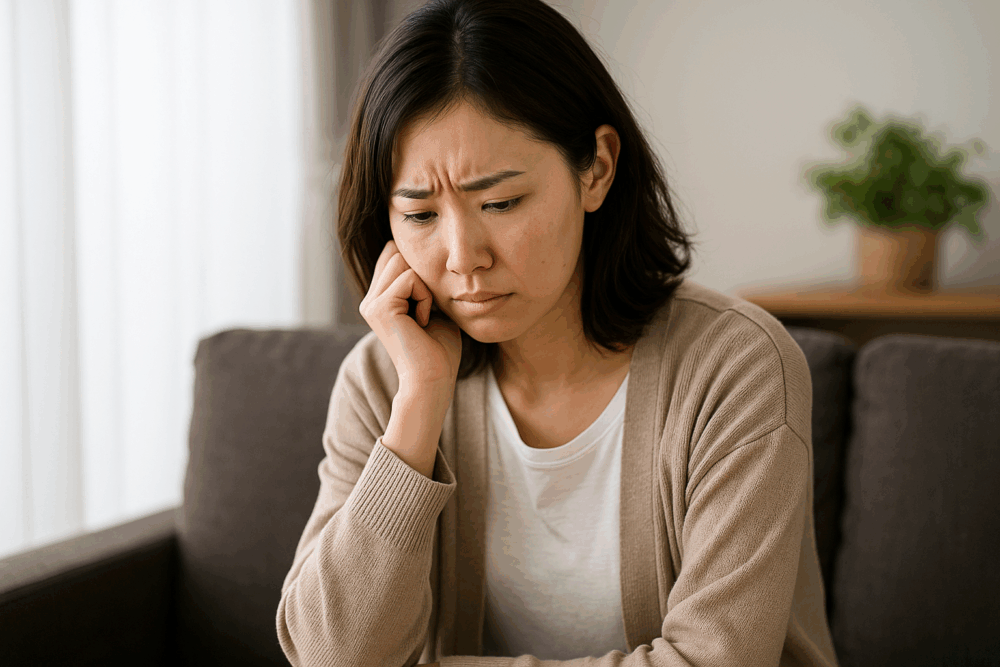
右胸の下に痛みを感じるとき、その原因は筋肉や神経といった体の外側から、肺・胆のう・心臓などの内臓まで幅広いと言われています。まずは痛みの出方や伴う症状を観察し、セルフケアで楽になるのか、あるいは強く続くのかを見極めることが大切です。
自分でできる観察と工夫
押すと痛い、呼吸で変化する、食後に強まるなどの特徴を整理するだけでも、体の状態を把握しやすくなります。軽度な場合には姿勢を整えたり、胸郭を広げるストレッチや呼吸法を取り入れることが役立つとされています。
専門的な確認の大切さ
ただし、冷や汗や吐き気、動悸、息苦しさを伴うときや痛みが長引くときは、自己判断せずに専門的な確認を受けることが安心につながります。当院(整体oasis)では多角的な検査を行い、施術とセルフケアの両面からサポートする方針をとっています。
安心のために
「放っておいても大丈夫かもしれない」と迷うときほど、早めに相談しておくと不安が軽くなることがあります。ご自身の体の声に耳を傾けながら、必要に応じて専門家の手を借りることが、安心した生活につながると考えられています。
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

瑞慶山 良二
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


