荒川院へのご予約
スタッフブログ

ハムストリングスを徹底解説|機能・硬さの対策・痛み予防まで完全ガイド
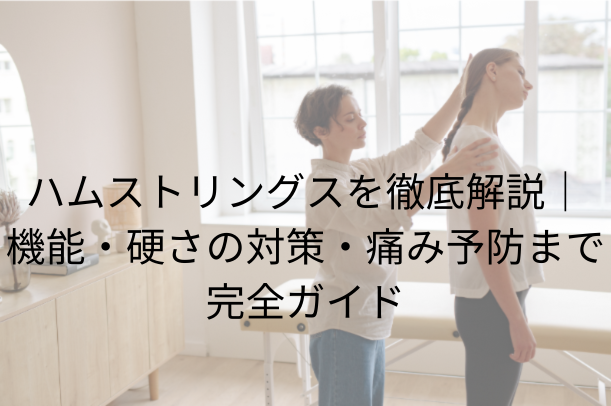
目次
1.ハムストリングスとは何か/構造と役割

ハムストリングスの定義と基本構造
「ハムストリングス」という言葉は、太ももの裏側にある3つの筋肉――大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋――をまとめた名称です。これらは骨盤の坐骨から始まり、膝の下(脛骨・腓骨)にかけて付着しています。いずれも股関節を伸ばす・膝を曲げる動きに関わり、歩行や階段の上り下りなど日常のあらゆる動作を支えています。特に大腿二頭筋は外側に位置し、太もものラインを形づくる筋肉でもあります。
起始・停止・神経と作用
ハムストリングスは「坐骨から下腿骨へ」つながっており、股関節と膝関節という2つの関節をまたぐ「二関節筋」として働きます。そのため、動きが複雑で、使い方や姿勢の癖によって硬くなりやすいとも言われています。支配している神経は坐骨神経で、特に長時間の座位姿勢や腰部の緊張が続くと神経の流れが滞り、ハムストリングスの柔軟性にも影響を及ぼすことがあります。当院(athletic.work)では、こうした神経の流れや骨盤の傾きを含めた検査を行い、筋肉の単なる「硬さ」だけでなく、体全体のバランスから原因を探っていきます。
日常動作・スポーツでの働き
歩く・走る・立ち上がるなど、ハムストリングスは体を動かす基礎的な場面で常に働いています。特に走行中には、地面を蹴る瞬間やブレーキ動作で強く収縮し、膝を守る役割も担っています。スポーツでは、スプリント中やサッカーのキック動作などで急激に伸ばされることが多く、肉離れを起こす部位としても知られています。そのため、筋力と柔軟性の両立が大切だと言われています。
ハムストリングスの語源と豆知識
「ハムストリングス(hamstrings)」の語源は、英語の「ham(もも肉)」と「string(腱)」に由来します。古くは肉屋が豚のももを吊るす際に使っていた腱を指していたとされ、そこからこの筋群の名前が付けられたと言われています。少しユニークですが、体の機能を知るうえで興味深い背景です。
当院の検査・施術アプローチ
当院では、ハムストリングスの硬さや痛みが出ている場合でも、直接ほぐす前に「なぜそこに負担がかかっているのか」を検査で確認します。股関節や骨盤のねじれ、神経の滑走不全、筋膜の癒着などを細かく見極めた上で、筋膜リリースや神経モビライゼーションなどを組み合わせ、体全体の動きをスムーズに導く施術を行っています。セルフケアとしては、タオルを使ったストレッチや呼吸を意識したゆるめ方など、日常で再現しやすい方法を指導しています。これらは、筋肉を「柔らかくするための方法」というより、体を使いやすくする準備として取り入れることをおすすめしています。
2.なぜハムストリングスは硬くなる?/硬さ・張り・痛みの原因

座りすぎ・運動不足による筋肉の拘縮
「ハムストリングスが硬い」と感じる人の多くは、日常的に座る時間が長い傾向があります。座位姿勢では股関節が曲がった状態が続くため、太ももの裏側の筋肉は常に短縮したまま。長時間の圧迫で血流も悪くなり、筋肉がこわばる原因になると言われています。また、デスクワークや車の運転などで下半身をほとんど動かさない生活は、筋肉の柔軟性を失わせる一因です。
姿勢の歪みと骨盤の傾き
ハムストリングスの硬さは、骨盤の傾きとも深く関係しています。たとえば、骨盤が後傾すると筋肉が常に引き伸ばされるような状態となり、緊張が続くことで痛みや張りを感じやすくなります。逆に、骨盤が前傾しすぎるタイプではハムストリングスが過剰に縮まり、動作のたびに引っ張られることで腰痛や膝の負担につながることもあると考えられています。当院では、骨盤や股関節の可動域を細かく検査し、筋肉だけでなく関節や神経の連動まで確認しています。
筋力バランスの崩れとオーバーユース
前側の大腿四頭筋とのバランスが崩れると、ハムストリングスに過剰な負荷がかかることがあります。特にスポーツをしている人では、蹴る・走る・止まるなどの動作で片側の筋肉ばかり使う傾向があり、硬さや痛みが出やすいと言われています。使いすぎによる微細な損傷や筋膜の癒着も原因の一つです。
神経の滑走不全や血流の低下
ハムストリングスの奥を通る坐骨神経は、筋肉の緊張が強いと圧迫を受けやすくなります。神経の通り道が狭くなることで「しびれ」「引きつり感」が出るケースもあります。当院では、神経モビライゼーションという方法で神経の滑走性を回復させる施術を行い、筋肉を無理に伸ばさなくても柔らかさを取り戻せるよう導いていきます。
生活習慣の影響
冷え、睡眠不足、水分不足なども筋肉の硬さを助長すると言われています。血流が悪い状態では老廃物が滞り、筋肉内の循環が落ちることで「常に重だるい」「動かすと突っ張る」といった感覚につながります。セルフケアでは、湯船で体を温める、呼吸を整える、ストレッチ前に軽い運動を行うなどが効果的です。
3.ハムストリングスをほぐす・柔らかくするストレッチ・セルフケア法

まずは「無理に伸ばさない」意識から
「ストレッチ=強く伸ばす」と思われがちですが、実はハムストリングスの柔軟性を高めるには“ゆるめる”意識が大切だと言われています。特に硬さを感じている人は、筋膜や神経が軽い圧で反応している可能性もあります。いきなり引っ張ると防御反応が働いて、かえって筋肉が緊張してしまうことも。当院では、まず深呼吸を取り入れながら筋肉が自然にゆるむ方向を探っていく検査と施術を行っています。
座ってできるストレッチ
イスに浅く腰をかけ、片足を前に伸ばしてつま先を軽く上に向けます。背中を丸めず、股関節から体を倒すようにして前屈していくのがポイントです。太ももの裏側に軽い伸び感を感じたところで10〜20秒キープ。呼吸を止めずに、ゆっくりと戻します。
このとき「痛いくらいに伸ばす」必要はありません。気持ちよく感じる程度で十分効果があると言われています。
寝ながら行うタオルストレッチ
仰向けで寝て、片足の裏にタオルを引っかけます。そのまま足をゆっくり持ち上げ、無理のない範囲で膝を伸ばします。タオルを軽く引きながら呼吸を繰り返すことで、太ももの裏がじんわりと伸びていきます。脚の重みを利用するため、体に余計な力が入りにくく、リラックス効果も高い方法です。
セルフケアの前後でチェックを
ストレッチの前後で「足の上げやすさ」「前屈のしやすさ」「膝を伸ばした感覚」などを確認すると、自分の体の変化がわかりやすくなります。当院では、検査で動きの制限がどこに出ているかを特定し、筋肉ではなく神経や筋膜に原因がある場合は、それに合わせたリリースを行います。ご自宅でのセルフケアも、そうした検査の結果をもとに指導しています。
毎日続けるコツ
ストレッチは“長くやるより頻度を増やす”ことが大切だと言われています。1日1回まとめてよりも、朝・昼・夜の3回に分けて1〜2分ずつ行う方が筋肉はやわらかさを保ちやすい傾向があります。体が温まったタイミング(入浴後や軽い運動のあと)に行うとさらに効果的です。
4.ハムストリングスを鍛える・強化するトレーニング法

柔らかさだけでなく「使える筋肉」に
ハムストリングスは、伸ばすだけでなく“使える状態”にしていくことも大切だと言われています。柔軟性を高めたあとに筋力をつけると、再び硬くなりにくく、関節の動きが安定します。当院でも、施術のあとに軽いトレーニングを組み合わせることで、筋肉と神経のつながりを高めるサポートを行っています。
初心者におすすめの「ヒップリフト」
仰向けになり、膝を曲げて足裏を床につけます。そこからお尻をゆっくり持ち上げ、肩から膝まで一直線になるように意識します。太ももの裏側(ハムストリングス)とお尻の筋肉を感じながら、3〜5秒キープ。呼吸を止めずに10回ほど繰り返します。腰を反らせすぎると負担がかかるため、骨盤の動きを感じながら行うのがコツです。
中級者向け「ノルディックハムカール」
膝立ちの姿勢で、足首を固定して上体をゆっくり前に倒していくトレーニングです。ハムストリングスに強く刺激が入るため、無理のない範囲で少しずつ行うのがポイント。倒れそうなときは手で支えて調整します。筋肉だけでなく、腱や神経系にも良い影響があるといわれています。
体幹との連動を意識する「ヒップヒンジ」
立位で膝を軽く曲げ、股関節を支点にして上体を前に倒していく動作です。背中を丸めず、腰を反らさないことを意識します。この動作ではハムストリングスと体幹の筋肉が同時に働くため、動きの安定や姿勢改善にもつながると考えられています。当院では、ヒンジ動作を通して骨盤の可動域を評価し、正しい体の使い方を身につける指導を行っています。
トレーニング後のケアを忘れずに
鍛えたあとは、軽いストレッチや深呼吸で筋肉をリセットすることが重要です。トレーニングによる微細な緊張をそのままにしておくと、せっかくの柔軟性が損なわれてしまうことも。当院では施術後に「筋膜の滑走性」を保つためのセルフケア法もお伝えしており、自分で再現しやすい形でサポートしています。
5.ハムストリングスの痛み・怪我ケースと予防・対処法

痛みのサインを見逃さない
「太ももの裏が突っ張る」「歩くとピキッとする」「長く座っていると痛む」などの症状は、ハムストリングスに小さな炎症や筋膜の癒着が起きているサインかもしれません。強い痛みがなくても、筋肉がうまく伸び縮みできていない状態では、パフォーマンス低下や再発のリスクが高まるといわれています。
よくある怪我のタイプ
代表的なのは「肉離れ(筋挫傷)」で、急なダッシュや方向転換、ストレッチ中の伸ばしすぎで発生するケースが多いです。軽度の場合は張り感程度ですが、中等度以上になると歩行時にも痛みが出ることがあります。また、慢性的にハムストリングスが硬い方は、骨盤の後傾や腰部の緊張をともなう「神経系の滑走不全」が関係していることもあると言われています。
自宅でできる初期ケア
軽い違和感の段階では、まず安静を意識し、温めすぎずに軽いストレッチから始めます。患部を無理に押したり揉んだりせず、ゆっくり呼吸を合わせながら動かすのがポイントです。違和感が強いときや、痛みが数日以上続く場合は、専門機関で体のバランスを検査してもらうことをおすすめします。
当院の施術アプローチ
当院では、ハムストリングスの痛みを単に筋肉の問題として捉えるのではなく、骨盤・股関節・神経の連動性を重視して検査します。筋膜リリースや神経モビライゼーション、骨格矯正などを組み合わせることで、痛みの根本的な要因にアプローチしていきます。施術後は、再発防止のために自宅でできるリハビリ的なストレッチや体の使い方も指導しています。
予防のための習慣づくり
日頃から股関節をしっかり動かす習慣があると、ハムストリングスの過剰な負担を減らせると言われています。ストレッチや軽い筋トレを習慣化し、長時間同じ姿勢を続けないことが大切です。また、睡眠や食事などの生活リズムも筋肉の回復に影響します。体のコンディションを整えることが、ケガを防ぐ第一歩になります。
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

瑞慶山 良二
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


