荒川院へのご予約
スタッフブログ

アキレス腱炎:原因・症状・治療法と再発予防の完全ガイド
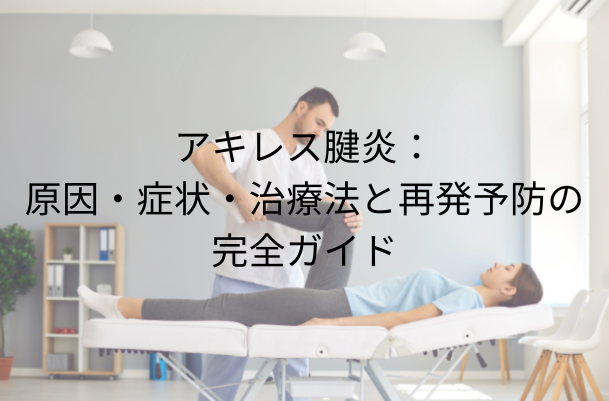
アキレス腱炎とは? — 基本知識と分類

「最近、かかとの上あたりがズキッと痛む…」そんな経験はありませんか?
その原因のひとつとして考えられるのが「アキレス腱炎」と呼ばれる炎症です。アキレス腱は、ふくらはぎの筋肉(腓腹筋・ヒラメ筋)とかかとの骨(踵骨)をつなぐ太い腱で、歩く・走る・ジャンプするといった動作で大きな力を発揮する重要な組織です。私たちが無意識に行っている立ち上がりや階段の上り下りも、この腱の働きによってスムーズに行えています。
アキレス腱炎とアキレス腱周囲炎の違い
「アキレス腱炎」とひとことで言っても、実際には大きく2つに分けられることが多いです。
ひとつはアキレス腱そのものに炎症が起きるタイプ(腱炎)で、もうひとつはアキレス腱の周りの組織に炎症が広がるタイプ(腱周囲炎)です。どちらも似たような場所に痛みを感じますが、炎症の起こる位置や原因が少し異なります。
特にランニングやジャンプ動作を繰り返す方、長時間の立ち仕事をする方では、腱に過度な負担がかかりやすく、炎症が慢性化することもあります。
発生頻度と好発年齢・リスク要因
アキレス腱炎はスポーツをする人に多いですが、実は運動習慣のない方にも見られます。
30〜50代での発症が多く、加齢による筋腱の柔軟性低下や血流の悪化、筋力バランスの乱れが関係していると考えられています。また、合わない靴・硬いソール・ヒールのない靴などを日常的に使用していると、アキレス腱にかかるストレスが増え、炎症を引き起こす要因になることがあります。
当院では、痛みの部位や腱の動きを丁寧に触診し、ふくらはぎや足首の柔軟性・骨格のねじれ・重心の偏りを細かく検査します。筋膜の滑走不良や下腿のねじれなどを見極め、腱そのものだけでなく、負担をかけている全体の動作パターンを改善していくことが大切だと考えています。
施術では、過度な刺激を避けつつ筋膜リリースや関節モビライゼーションで緊張を和らげ、再発を防ぐためのセルフケアとしてふくらはぎのストレッチや足首の可動域トレーニングもお伝えしています。
アキレス腱炎は、単に炎症を抑えるだけでなく、原因となる動きや姿勢のクセを見直すことが改善の第一歩となります。
アキレス腱炎が起きる原因と誘因

「走ったあとにかかとの上がズーンと痛む」「朝起きて歩き始めがつらい」──そんな声を耳にすることがあります。アキレス腱炎の多くは、体の使い方のクセや繰り返しの負担が関係していることがあります。特別なケガをしたわけではなくても、少しずつ腱にストレスが蓄積し、炎症を起こしてしまうケースが多いです。
オーバーユース(使い過ぎ)が引き金になるケース
ランニングやジャンプ動作を繰り返すスポーツでは、アキレス腱に何度も強い張力がかかります。十分な休息やストレッチを挟まずに続けると、腱の繊維が微細に傷つき、それが炎症反応として現れると考えられています。
当院では、痛みの出る位置や筋肉の緊張パターンを丁寧に確認し、「ふくらはぎの使いすぎ」なのか「足首の動きの悪さ」なのかを細かく見分けています。単に安静にするだけではなく、再発を防ぐためにどの動作が腱へ負担をかけているのかを一緒に確認していくことを大切にしています。
柔軟性や筋力のアンバランスも関係
ふくらはぎや足首の柔軟性が低下すると、アキレス腱が引っ張られやすくなります。逆に、足裏や股関節まわりの筋肉がうまく使えていないと、負荷が一点に集中して炎症を招くこともあります。
施術では、筋膜リリースや関節モビライゼーションを用いて動きの制限を取り除き、滑らかに動くラインを整えることを目的としています。また、セルフケアとしては「アキレス腱まわりのストレッチ」や「つま先立ち運動」などを無理のない範囲で続けることが重要になります。
靴の影響や足の形のクセも無視できない
「靴を変えたら痛くなった」「ヒールのない靴で歩くと違和感が出る」──こうした声も少なくありません。合わない靴や硬いソール、インソールの歪みなどによって足の接地角度やアライメント(骨の並び)が崩れると、腱への引っ張りが偏ることがあります。特に扁平足や外反母趾の方は、足首のねじれが加わるため、アキレス腱に負担がかかりやすくなります。
加齢や血流の低下による腱の変化
年齢とともに腱の水分量が減り、弾力が失われていくと言われています。その結果、小さな負担でも炎症が起こりやすくなります。冷えや血流の悪化も回復を遅らせる要因となるため、ふくらはぎを温める・足首を回すなど、日常のケアも大切です。
当院では、施術後に血流促進を目的としたセルフストレッチを指導し、体が自分で回復しやすい状態を整えていきます。
アキレス腱炎は「使い過ぎ」だけではなく、姿勢や歩き方、靴選び、年齢など複数の要因が重なって起こることが多いです。まずは自分の動きのクセを知り、体に合ったケアを積み重ねることが、長く動ける体をつくる第一歩と言えるでしょう。
症状・診断 — どこが痛む?いつ病院へ?

「歩き始めにズキッと痛む」「朝起きて一歩目がつらい」──そんな違和感から始まるのが、アキレス腱炎によく見られる症状です。最初は軽い張りや重だるさ程度でも、放っておくと炎症が強まり、階段の上り下りや長時間の立ち仕事がつらくなることもあります。
典型的な症状と痛みの特徴
アキレス腱炎では、かかとの上あたり(ふくらはぎとの境目付近)に圧痛や腫れ、こわばりを感じることが多いです。特に「動き出しの痛み」が特徴的で、しばらく歩くと軽くなるものの、安静後や翌朝に再び痛みが戻るケースもあります。
痛みの感じ方は人によって異なりますが、「歩くたびに突っ張る」「ふくらはぎを伸ばすと響く」といった訴えが多く聞かれます。運動習慣のある方はもちろん、デスクワークや立ちっぱなしの仕事をしている方にも起こりやすい傾向があります。
痛みの出るタイミングと進行の目安
アキレス腱炎は、初期では歩き始めや運動開始直後の痛みとして現れることが多く、進行すると動作中や安静時にも違和感が残ることもあります。特にランニングやジャンプ動作を繰り返す方では、トレーニング翌日の朝に強いこわばりを感じることが目安になります。
当院では、動作中だけでなく立ち姿勢や足首の角度にも注目し、どの動作で腱に負担がかかっているかを丁寧に検査します。ふくらはぎの筋緊張や足の軸のブレを確認し、体の動き全体を見ながら原因を特定していきます。
似た症状に注意すべき疾患
アキレス腱炎と似た症状を示すものに、アキレス腱断裂・踵骨棘(しょうこつきょく)・滑液包炎などがあります。特に断裂は、突然「ブチッ」という感覚とともに強い痛みが走るのが特徴です。また、踵骨棘ではかかとを押したときの鋭い痛み、滑液包炎では腫れや熱感が強く出る傾向があります。
触診や検査のポイント
アキレス腱炎の評価では、まず触診で炎症部位を確認します。押して痛みがある場所、熱感、腫れ具合をチェックし、必要に応じて超音波検査やMRIで腱の損傷範囲を確認する場合もあります。
当院では、医療的な画像検査が必要な場合には専門機関での検査を勧め、整体としては筋膜・関節・神経の動きの評価を重視しています。単に痛みのある部位だけを見ず、歩行時の癖や体のバランスの崩れまで検査することで、根本的な負担の原因を明確にしていくことを大切にしています。
「歩くたびに少し痛むだけだから」と我慢してしまう方も多いですが、早い段階でのケアが回復への近道につながります。痛みが続く場合や、朝のこわばりが強くなってきたときは、無理せず専門家に相談することをおすすめします。
治療法・セルフケア:段階別ガイド

アキレス腱炎の改善には、「痛みを落ち着かせる段階」と「再発を防ぐ段階」の両方を意識することが大切になります。無理に動かして悪化させるよりも、体の回復リズムに合わせて段階的にケアを行うことがポイントです。
保存療法の基本
まずは、安静と冷却(アイシング)が基本です。痛みや腫れが強い初期は、運動や長時間の立ち仕事を控え、患部を冷やして炎症を落ち着かせます。必要に応じて、整形外科でNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)や物理療法(超音波・温熱)を併用することもあります。
ただし、「痛みが落ち着いた=完治」ではなく、まだ腱に負担が残っている状態の場合も多いです。当院では、安静だけに頼らず、腱にかかるストレスの原因を見つける検査を重視しています。ふくらはぎや足首の可動域、骨格のねじれ、歩き方の癖などを確認し、再発しにくい体づくりをサポートしています。
リハビリとセルフケア
痛みが落ち着いてきたら、ストレッチや筋力強化を少しずつ再開します。特に、ふくらはぎ(下腿三頭筋)のストレッチはアキレス腱への負担軽減につながります。
段階的には、①壁押しストレッチ → ②つま先立ち → ③軽いジョギング というように、漸進的に負荷を高めることが大切です。
当院では、筋膜リリースや関節モビライゼーションを組み合わせて、腱の滑走を促しながら動作の質を整えます。また、自宅では「お風呂上がりのストレッチ」や「足首まわし」を習慣にするようアドバイスしています。
装具・テーピング・インソールの活用
歩くときに痛みが残る場合は、ヒールリフト(踵を少し上げる補助具)やテーピングを使って負担を軽減する方法もあります。
扁平足や外反母趾など、足のアライメントが崩れている方には、オーダーインソールの併用が有効となります。当院でも、歩行検査の結果に基づいて、シューズやインソールの選び方を一緒に見直すサポートを行っています。
難治例や特殊な検査
慢性的に続くケースでは、腱の変性や血流低下が関係していることもあります。その場合、整形外科でのPRP(多血小板血漿)療法や体外衝撃波療法などが検討されることもあります。手術が必要になるのはごく一部の重度例ですが、どの段階でも「自分の体の使い方」を見直すことが改善への近道になります。
改善までの目安と流れ
一般的には、炎症期(1〜2週間)→回復期(3〜6週間)→再発予防期(2〜3カ月)という流れが目安となります。ただし、症状の度合いや体の使い方によって差があるため、焦らず段階的に進めることが大切です。
当院では、痛みの軽減だけでなく、「再発しにくい歩き方・立ち方」に導くことを目標に、施術とセルフケアの両面からサポートしています。
再発予防・セルフメンテナンス

アキレス腱炎は、一度落ち着いたように見えても再び痛みが出ることが少なくありません。再発を防ぐためには、「回復後の過ごし方」が大切となります。ここでは、自分でできるセルフメンテナンスのポイントを紹介します。
ストレッチと筋力トレーニングの習慣化
まず基本となるのは、ふくらはぎからアキレス腱にかけての柔軟性を保つことです。朝起きた直後や運動後は腱が硬くなりやすく、ストレッチを取り入れることで再発リスクを減らせることができます。
当院では、ストレッチだけでなく下腿の筋力バランスにも注目しています。たとえば、ヒラメ筋や腓腹筋を均等に使うトレーニングや、足裏のアーチを支えるインナーマッスルを意識した運動を組み合わせることで、腱にかかる負担を分散させることができると考えています。
ウォーミングアップとクールダウンの工夫
「運動前後の準備」が不足すると、アキレス腱へのストレスが増えやすくなります。
運動前には、軽いジョギングや足首回し、ふくらはぎの動的ストレッチで血流を高めましょう。運動後は、静的ストレッチやアイシングで熱を抑えることで回復がスムーズになります。
靴選びとインソール調整
意外と見落とされがちなのが靴の選び方です。
ソールの硬さ、かかとの高さ、クッション性が合わない靴は、アキレス腱への負荷を増やす原因になります。扁平足や外反母趾の方は、足のアライメントが崩れやすいため、オーダーインソールや補助具の活用が効果的です。
負荷管理と早期介入のポイント
運動を再開するときは、「痛みがない=完全に回復」とは限りません。
ランニング距離を急に増やしたり、ジャンプ動作を繰り返したりすると再発することがあるため、1週間ごとに10%ずつ負荷を上げるくらいのペースが望ましいです。
また、「朝のこわばりが戻った」「押すと違和感がある」といった初期サインが出た段階で、早めにケアを行うことが重要になります。
当院では、こうした微細な変化を見逃さないために、施術中の触診や動作確認を丁寧に行い、必要に応じてセルフケアの内容を調整しています。
アキレス腱は毎日の歩行でも常に使われる部分です。だからこそ、再発予防は“特別なことをする”よりも“日常の動きを整える”ことが大切だと考えています。
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

廣瀬 知志
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


