荒川院へのご予約
スタッフブログ

頭が痛い時の対処法:即効でできるケア+予防につながる習慣
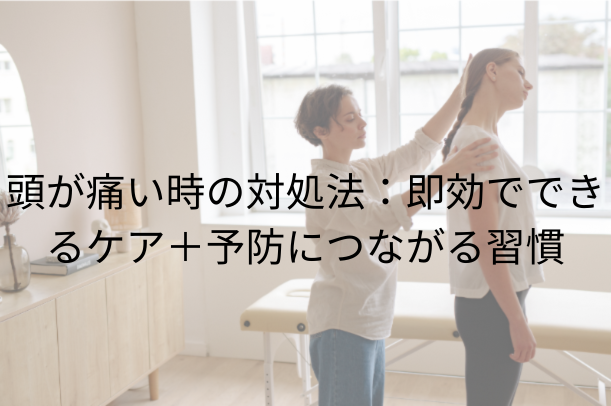
目次
「頭が痛い」といっても、その感じ方は人によってさまざまですよね。こめかみの奥がズキズキしたり、頭全体が締めつけられるように重く感じたり…。こうした違いの背景には“頭痛のタイプ”が関係していると言われています。
頭痛にはいくつかの種類がありますが、代表的なのは片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛の3つです。それぞれ原因やメカニズムが異なり、効果的な対処法も変わります。まずは、自分の痛みがどのタイプに近いのかを知ることが改善への第一歩です。
片頭痛 ― ズキズキと脈打つような痛み
片頭痛は、血管の拡張とそれに伴う神経への刺激で起こると考えられています。こめかみや頭の片側がズキズキと脈打つように痛み、光や音に敏感になる人も少なくありません。気圧の変化やホルモンバランスの乱れ、寝不足、空腹などが引き金になることも多いです。
発作的に痛みが出ることがあり、「片側の痛み」と「吐き気」を伴うのが特徴。血管や神経の過敏反応が関係していると言われており、冷やして安静にするのが有効とされるケースが多いです。
当院では、片頭痛の方に対して、首や肩の筋膜の緊張・顎関節の動き・姿勢の崩れをチェックします。血流や神経の流れを妨げている部分を見つけ、筋膜リリースや神経モビライゼーションで神経の滑走を促す施術を行っています。
緊張型頭痛 ― 締めつけられるような重さ
最も多いタイプがこの緊張型頭痛。首・肩・背中の筋肉がこわばることで血流が悪くなり、神経が刺激されて起こると言われています。特徴は「頭全体の重だるさ」や「締めつけられるような痛み」。長時間のデスクワークやスマホ操作で姿勢が崩れ、首まわりの筋肉に負担がかかる人に多い傾向があります。
「仕事が終わる夕方に痛くなる」「休日になると軽くなる」というパターンも多く、ストレスや目の疲れが関係している場合もあります。温める・姿勢を整えるなど、筋肉の緊張をやわらげるケアが大切です。
当院では、肩甲骨の可動域・背骨の動き・姿勢バランスを検査し、必要に応じて神経ストレッチや姿勢調整を行います。日常では、デスクでできる肩回し運動や深呼吸を取り入れることで、血流を保ちやすくなると言われています。
群発頭痛 ― 目の奥がえぐられるような痛み
群発頭痛は比較的まれですが、非常に強い痛みを伴うタイプです。特徴は目の奥をえぐられるような激しい痛みで、一定の周期で同じ時間帯に起こることが多いと言われています。涙や鼻水を伴うケースもあり、痛みの期間は数週間から数か月続くこともあります。
体内時計や自律神経の乱れ、アルコール摂取などが誘因になることがあるため、生活リズムの見直しも重要です。このタイプはセルフケアだけでの改善が難しいため、早めの専門機関への相談が勧められています。
当院では、来院された際に頭部や首の可動域、筋膜のつながりを検査し、神経系の圧迫や血流の偏りを確認します。施術では、首から背中にかけての筋膜調整を中心に、神経の通りを整えるアプローチを取り入れています。
タイプ別に対処法が変わる理由
片頭痛は「冷やす」、緊張型頭痛は「温める」、群発頭痛は「生活リズムを整える」といったように、タイプによってケアの方向性が異なります。これは、痛みを引き起こしているメカニズムが違うからです。
血管性の片頭痛では、冷やして血管の拡張を抑えることが効果的と言われています。一方で筋緊張による頭痛では、温めて血流を促すほうが改善しやすい傾向にあります。
当院では、初回の検査で姿勢・筋膜・神経・血流の4方向から体を分析し、頭痛のタイプを正確に見極めた上で、最適な施術とセルフケアを提案しています。
2.緊急性あり?来院を考えるべきサインと注意点

頭が痛いとき、「少し休めば良くなるだろう」と思って様子を見る人は多いですよね。けれど、中には放置すると危険なタイプの頭痛もあると言われています。どんなときに注意が必要なのか、そして整体で対応できるケースとそうでないケースについて見ていきましょう。
放置してはいけない頭痛のサイン
もし次のような症状がある場合は、一度医療機関での検査を考えた方が良いとされています。
- 今までにない強い痛みが急に出た
- 痛みが日に日に強くなっている
- 吐き気・嘔吐・視覚異常(光がまぶしい、見えづらい)がある
- 手足のしびれ、ろれつが回らないなどの神経症状がある
- 発熱や首の強いこわばりを伴う
こうした症状の中には、脳出血・くも膜下出血・髄膜炎などの可能性もあると考えられています。整体で扱える範囲を超えるケースもあるため、「ただの頭痛だから」と軽く見ず、早めに相談することが大切です。
整体で対応できるケースと医療機関に相談すべきケース
一方で、筋緊張や姿勢の崩れが原因の頭痛は、整体の検査と施術で改善を目指せる場合もあります。たとえば、首・肩・背中まわりの筋膜が硬くなり、血流が滞っていることで痛みが出ているケースです。この場合、筋膜リリースや神経モビライゼーションを行うことで、神経や血流の流れを促し、頭痛が軽くなることが多いと言われています。
当院では、痛みの強さや出るタイミングを細かく聞き取り、首・肩甲骨・顎関節・背骨などの動きを検査します。そのうえで、「整体で対応できる筋肉性の頭痛なのか」「医療的な検査が必要か」を明確に判断した上で施術方針を決めています。
また、医療機関で問題がないと確認された方でも、再発を繰り返す頭痛に悩むケースは多く見られます。そのような場合は、姿勢の改善やストレス緩和、生活習慣の見直しを組み合わせた整体アプローチが有効とされています。
早めの検査が安心につながる理由
「もう少し様子を見よう」と我慢してしまうと、痛みが慢性化してしまうこともあります。頭痛は体からのサインのひとつであり、原因を放置することで別の不調(めまい・肩こり・睡眠の質の低下など)につながることもあると言われています。
当院では、初回時に姿勢や神経の状態を検査し、必要に応じて医療機関での画像検査をおすすめする場合もあります。そのうえで、整体でできる範囲を明確にし、体のバランスを整えて痛みの出づらい状態を目指していきます。
「痛みが続く」「何度も繰り返す」「日常生活に支障が出ている」──そんなときこそ、早めの検査が安心への第一歩です。自分の体の状態を正しく知ることが、改善への近道になると言われています。
3.即効でできる頭痛の対処法(セルフケア編)

「今すぐなんとかしたい…」そんなときに、自分でできる頭痛ケアを知っておくと安心ですよね。実は、頭痛のタイプによって“冷やすほうが良い”場合と“温めたほうが良い”場合があり、ちょっとした使い分けで楽になることがあると言われています。ここでは、ご自宅で簡単にできるケア方法を紹介します。
冷やす・温めるの使い分けを知ろう
片頭痛のようにズキズキと脈打つような痛みがあるときは、血管が拡張しているサインのことが多く、冷やすことで血流を落ち着かせると楽になる場合があります。タオルで包んだ保冷剤をこめかみや首の後ろに当てて、数分間ゆっくり深呼吸をしてみましょう。
一方、締めつけるような重さを感じる緊張型頭痛では、首や肩の筋肉がこわばっていることが多いため、温めて血流を促すのが良いとされています。蒸しタオルや入浴でじんわり温め、筋肉をゆるめると神経の通りもスムーズになりやすいです。
ツボ押し・ストレッチで血流を整える
こめかみから手の甲にかけての「合谷(ごうこく)」や、うなじ部分の「風池(ふうち)」と呼ばれるツボは、頭の緊張をやわらげるとされています。強く押す必要はなく、深呼吸をしながら10秒ほどゆっくり押すのがおすすめです。
また、肩甲骨を動かすストレッチも効果的です。座ったままでも、両肩をゆっくり後ろに回すだけで、首・肩の血流が改善しやすくなると言われています。
当院では、こうしたセルフケアに加えて、神経モビライゼーションや筋膜リリースで神経と筋膜の滑走を整える施術を行っています。自分では届かない深層部の緊張をゆるめることで、頭痛が起きにくい体づくりをサポートしています。
姿勢と呼吸を整えるだけでも変化する
意外かもしれませんが、呼吸が浅くなると首や肩に余計な力が入り、頭痛が起きやすくなることがあります。デスクワーク中や寝る前に、**「背すじを軽く伸ばして深く息を吐く」**ことを意識するだけでも、体の緊張がゆるみやすくなります。
当院では、呼吸と姿勢のバランスを重視した検査を行い、背骨の動きや肩甲帯の安定性をチェックしています。必要に応じて、自宅でも再現できる呼吸ストレッチをお伝えしています。
日常生活で意識したい「予防のヒント」
・スマホやPCを長時間使うときは、1時間ごとに軽く首を回す
・水分をこまめに取る(脱水は片頭痛を誘発しやすいと言われています)
・寝すぎ・寝不足を避けて、リズムを整える
・枕の高さを見直し、首が詰まらない姿勢をつくる
日常のちょっとした工夫が、頭痛の頻度を減らすきっかけになるかもしれません。体が教えてくれるサインを見逃さず、無理のないケアから始めてみましょう。
再発を防ぐための日常ケアと予防のポイント
頭痛が落ち着いても、「また痛くなりそう…」という不安を感じる方は多いですよね。実は、日常のちょっとした習慣を整えることで、再発のリスクを減らせることがあると言われています。ここでは、普段から意識しておきたい生活の工夫やセルフケアを紹介します。
姿勢と環境を整えることが第一歩
長時間のデスクワークやスマホ操作によって、首や肩にかかる負担は想像以上です。特に、頭が前に出る姿勢(いわゆるスマホ首)になると、首まわりの筋肉が常に緊張し、血流や神経の流れを妨げる要因になると言われています。
座るときは「耳・肩・腰が一直線になる」よう意識し、パソコンの画面は目の高さに合わせるのがポイントです。椅子の高さを少し変えるだけでも、首への負担が減るケースもあります。
当院では、こうした姿勢の崩れを細かく検査し、骨盤・背骨・肩甲骨の位置関係を調整することで、頭の位置が自然に安定するようサポートしています。
呼吸と睡眠リズムを見直す
浅い呼吸が続くと、体は常に緊張モードになり、自律神経のバランスが崩れやすくなると言われています。特に片頭痛の方は、リラックスできる時間を意識的に取ることが大切です。
寝る前に**深く息を吐く「呼吸リセット」**を行うと、副交感神経が働きやすくなり、眠りが深まりやすくなります。睡眠不足や寝すぎも頭痛の原因になることがあるため、毎日ほぼ同じ時間に寝起きするリズムを意識しましょう。
当院では、施術の中で呼吸の深さや肋骨の動きを検査し、必要に応じて「胸郭ストレッチ」や「横隔膜リリース」を取り入れています。呼吸が整うことで、自然と頭や首の筋肉もゆるみやすくなると言われています。
食事と水分で体の巡りを整える
意外と見落とされがちなのが、水分不足や食事の偏りです。カフェインの摂りすぎや脱水は血管の反応を変え、片頭痛を誘発することがあるとされています。こまめな水分補給と、バランスの取れた食事を意識しましょう。
特に、マグネシウムやビタミンB群は神経の働きを整える栄養素として知られています。ナッツ類や青魚、緑黄色野菜などを日常に取り入れるのもおすすめです。
定期的なメンテナンスで体をリセット
頭痛が改善しても、姿勢や筋膜のクセが残っていると再発しやすくなる場合があります。当院では、施術後の経過を見ながら、月1回程度のメンテナンスを提案しています。
検査で筋膜の硬さや関節の動きを確認し、必要な箇所を軽く調整することで、日常生活でのストレスが体に溜まりにくくなります。整体を「痛みを取る場」ではなく、「整える習慣」として取り入れることが大切だと言われています。
4.再発を防ぐための日常ケアと予防のポイント
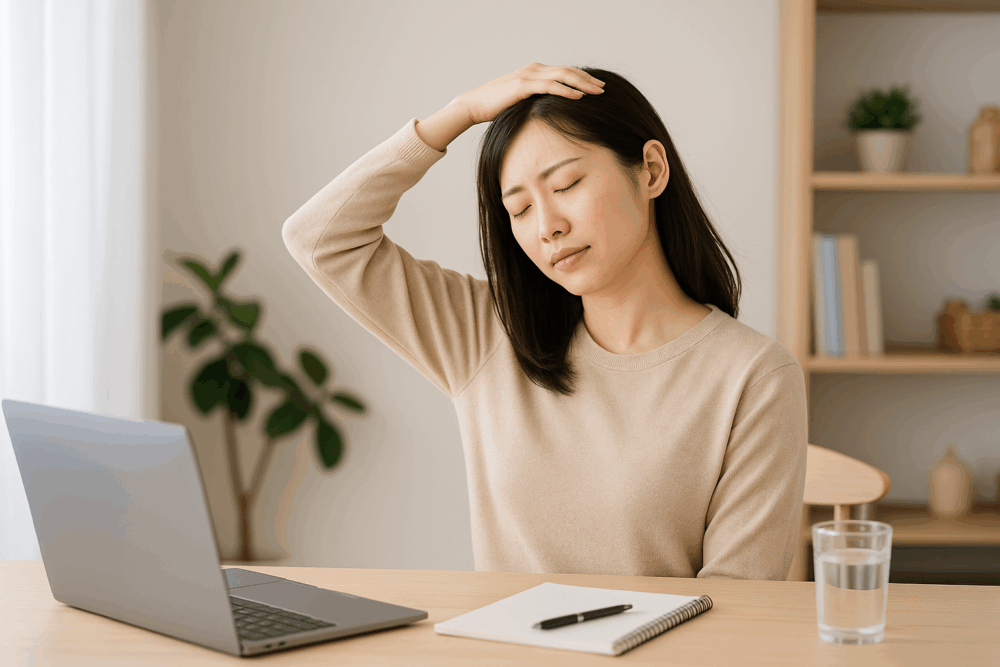
頭痛が落ち着いても、「また痛くなりそう…」という不安を感じる方は多いですよね。実は、日常のちょっとした習慣を整えることで、再発のリスクを減らせることがあると言われています。ここでは、普段から意識しておきたい生活の工夫やセルフケアを紹介します。
姿勢と環境を整えることが第一歩
長時間のデスクワークやスマホ操作によって、首や肩にかかる負担は想像以上です。特に、頭が前に出る姿勢(いわゆるスマホ首)になると、首まわりの筋肉が常に緊張し、血流や神経の流れを妨げる要因になると言われています。
座るときは「耳・肩・腰が一直線になる」よう意識し、パソコンの画面は目の高さに合わせるのがポイントです。椅子の高さを少し変えるだけでも、首への負担が減るケースもあります。
当院では、こうした姿勢の崩れを細かく検査し、骨盤・背骨・肩甲骨の位置関係を調整することで、頭の位置が自然に安定するようサポートしています。
呼吸と睡眠リズムを見直す
浅い呼吸が続くと、体は常に緊張モードになり、自律神経のバランスが崩れやすくなると言われています。特に片頭痛の方は、リラックスできる時間を意識的に取ることが大切です。
寝る前に**深く息を吐く「呼吸リセット」**を行うと、副交感神経が働きやすくなり、眠りが深まりやすくなります。睡眠不足や寝すぎも頭痛の原因になることがあるため、毎日ほぼ同じ時間に寝起きするリズムを意識しましょう。
当院では、施術の中で呼吸の深さや肋骨の動きを検査し、必要に応じて「胸郭ストレッチ」や「横隔膜リリース」を取り入れています。呼吸が整うことで、自然と頭や首の筋肉もゆるみやすくなると言われています。
食事と水分で体の巡りを整える
意外と見落とされがちなのが、水分不足や食事の偏りです。カフェインの摂りすぎや脱水は血管の反応を変え、片頭痛を誘発することがあるとされています。こまめな水分補給と、バランスの取れた食事を意識しましょう。
特に、マグネシウムやビタミンB群は神経の働きを整える栄養素として知られています。ナッツ類や青魚、緑黄色野菜などを日常に取り入れるのもおすすめです。
定期的なメンテナンスで体をリセット
頭痛が改善しても、姿勢や筋膜のクセが残っていると再発しやすくなる場合があります。当院では、施術後の経過を見ながら、月1回程度のメンテナンスを提案しています。
検査で筋膜の硬さや関節の動きを確認し、必要な箇所を軽く調整することで、日常生活でのストレスが体に溜まりにくくなります。整体を「痛みを取る場」ではなく、「整える習慣」として取り入れることが大切だと言われています。
5.症状が続くときの来院・検査の目安
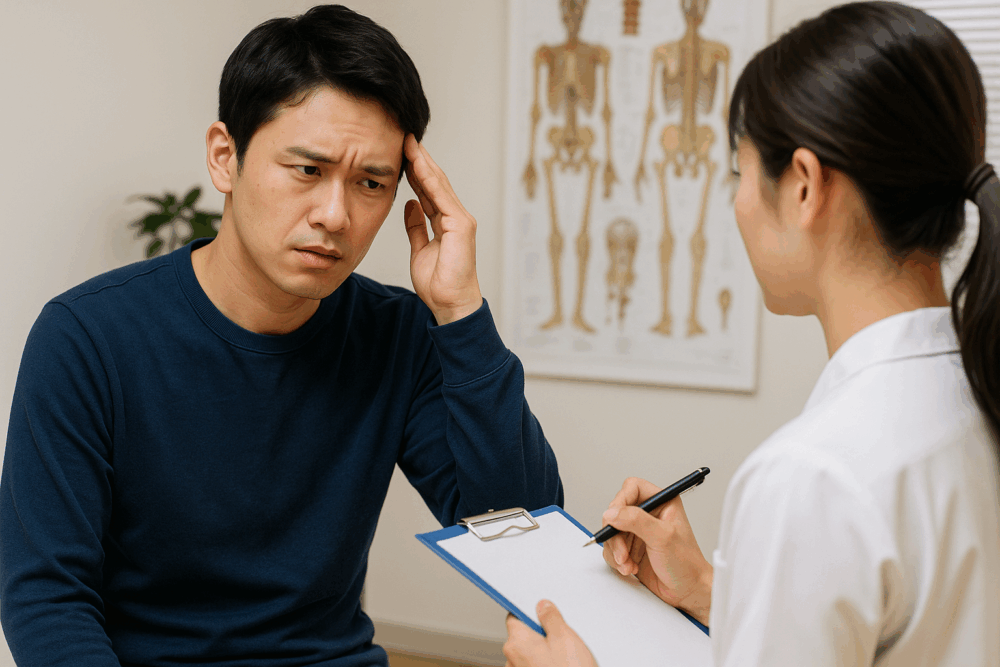
「頭痛くらいで整体に行ってもいいのかな?」と迷う方は多いですよね。実際のところ、頭痛には一時的なものもあれば、体のバランスの崩れや神経の働きに関係して長く続くケースもあると言われています。ここでは、整体への来院を考えるタイミングや検査で見るポイントについてお話しします。
頭痛が続くときに気をつけたいサイン
頭痛が数日から数週間続く、もしくは同じような痛みを何度も繰り返す場合は、体の構造的なゆがみや筋膜の緊張が関係していることがあります。特に以下のようなケースは、一度しっかりと検査を受けることがすすめられています。
- 首や肩こりとセットで頭痛が出る
- 長時間のデスクワークで痛みが強くなる
- 朝起きたときから頭が重い
- 天候や気圧の変化で痛みが出やすい
こうした特徴がある場合、姿勢や血流、神経の通りに問題があることが多いと考えられています。
整体で行う検査と施術の流れ
当院では、まず最初に姿勢と動きのチェックを行います。頭の位置、首・背骨・骨盤のバランス、肩甲骨の動きなどを観察し、筋膜のつながりや神経の滑走性を丁寧に確認していきます。
痛みの出る部位だけでなく、原因がどこから始まっているのかを見極めるため、神経モビライゼーション(神経の動きを整える手技)や筋膜リリースを組み合わせながら施術を行うことが多いです。
また、頭痛の背景には「呼吸の浅さ」「噛みしめグセ」「胸郭の硬さ」なども関係していることがあり、それらも含めて全身の調整を行います。施術後には、セルフケアとしてできる簡単なストレッチや姿勢のコツもお伝えしています。
医療機関との連携も大切に
頭痛の中には、整体では対応が難しいもの(脳血管疾患や炎症性疾患など)もあります。そのため、当院では初回の検査時に必要に応じて医療機関での画像検査をおすすめすることもあります。
整体と医療機関の役割は違いますが、「異常がないとわかったうえで、体のバランスを整える」という流れが、安心して改善を目指すためには大切だと考えています。
来院を迷っている方でも、「原因を一緒に探ってほしい」という段階で相談していただくのも大歓迎です。痛みが出てから時間が経つほど、体がその姿勢を記憶してしまうとも言われています。早めの検査とケアが、再発を防ぐ第一歩になります。
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

瑞慶山 良二
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。



