荒川院へのご予約
スタッフブログ

寒い時の対処法|すぐできる体を温めるコツと冷えに強い生活習慣とは?
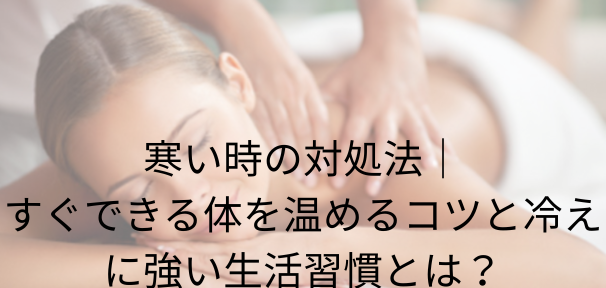
目次
1.寒い時の対処法とは?|よくある冷えの悩みとその背景

どういうときに「寒い」と感じるのか
「外に出た瞬間、体がこわばる感じがするんですけど、これって冷えなんですか?」
こんなふうにお話しされる方、実は少なくありません。
寒さを感じる要因は、単に気温の低下だけではありません。
たとえば、同じ気温でも風が強かったり、湿度が低かったりすると、体感温度はグッと下がると言われています。さらに、体調が優れないときや疲れがたまっているとき、環境の変化(室温差・気圧など)も影響しやすいようです。
私たちの体は、自律神経の働きで体温を一定に保とうとしますが、ストレスや睡眠不足が続くとその調整機能がうまく働かなくなることもあるんです。
冷えのタイプ:末端型・内臓型・全身型
一口に「冷える」と言っても、実は冷え方にはタイプがあります。
● 末端型冷え性
「手足の先だけがいつも冷たい…」というタイプ。血行が悪く、温かい血液がうまく末端まで届いていないと考えられます。
● 内臓型冷え性
手足はそれほど冷たくないのに、「お腹だけ冷える」「食後に体が冷える」というような方はこちら。内臓の血流や代謝の問題が関係していることもあるようです。
● 全身型冷え性
「とにかく体全体が冷える」「いつも寒気がする」という方に多いタイプ。体温調節機能が乱れている可能性があり、自律神経のバランスの影響が大きいとも言われています。
当院では、こうした冷えのタイプを見極めるため、体の動きや筋肉の緊張状態、骨格のバランス、姿勢のクセなどを細かく検査します。たとえば股関節まわりや肩甲骨の動きが悪くなると、循環が滞って冷えやすい体質につながることもあるんですよ。
一時的な寒さと慢性的な冷えの違い
「外が寒いときに冷えるのはわかるけど、部屋にいてもずっと寒いんです…」
そんなふうに、一時的な寒さと慢性的な冷えは別のものとして考える必要があります。
一時的な寒さは、温度や天候など外的な要因によるものが多く、体がしっかり温まればすぐに楽になることがほとんどです。
それに対して、慢性的な冷えは生活習慣や体の使い方、筋力・代謝の低下、自律神経の乱れなどが複雑に絡んで起こるケースが多く、放っておくと疲れやすさや不眠、消化不良といった不調につながることもあるんですね。
当院では、まず「なぜ冷えるのか」という根本の部分を探るため、骨盤や背骨の動き・緊張・柔軟性を丁寧にチェックしています。検査を通して、「動きのクセ」や「可動域の左右差」なども確認し、体の循環が整いやすい状態へと導いていきます。
#冷えのタイプ別対策
#整体でできる冷えケア
#寒さに強くなる生活習慣
#自律神経と冷えの関係
#慢性冷えと骨格バランス
2.今すぐできる!寒さを和らげる7つの簡単対処法
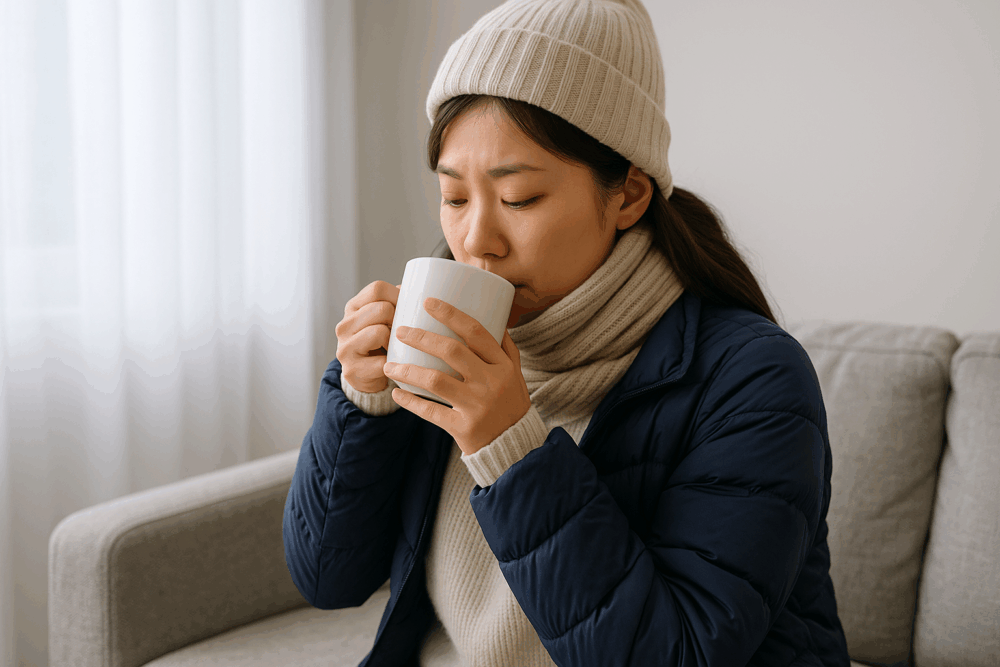
カイロの使い方(貼る場所のコツ)
「カイロってどこに貼るのが効果的なんですか?」
こう聞かれることが多いんですが、ポイントは“熱を逃がしにくい場所”を選ぶことなんです。
特におすすめなのが腰(仙骨のあたり)や首の後ろ、お腹など。ここは太い血管や神経が集まりやすく、温めると全身がじんわり楽になると言われています。逆に、手足の先など動きが多い場所は熱が逃げやすいので注意が必要です。
温かい飲み物を飲む際の注意点(カフェインや白湯など)
「温かい飲み物なら何でもいいんでしょ?」と思われがちですが、実は選び方もポイントがあります。
たとえばコーヒーや緑茶は温かくてもカフェインが含まれているため、利尿作用によって体を冷やす可能性もあるんですね。できれば白湯や生姜湯、ノンカフェインのハーブティーなどを選ぶのがおすすめです。
当院でも、セルフケアの一つとして“内臓を冷やさない飲み方”のアドバイスをお伝えしています。
レイヤード(重ね着)の工夫
「厚着すればいいってもんじゃないんですね…」という声も多いですが、その通りです。
体温調整には、空気の層をつくることが大切。インナーは吸湿性・保温性のあるもの、中間層は空気を含む素材、アウターは風を通しにくい素材…というふうに3層構造を意識すると、同じ服装でもかなり違いが出ると言われています。
足元・首・お腹を重点的に温める理由
「なぜか足だけ冷えて眠れないんですよ…」という方には、“三首”と呼ばれる首・手首・足首のケアがカギになります。
この3か所は皮膚が薄く、太い血管が通っているため、冷えると全身に冷えが広がりやすいようです。特にお腹(腹部)も大切で、内臓を温めると体の中心が安定しやすくなると言われています。
深呼吸や軽いストレッチで血流アップ
体が冷えているときって、つい肩に力が入って呼吸が浅くなりがちなんです。
そんなときは、ゆっくり深呼吸して、背中や肩甲骨を動かすようなストレッチを取り入れてみてください。
当院では、可動域の検査を通して「どこが動いていないのか」「どこで血流が滞っているのか」を確認しています。特に股関節や骨盤まわりの動きが硬い方は、冷えとセットで腰痛や不調が出やすい傾向があるようです。
即効性のあるツボ押し(合谷・三陰交など)
「外出先で寒くなったらどうしたらいいですか?」という方には、ツボ押しが便利です。
手の甲にある「合谷(ごうこく)」や、足首の内側にある「三陰交(さんいんこう)」は、全身の巡りをよくするツボと言われています。ゆっくり押しているだけでも、体の芯がじわっと温かく感じられることがあるようです。
湯たんぽ・電気毛布などの活用
「寝るときはどうしたらいい?」というご相談では、湯たんぽや電気毛布の活用がおすすめです。
ただし、長時間・高温での使用は低温やけどのリスクがあるため、注意が必要です。当院では、寝る直前の環境づくりとしてお腹や腰を10分程度温めるなど、時間を区切った使い方を推奨しています。
#寒さ対策セルフケア
#今すぐ温まる方法
#カイロの貼り方
#冷えに効くストレッチ
#整体でできる冷えの分析
3.冷えに強い体づくり|食事・運動・睡眠の見直しポイント

温活におすすめの食材(根菜・発酵食品・生姜など)
「体を温める食べ物って、結局なにを選べばいいんですか?」
このご質問、寒い時期によくいただきます。冷えに強い体づくりを考えるなら、根菜類や発酵食品、生姜など、体の内側からじんわり温めてくれる食材を意識してみるとよいかもしれません。
たとえば、ごぼう・にんじん・れんこんなどの根菜類は、加熱調理することで消化にもやさしく、体を冷やしにくい食材として知られています。納豆・味噌・ぬか漬けといった発酵食品も腸内環境を整える働きがあり、免疫や代謝の面からも冷え対策の一環になると考えられています。
当院では、施術中に食事の傾向を伺いながら、栄養や体調との関係性を探ることもあります。無理な制限よりも、“温める”という視点で食生活を整えていくことが大切です。
筋肉を増やすと冷えにくくなる理由
「冷えやすい体質なんですけど、運動ってやっぱり必要ですか?」
これは実はとても重要な視点です。筋肉は、熱をつくり出す“体のストーブ”のような役割を担っていて、特に**下半身の筋肉(太もも・お尻など)**をしっかり使うことで、体温を一定に保ちやすくなると言われています。
筋肉量が少ない方は、体の熱が逃げやすくなる傾向があるため、ウォーキングや軽いスクワット、階段の上り下りなど、日常に取り入れられる動きを意識してみるのも一つの手です。
当院の施術でも、筋肉の緊張や動きのクセをチェックし、使えていない筋肉の部位や偏りを把握したうえで、セルフケアや運動の提案につなげています。
寝る前の入浴やルーティンの重要性
「布団に入っても手足が冷たくてなかなか眠れません…」
そんな方には、寝る前の習慣づくりがとても大切です。たとえば、ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで副交感神経が優位になり、リラックスしやすい状態が整いやすくなると言われています。
さらに、入浴後すぐに靴下を履く・温かい飲み物を飲む・ストレッチを取り入れるなど、毎晩のルーティンを整えることで、自然と冷えにくい体へつながっていくこともあるようです。
当院でも、睡眠環境や生活リズムのヒアリングを行い、「日中は動けているか」「入浴後に体が冷えていないか」などのチェックを通して、セルフケアの工夫を一緒に考えていきます。
#冷えに負けない体づくり
#温活食材の選び方
#筋力アップで代謝向上
#寝る前の冷え対策
#整体と生活習慣の連携
4.整体師が教える寒さ・冷えやすさの本当の原因とケア方法

骨格の歪みや姿勢のクセによる血流低下
「姿勢が悪いって、冷えにも関係あるんですか?」
そんなご質問をよくいただきますが、実は骨格の歪みや姿勢のクセが血流を妨げてしまうことがあるようです。
たとえば、骨盤が後ろに倒れていたり、猫背の姿勢が続いたりすると、背中や腰回りの筋肉が緊張しやすくなり、その結果、血液の循環がスムーズにいかなくなることがあるんですね。
とくに股関節や肩甲骨まわりの動きが制限されていると、全身の巡りにも影響が出やすくなるため、「冷えやすい」「末端がなかなか温まらない」というお悩みにもつながるケースがあるようです。
自律神経の乱れと冷えの関係
「寝ても疲れが取れないし、朝から体が冷たい気がして…」
そんなふうに感じている方は、自律神経がうまく働いていない可能性もあるかもしれません。
自律神経は、体温や血流の調整を無意識にコントロールする役割がありますが、ストレス・過労・睡眠不足などが続くと、そのバランスが崩れやすくなることがあるんです。
結果として、体が「寒い」と感じていても、熱を生み出す機能がうまく働かずに冷えが慢性化してしまうこともあるようです。
当院では、こうした状態を**“姿勢と神経の両面”からチェックする**ことを大切にしています。
当院(整体院)で行っているチェックポイントとアプローチ例
当院では、まず「冷えている部位」そのものではなく、**なぜその部分が冷えるのか?**という“根本的な原因”を探ることからスタートします。
具体的には、以下のようなポイントを検査します:
- 骨盤の傾きや左右差
- 股関節・足首・肩甲骨など主要関節の可動域
- 背骨の柔軟性と緊張のバランス
- 呼吸の深さ(肋骨や横隔膜の動き)
- 神経反射や血流反応の状態
これらの検査結果をもとに、動きが滞っている部分の可動性を取り戻す施術や、自律神経を整える呼吸・ストレッチ指導を組み合わせたアプローチを行っています。
セルフケアについても、「今の体の状態に合ったやり方」でお伝えするようにしているため、毎回の検査で内容を微調整しながらサポートしていきます。
#骨格の歪みと冷えの関係
#自律神経と体温調整
#整体でできる冷えケア
#姿勢から見直す冷え対策
#冷えに強い体づくりの第一歩
病院に行くべき寒さ・冷えの症状とは?

冷えが病気と関係しているケース(貧血・甲状腺疾患・自律神経失調など)
「なんだかずっと寒いし、他の人と温度感覚が合わないんですよね…」
こうした違和感、もしかすると単なる冷え性ではなく、体の内部に原因がある可能性も考えられます。
たとえば貧血があると、血液中の酸素が全身に届きにくくなり、手足の冷えや倦怠感につながることがあるようです。
また、甲状腺の働きが低下していると、代謝が落ち、体温をうまく調整できなくなるとも言われています。
そのほか、ストレスや生活リズムの乱れが続くと、自律神経がうまく機能しにくくなることもあるため、冷えだけでなく動悸・胃腸トラブル・寝つきの悪さなど、他の不調が同時に出てくることもあるようです。
手足のしびれ・むくみ・皮膚の変色がある場合
「最近、冷えるだけじゃなくて足がむくむし、しびれも気になります…」
そんな症状がある方は、血流や神経の通り道に何らかの影響が出ているかもしれません。
特に注意したいのが、皮膚の色の変化や触ったときの感覚の鈍さ。これらは血管や神経に関係することが多く、冷えだけでは片づけられないこともあるため、無理にセルフケアで我慢せず、医療機関での検査を検討してみるのも一つの判断だと思います。
整体やセルフケアで改善しないときの相談先
「ストレッチもカイロもやってるけど、なんだか冷えが取れない…」
このように、セルフケアや整体だけでは変化が感じにくい場合、冷えの背景に別の体調不良が隠れている可能性もあります。
当院でも、施術前の検査で筋肉の状態や可動域のチェック、呼吸の浅さや姿勢のクセなどを確認しますが、それでも冷え以外の反応が見られるときには、病院との連携をおすすめするケースもあります。
たとえば、冷えと一緒に強い倦怠感・吐き気・異常な発汗などがある場合は、早めの医療相談が望ましいと言われています。
整体と医療、それぞれの得意な領域をうまく活かしながら、ご自身の体と向き合っていけるといいですね。
#冷えと病気の関係
#しびれや変色は要注意
#整体と医療の使い分け
#自律神経と冷えのつながり
#慢性的な冷えの見極め方
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

瑞慶山 良二
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


