荒川院へのご予約
スタッフブログ

「寝過ぎて頭痛い」原因と対処・予防法|今すぐできるリセット術
目次
なぜ寝すぎで頭が痛くなる?原因を知ろう

血管の拡張と片頭痛のメカニズム
「寝過ぎて頭痛い」と感じるとき、片頭痛が関わっているケースがあると言われています。長時間眠ることで脳の血管が拡張し、拍動に合わせてズキズキと痛みを感じやすくなると考えられています。特に普段から片頭痛の傾向がある人は、この仕組みによって症状が出やすい傾向があるとされています。
当院では、首や肩の筋肉のこわばりが血流に影響を与えていないかを触診で確認します。必要に応じて骨盤や背骨の歪みもチェックし、全体的なバランスから頭痛への関与を探ります。施術は筋肉や関節の動きを整えるソフトなアプローチを取り入れており、ご自宅でできる首回りの軽いストレッチや深呼吸を組み合わせることで、再発の予防につなげやすくなります。
筋肉の緊張・血行不良と緊張型頭痛
もうひとつ多いのが、筋肉の緊張からくる「緊張型頭痛」と言われています。長く眠りすぎると同じ姿勢が続き、首から肩の筋肉が硬くなることで血行が悪くなり、後頭部から頭全体にかけて重だるさを感じることがあります。
当院では、首や肩の可動域を確認しながら、筋肉がどのように硬くなっているかを丁寧に見極めます。施術では優しく関節を動かすことで筋肉が緩みやすくなり、血流改善のサポートを目指します。また、日常生活では肩甲骨を回す体操や、入浴で首・肩を温めるセルフケアを提案しています。これらを組み合わせることで、頭痛が出にくい体の状態を保ちやすくなると言われています。
睡眠リズムのズレ(ソーシャル・ジェットラグ)やセロトニンの変動
寝すぎによる頭痛は、単に時間が長いからというだけでなく、体内時計の乱れとも関連があると考えられています。平日と休日で睡眠リズムが大きく変わると、いわゆる「ソーシャル・ジェットラグ」と呼ばれる状態になり、体がうまくリセットされずに頭痛が出やすくなることがあります。また、セロトニンの分泌バランスが崩れると、自律神経が不安定になり、結果として頭痛につながりやすいとも言われています。
当院では、こうした生活リズムの乱れが体に及ぼす影響についても説明しながら、日常で取り入れやすい工夫を一緒に考えます。たとえば、毎日同じ時間に起床することや、朝日を浴びて体内時計を整えることは、誰でも実践しやすい予防策になります。
#寝過ぎて頭痛い
#片頭痛と緊張型頭痛
#睡眠リズムの乱れ
#整体で整えるアプローチ
#セルフケアで予防
片頭痛と緊張型頭痛、見分け方は?

片頭痛の特徴
「寝過ぎて頭痛い」と感じるとき、その痛みが片頭痛かどうかを見分けることが大切だと言われています。片頭痛の特徴としては、ズキズキとした拍動性の痛みや、光や音に敏感になる、吐き気を伴うなどが挙げられます。片側だけに症状が出るケースが多いのも特徴とされています。
当院ではこうした症状の有無を丁寧にヒアリングし、首から頭にかけての血流や筋肉の状態を触診します。その上で体全体のバランスを整える施術を行い、過敏になりやすい神経の負担を和らげるアプローチを取り入れています。セルフケアとしては、静かな場所で横になる、こめかみを冷やすといった工夫が有効とされています。
緊張型頭痛の特徴
一方で、緊張型頭痛は首や肩の筋肉が固まることで起きると言われています。頭全体が締めつけられるような重さや、後頭部から首筋にかけてのだるさが目立つのが特徴です。長時間同じ姿勢をとったあとや、寝過ぎによって首が圧迫されたときに出やすいとされています。
当院では筋肉の緊張度合いや姿勢のクセを確認し、関節や筋肉の柔軟性を高める施術を行います。また、肩甲骨を動かす体操や首まわりを温めるセルフケアもあわせてお伝えし、日常的に取り入れていただくことで予防しやすくなります。
両者を見分けるポイント
片頭痛は「ズキズキ・片側・光や音に敏感」、緊張型頭痛は「重だるい・両側・筋肉のこり」といった違いがあります。ただし、両方が混ざって出る場合もあるため、自分だけで判断しづらいケースも少なくありません。
当院では、痛みの出方や体の状態を総合的に確認し、どちらのタイプが強いかを見極めたうえで施術を行います。自宅でのセルフケアと合わせることで、再発しにくい体づくりをサポートしています。
#片頭痛の特徴
#緊張型頭痛の特徴
#寝過ぎ頭痛の見分け方
#整体でのチェックポイント
#セルフケアの工夫
寝過ぎによる頭痛を“今すぐ”緩和する方法
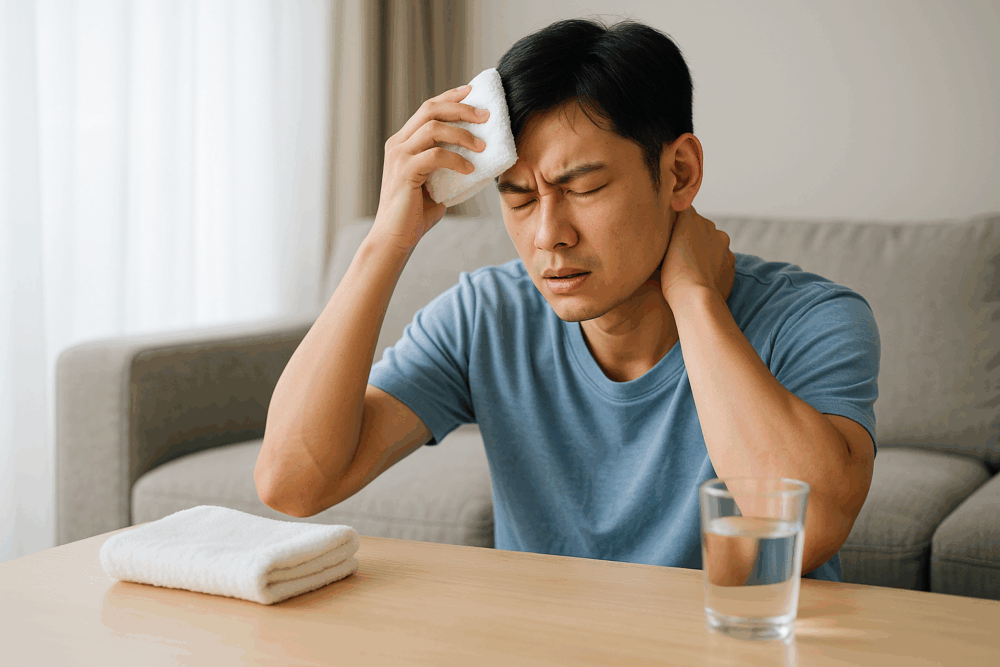
片頭痛には「冷やす」ケア
寝過ぎたあとにズキズキするような痛みを感じるときは、片頭痛の可能性があると言われています。この場合はこめかみや後頭部を冷やすと、血管の拡張を落ち着かせやすいと考えられています。氷枕や冷却シートをタオルで包んで使うと、肌への刺激も和らぎます。静かな暗い部屋で安静に過ごすのもポイントとされています。
当院では、片頭痛に対して首まわりの過度な緊張がないかを検査し、姿勢や背骨のバランスも確認しています。自律神経に関わる部分をソフトに整える施術を取り入れ、神経の負担を減らすことを目指します。
緊張型頭痛には「温める」ケア
反対に、後頭部から首にかけて重く締めつけられるような痛みは、緊張型頭痛の可能性が高いとされています。この場合は首や肩を温めることで血流が促され、筋肉のこわばりが緩みやすくなると言われています。蒸しタオルを首にあてたり、ぬるめのお風呂に浸かるのも効果的です。
当院では、首から肩の可動域や筋肉の張りを触診し、関節の動きを回復させる施術を行います。セルフケアとしては肩甲骨を回す運動や軽いストレッチをおすすめしており、痛みが和らぎやすい体づくりを一緒に目指します。
見分けがつかないときの対処
自分では片頭痛か緊張型かを判断しづらいこともあります。そのようなときは無理に動かず、まずは安静にして頭を休めることが大切です。水分をしっかり取る、カフェインを少量だけ摂ることで頭痛が和らぐケースもあると言われています。
当院では、「頭痛のタイプがわからない」「セルフケアで変わらない」といった場合に、体の状態を丁寧に確認しながら施術の方向性を決めています。再発を繰り返さないように、生活リズムや姿勢の工夫もあわせて提案しています。
#寝過ぎ頭痛の緩和法
#片頭痛は冷やす
#緊張型頭痛は温める
#セルフケアの工夫
#整体で整えるアプローチ
寝過ぎ頭痛を防ぐ!生活リズムと習慣の工夫

睡眠時間を一定に保つ
「寝過ぎて頭痛い」と感じる背景には、平日と休日で睡眠時間が大きくずれていることが関係していると言われています。急に長く眠ると体内時計が乱れ、自律神経がバランスを崩しやすくなるためです。目安として7〜9時間の睡眠を毎日同じリズムでとることが、頭痛予防につながると考えられています。
当院でも、睡眠リズムの安定が体全体の回復力に直結すると考えており、生活の中で無理なく続けられる工夫を一緒に提案しています。
起床時間を揃える習慣
休日になると「もう少し寝たい」と思う方も多いですが、起床時間が大きくずれるとソーシャル・ジェットラグが起きやすくなると言われています。眠る時間を変えるよりも、起きる時間を毎日揃える方がリズムは安定しやすいとされています。
当院では日々のカウンセリングで、仕事や生活スタイルに合わせた現実的な起床時間の設定をサポートし、無理のない形で続けられるようアドバイスをしています。
昼寝の取り入れ方
どうしても眠気が強いときは、昼寝を取り入れるのも一つの方法です。ただし、30分以内・午後3時までといったルールを守ると夜の睡眠に影響しにくいとされています。
当院では施術後に眠気が出やすい方に、短時間の休息の取り方もお伝えしています。体の声に耳を傾けながら休むことで、頭痛を招きにくい状態を維持しやすくなります。
運動・ストレスケア・環境調整
適度な運動は血流を整え、自律神経の安定にもつながると言われています。ストレッチやウォーキングなど無理なくできるものを継続するとよいでしょう。また、寝室を暗く・静かに・快適な温度に整えることも大切です。
当院では体のゆがみを整える施術に加え、自宅で取り入れられるセルフケアや生活習慣の工夫もあわせてお伝えしています。姿勢改善や呼吸法など、小さな積み重ねが頭痛の予防に役立つと考えています。
#寝過ぎ頭痛の予防
#生活リズムの整え方
#休日も同じ起床時間
#昼寝の工夫
#整体と習慣改善
まとめ|タイプに合わせた対処と習慣改善で快適な朝へ

原因を知ることが第一歩
「寝過ぎて頭痛い」と感じたとき、その背景には片頭痛・緊張型頭痛・生活リズムの乱れといった要素が関わっていると言われています。まずは自分の頭痛がどのタイプに近いのかを知ることが、適切なケアにつながる第一歩になります。
今すぐできる緩和方法
片頭痛は「冷やす」、緊張型頭痛は「温める」といったシンプルな方法でも、症状が和らぐことがあるとされています。判断がつかないときは安静を優先し、必要に応じて水分補給や軽いカフェイン摂取も有効とされています。
習慣を整えて再発予防へ
毎日の睡眠リズムを一定に保つことや、休日の起床時間をずらさない工夫が、頭痛の再発を防ぐ大きなポイントと考えられています。さらに、日常に軽い運動やストレッチを取り入れ、寝室環境を整えることも安定した睡眠につながります。
当院でのサポート体制
当院では、単に症状を見るだけでなく、首や肩の筋肉・骨格のバランス・生活習慣の影響まで総合的に確認します。施術を通して体を整えるとともに、自宅で続けられるセルフケアや予防策をお伝えすることで、頭痛が出にくい状態を目指します。
#寝過ぎ頭痛のまとめ
#片頭痛と緊張型頭痛
#生活習慣の工夫
#整体でのチェックポイント
#セルフケアで予防
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

瑞慶山 良二
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


