荒川院へのご予約
スタッフブログ

左手がしびれるときに考えられる原因|放置せず確認したい体のサインとは?
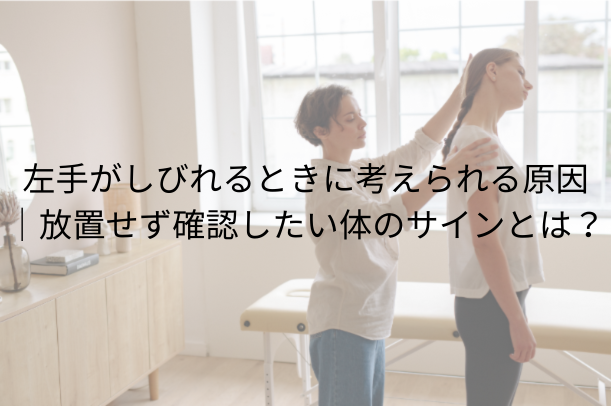
目次
左手がしびれる症状とは?どんな状態を指すのか

「左手がしびれてる感じがして…なんか気になるんだよね」
「それって、ビリビリしたり、ジンジンするような感覚?」
こんな会話、身近に聞いたことがあるかもしれません。
しびれといっても、人によって感じ方はさまざまです。よくあるのは「電気が走るようなピリピリ感」や「じんわり感覚が鈍るような違和感」、あるいは「手先の感覚がなくなるようなボワッとした感じ」などが挙げられます。これらの感覚は、神経の伝達に何らかの変化が起きているサインとも考えられます。
特に左手にしびれを感じる場合、神経だけでなく循環器系や内臓の影響が関係している可能性もあると考えられており、片側だけに症状が出ていることが多いのが特徴です。ただの疲れかと思っても、首や肩の緊張、体の使い方のクセが積み重なって、神経に軽い圧迫が起きているケースも少なくありません。
当院では、ただ「しびれている場所」だけを見るのではなく、首から背中、腕の動かし方や普段の姿勢までを丁寧に検査し、その方に合ったアプローチを行っています。
「ビリビリ・ジンジン」など感覚の種類と特徴
「チクチクする感じ」「指先の感覚が鈍くなってる」「触っても分かりづらい」など、しびれの表現は本当にさまざまです。
感覚のタイプには大きく分けて2つあります。ひとつは「感覚が過敏になるタイプ」で、ビリビリ・ピリピリする電気的な痛みに近いしびれです。もうひとつは「感覚が鈍くなるタイプ」で、触れている感じが分かりづらい、もしくは触れていないのに違和感があるようなタイプです。
こうした感覚の違いには、どの神経が関わっているか、どの部位で圧迫が起きているかなど、身体の内側で起きている状態が関係しているとも考えられています。
また当院では、症状をただ聞くだけではなく、実際の可動域や神経の通り道、筋肉や関節の動き方も見ながら、しびれの背景を総合的に読み解いていきます。必要に応じて自律神経のバランスや呼吸の状態も見直し、身体全体からしびれを捉えるようにしています。
一時的なしびれと継続するしびれの違い
「寝てる間に腕が圧迫されてしびれた」といった経験は、誰にでもあるかもしれません。こうした一時的なしびれは、血流が戻れば自然と消えていくことがほとんどです。
一方で、「数日経っても改善しない」「同じ部位に繰り返し起こる」「しびれと一緒にだるさや痛みがある」などの場合は、何かしら体の構造や神経経路に継続的な負担がかかっている可能性があるとも考えられます。
当院では、こうした継続的なしびれに対して、神経の通り道の圧迫や姿勢・動きのクセ、筋肉のバランスを多角的に確認します。また、再発を防ぐためのセルフケア(ストレッチや呼吸、動作の再教育)も、生活の一部に無理なく取り入れられるよう工夫しています。
#左手のしびれ
#ビリビリ感覚
#神経圧迫の可能性
#整体での検査ポイント
#しびれのセルフケア方法
左手がしびれるときに考えられる主な原因
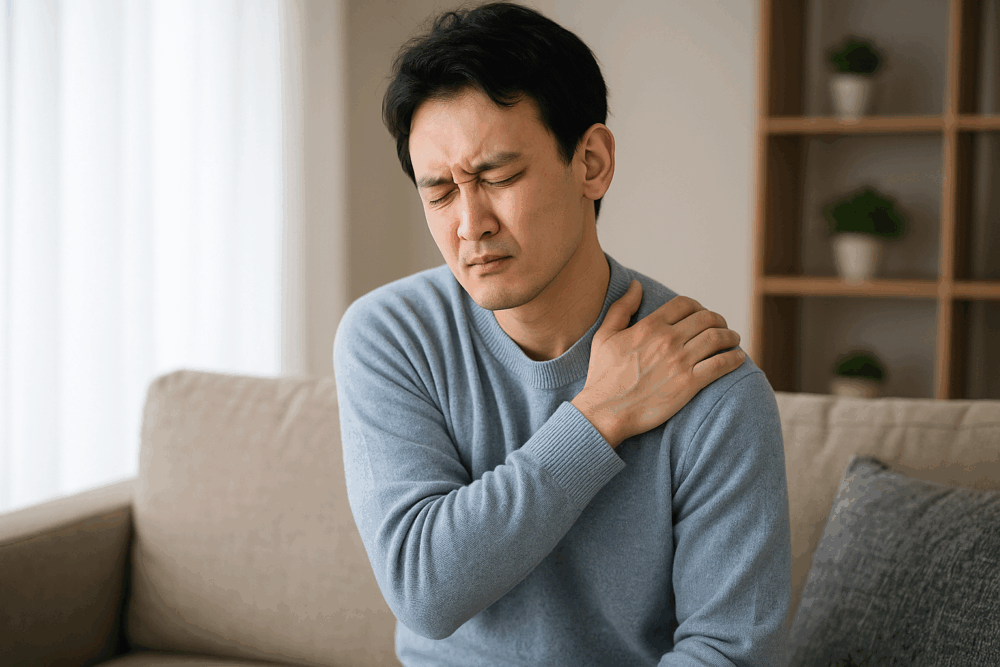
「なんか最近、左手がジンジンするんだよね…」「それ、もしかして首とか神経の圧迫かも?」
こんなやり取り、思い当たる人もいるかもしれません。
左手のしびれには、筋肉や関節、神経、さらには内臓の状態まで、さまざまな要因が関係していると考えられます。ここでは、よくある原因についていくつかご紹介していきます。
頸椎の異常(ヘルニア・ストレートネックなど)
しびれの原因としてよく挙げられるのが、首まわりのトラブルです。
特に「ストレートネック」や「頸椎ヘルニア」のように、首の骨の並び方や間にあるクッション(椎間板)に異常があると、周囲の神経が圧迫されやすくなります。
スマホやパソコン作業などで、首を前に出す姿勢がクセになっている方は注意が必要です。当院でも、そうした姿勢のクセを見極めるため、首や肩甲骨まわりの動きや筋肉の張り具合、背骨のアライメントを細かくチェックしています。
施術では、ただ筋肉をゆるめるのではなく、首〜背中の連動性や、肋骨・骨盤のバランスまで視野に入れた調整を行うことが多いです。
胸郭出口症候群・手根管症候群など末梢神経の圧迫
「腕を上げるとしびれる」「重たい荷物を持つと違和感がある」といったケースでは、末梢神経の圧迫が関係している場合も考えられます。
たとえば、「胸郭出口症候群」は、鎖骨や首まわりの筋肉が神経を圧迫することで起こるとされており、デスクワークや猫背姿勢が影響しているとも言われています。
また、手首の内側で神経が圧迫される「手根管症候群」では、特に親指・人差し指・中指あたりにしびれが出やすいという特徴もあります。
当院では、こうした状態を見極めるために、頸椎・肩・肘・手首それぞれの可動域や、負担がかかっている部位を触診しながら全体のつながりをチェックしています。局所の施術に加えて、肩甲帯や体幹の動きも整えることで、再発しづらい状態づくりを目指します。
内科的疾患(脳卒中・心疾患など)の可能性も
「突然しびれが出た」「片側だけで感覚が鈍くなった」など、いつもと違う感覚がある場合には、内科的な原因も疑われることがあります。
たとえば、脳卒中(脳梗塞や脳出血)や心疾患などでも、左手にしびれや脱力が出ることがあります。特に、ろれつが回らない、めまいが強い、意識がぼんやりするような場合は、早めの医療機関での確認が大切です。
ただ、多くの場合は慢性的な姿勢や日常生活のクセが神経や筋肉に影響しているケースも多く見られます。当院では、体の状態を全体で見ながら、必要に応じて医療機関でのチェックをご案内することもあります。
#左手のしびれの原因
#頸椎ヘルニアとストレートネック
#胸郭出口症候群と手根管症候群
#内臓由来のしびれに注意
#整体でできる検査とアプローチ方法
病院に行くべき?来院の目安と注意すべきサイン

「左手がしびれてるけど、これって放っておいても大丈夫かな…?」
「でも、なんとなく不安になる時もあるよね」
そんなふうに思っても、明確な判断がつきづらいのが“しびれ”という症状です。実は、放置してよいケースと注意が必要なケースには違いがあるとされています。
しびれが左右差ある・長引く・痛みや脱力を伴う場合
しびれそのものが一時的なものなら、少し様子を見てもよいと言われていますが、以下のような症状がある場合には、何かしら体に変化が起きている可能性があるとも考えられます。
- 左右どちらかだけに強く出る
- 数日〜数週間たっても変わらない
- しびれと同時に「痛み」「だるさ」「力が入りにくい」といった違和感がある
こういったサインが見られるときは、神経の圧迫や血流の問題だけでなく、稀に内科的な疾患が関係していることもあります。
当院では、片側のしびれに対して、姿勢・背骨・肩まわり・神経ラインの可動などを細かく検査しながら、生活のクセや過去のケガ、体の使い方なども含めて状態を整理します。
また、「手をよく使う作業がある」「腕を上げるとしびれる」など、日常動作の中で出る特徴的な動きにも着目し、体のつながりからアプローチするようにしています。
何科を来院すればいいかの目安(整形外科・神経内科など)
「気になるけど、どこに行けばいいのか分からない…」という声もよく聞きます。
しびれの原因によって、来院先の目安も少し異なる場合があります。
- 首や肩の不調が気になる → 整形外科で骨・神経の検査
- しびれに加えて言葉が出づらい、意識がぼんやりする → 脳神経外科・神経内科など
- 胸の圧迫感や動悸とともに左手がしびれる → 循環器内科で心臓の状態を確認
ただ、しびれの感じ方や出方は人によって大きく違うため、検査を受けても「異常なし」と言われることもあります。そのようなときこそ、姿勢・動き・呼吸・自律神経など“構造以外の要因”に目を向ける必要があると考えています。
当院では、来院前のヒアリングから、普段の動作や体のバランスを見直し、必要なケアとセルフケアの組み立てを一緒に行っていきます。
#しびれが続くときの目安
#片側だけのしびれは要注意
#何科に相談するか迷ったら
#検査で異常なしでもケアはできる
#整体でできるしびれの確認方法と視点
整体で確認するポイントとアプローチの一例

「しびれてる場所だけ見ても意味ないんですか?」
「実は、手よりも先に“体の土台”を見ることの方が大切なんですよ」
そんな会話が、施術前のカウンセリングでよく交わされます。左手のしびれといっても、その背景には首・肩・肋骨・背骨・神経のラインなど多くの要素が関わっていると考えています。
整体では、単にしびれている場所だけを見ず、体の全体のバランスから“なぜそこに負担がかかっているのか”を掘り下げていくことが重要になります。
頸椎・肩まわり・胸郭の可動性チェック
まず、最も丁寧に確認するのが首(頸椎)と肩・肋骨まわりの動きです。
首の動きが制限されている場合、神経の通り道が狭くなってしびれにつながることがあるとされており、特に下位頸椎(首の下の方)と肩甲帯の硬さは見逃せないポイントです。
また、呼吸に深く関係する肋骨(胸郭)の柔軟性が失われていると、腕を動かすたびに首や肩へ負担が集中しやすくなります。
当院では、これらの部位をひとつずつ丁寧に触診し、左右差や動きのクセ、呼吸の状態まで総合的に評価したうえで、調整を行っていきます。
姿勢や使い方による神経への負荷の見直し
「普段の姿勢とか使い方が原因になることってあるんですか?」
その答えは、多くのケースで“はい”に近い傾向があると考えています。
特に、猫背やストレートネックなどの姿勢が定着してしまうと、肩や腕を支える筋肉が過緊張を起こし、それが神経を圧迫する形につながることもあります。
当院では、日常の体の使い方や座り方・歩き方にまで視点を広げて、“無意識のうちに神経に負担をかけてしまう習慣”を一緒に見つけ出します。
そのうえで、正しい体の使い方を身につけるためのセルフケアや姿勢トレーニングをご提案することもあります。
自律神経バランスや血流の影響にも着目
しびれの背景には、神経や筋肉だけでなく、自律神経や血流の影響も関係していると考えています。
特に「寒さで悪化する」「ストレスが強くなると出やすい」といった場合には、自律神経の緊張や血行不良が一因となっている可能性があります。
当院では、体の緊張状態や呼吸の浅さ、自律神経のバランスにも着目し、交感神経と副交感神経の切り替えを促す施術や、リズムを整える呼吸運動なども取り入れています。
これは、筋肉や関節の調整だけではアプローチしづらい「内側からの変化」を促す手法のひとつです。
#整体で行うしびれの検査
#頸椎や胸郭の柔軟性を確認
#日常動作から神経の負担を見直す
#自律神経と血流にもアプローチ
#全身からしびれの原因を探る整体
自宅でできる対策と再発予防のヒント
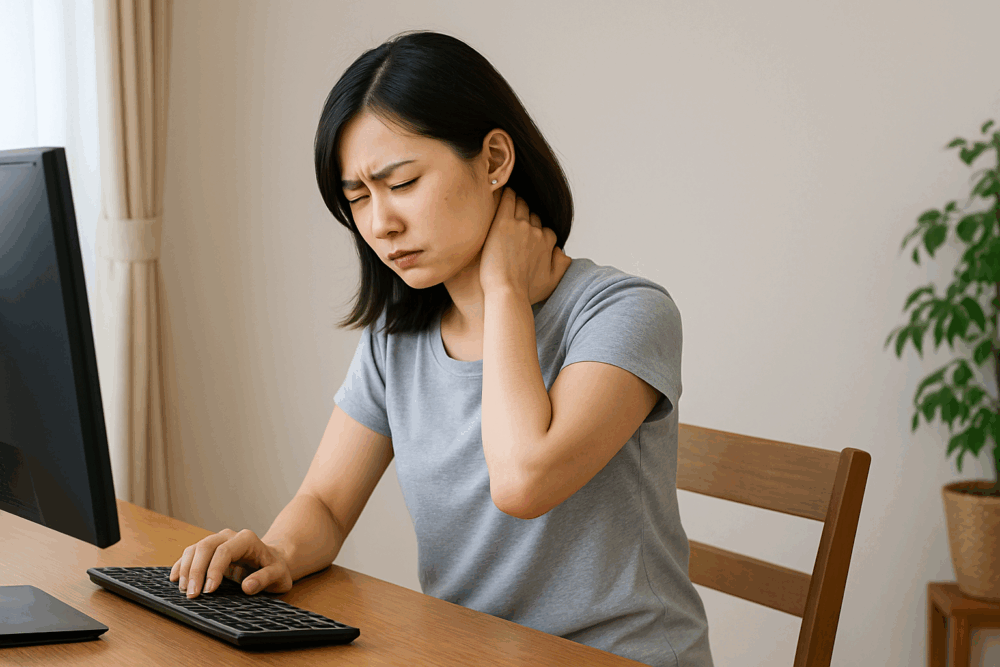
「整体で楽になったけど、またしびれが出たらどうしよう…」
「自分でも何かできることってあるのかな?」
そんな声をよく聞きます。実は、しびれを改善するうえで“セルフケアの積み重ね”がとても大切だと考えています。整体で体を整えるだけでなく、日常生活のクセを少しずつ見直していくことが、しびれの再発を防ぐカギになります。
姿勢の見直し・デスク環境の調整
まず意識したいのが、普段の姿勢になります。
特にデスクワークが多い方は、猫背や巻き肩の姿勢が首や腕の神経に負担をかけていることが多いです。画面の位置が低すぎたり、椅子の高さが合っていなかったりすることで、自然と肩が前に入りやすくなってしまいます。
当院では、施術時に座り方や立ち方のクセも一緒に確認し、椅子の深さ・画面との距離・肘の角度など、その方のライフスタイルに合わせた環境の整え方をご提案することが多いです。
軽めのストレッチや深呼吸などのケア方法
「ストレッチとか苦手で続かなくて…」という方でも大丈夫です。
しびれに対しては、強い運動よりも優しい動きの中で呼吸を整えることのほうが効果的とされることがあります。
たとえば、寝る前に首を軽く傾けて呼吸を深くするだけでも、首〜胸まわりの筋肉の緊張を和らげて、神経への圧迫を軽減するサポートになります。
当院では、そうした簡単に続けられるケア方法を施術後にお伝えしており、「これなら続けられそう」と言われることも多いです。
日常生活で避けたい悪い習慣
しびれの症状が出ている方の多くが、日常のちょっとしたクセによって神経に負担をかけている傾向があります。たとえば、
- スマホを長時間見続ける
- バッグをいつも同じ肩で持つ
- うつ伏せで寝る習慣がある
こうした無意識のクセが積み重なることで、体のゆがみや筋肉の緊張が強まり、神経を圧迫しやすくなるとも考えられます。
当院では、そうした日常の動作まで踏み込んだヒアリングを行い、無理なく改善できるポイントを一緒に探していきます。
#デスクワーク姿勢の見直し
#首肩への負担を軽減するセルフケア
#呼吸を活かした優しいストレッチ
#再発防止のための生活習慣改善
#整体×日常ケアでしびれ予防をサポート
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

廣瀬 知志
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


