荒川院へのご予約
スタッフブログ

膝窩リンパとは?腫れ・痛みとの関係とセルフケア方法を解説
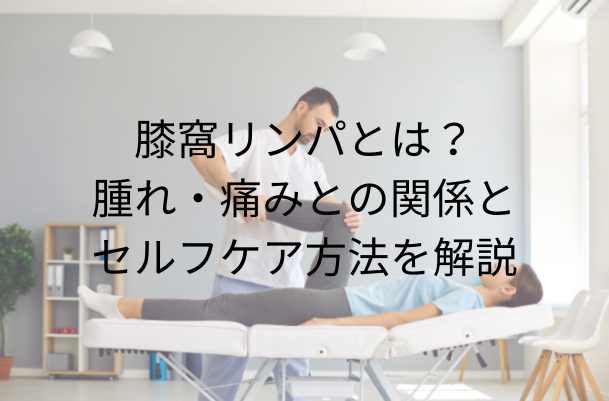
目次
膝窩リンパとは?|名称の意味と位置・役割

「膝窩」ってどこ?日常では意外と意識しない場所
「膝窩(しっか)」という言葉、聞き慣れないかもしれませんが、実は私たちが普段何気なく使っている“膝の裏”のことを指しています。膝を曲げたときにくぼむ部分です。「あれ、なんか膝裏が腫れてる?」と感じたことがある方もいるのではないでしょうか。その“くぼみ”の中には、筋肉、血管、神経、そしてリンパ節が複雑に集まっています。
リンパ節の役割とは?体の“見えないフィルター”
膝窩には「膝窩リンパ節」という小さなリンパのフィルターが存在します。リンパ節は体内にいくつもあり、ウイルスや細菌などの異物をとらえて、免疫細胞が働く“拠点”のような存在と言われています。ちょうど、体内の「交番」や「浄水器」のような役割を果たしているイメージです。
膝の裏にあるリンパ節も、足から流れてくるリンパ液をろ過して、体を守る働きをしています。
体をめぐるリンパの流れと膝窩リンパ節の関係
リンパ液は血液とは違い、心臓のようなポンプがありません。そのため、筋肉の動きや呼吸によってゆっくりと体をめぐっていきます。足のリンパは、重力に逆らって流れる必要があるため、特に膝やふくらはぎ周辺は詰まりやすい場所になります。
当院では、体の使い方や姿勢によってリンパの流れが滞ってしまっているケースも多く確認されています。例えば、長時間のデスクワークや立ちっぱなしでふくらはぎの筋肉が硬くなると、膝窩リンパ節周囲に圧迫が生じ、リンパの流れがスムーズでなくなることがあります。
当院では施術前に膝裏の圧痛・腫れ感・左右差を丁寧に触診し、リンパの滞りや筋肉の緊張を総合的に確認します。その上で、膝裏だけにアプローチするのではなく、太ももや骨盤、足関節の動きまで確認し、筋膜リリースや関節モビライゼーションを用いて全体のバランスを整える施術を行っています。
セルフケアとしては、ふくらはぎをやさしくほぐすストレッチや、膝裏を圧迫しない座り方を意識するだけでも、リンパの循環に役立つとされています。
#膝窩リンパとは
#膝裏の違和感
#リンパの流れを整える
#整体的な視点からケア
#足のむくみと膝裏の関係
膝窩リンパが腫れる・痛むのはなぜ?

膝裏が気になる?こんな症状はよくあるかもしれません
「膝の裏がなんとなく腫れてる気がする…」「押すとちょっと痛いかも」「しこりっぽいのがあるけど大丈夫?」
実際、膝窩リンパの違和感に気づくきっかけはこのような日常の感覚から始まる方が多いです。特に、しゃがんだときや正座をしたときに違和感を覚えやすくなります。
当院でも、「膝裏の腫れ」や「押すとズンと響くような痛み」といった訴えで来院される方は少なくありません。その場合、ただの筋疲労と判断せず、リンパの反応や筋肉の緊張度、動作のクセなどを丁寧に触診し、状態を見極めていきます。
膝窩リンパ節炎の可能性も|軽視できない炎症反応
膝窩リンパ節が腫れる原因の一つとして「リンパ節炎」が考えられています。これはリンパ節が細菌やウイルスに反応して炎症を起こしている状態と言われています。足や膝周辺のけが、擦り傷などから感染が広がることもあるため、侮れません。
当院では膝裏の腫れが見られる場合、患部周囲の皮膚状態や発熱、赤みなどの炎症サインも確認します。必要に応じて医療機関の受診を提案しながら、過度な刺激を避け、まずは安静と循環促進を意識した施術を行うようにしています。
スポーツや怪我による影響も見逃せない
膝窩リンパの腫れは、ランナーやジャンプ動作の多いスポーツ選手にも見られることがあります。というのも、膝裏には「腓腹筋」や「膝窩筋」といった筋肉が集中しており、ここが硬くなるとリンパや血流が滞りやすくなるためです。
特にフォームが崩れていたり、片脚に体重が偏っていたりすると、膝裏の組織に無意識のうちに負荷がかかってしまうことがあります。当院では動作のクセや立位での重心バランスをチェックし、再発しづらい体づくりをサポートしています。
感染症や免疫反応からくる腫れもある
膝窩リンパ節の腫れは、局所的な問題だけではなく、体全体の免疫反応の一部として現れる場合もあります。風邪をひいたあとや、体のどこかに炎症が起こっているときに、リンパ節が一時的に腫れることもあるとされています。
ただし、長期間しこりが引かない・熱を持つ・痛みが増してくるといった場合は注意が必要です。当院では「その場だけよくなればいい」ではなく、再発を予防する視点から、全身の状態を観察しながらアプローチしていきます。
#膝窩リンパ節の腫れ
#膝裏の違和感
#スポーツによる膝裏の負担
#リンパ節炎の可能性
#整体による根本サポート
膝裏の腫れや違和感があるとき考えられる疾患とは?

ベーカー嚢腫との違いとは?ふくらみの正体に注目
「膝の裏にやわらかいふくらみがあるけど、これって何だろう?」
そんなときに可能性の一つとして考えられるのがベーカー嚢腫(のうしゅ)です。関節の中にある滑液(関節液)が後方にたまることで、袋状の腫れができるものとされており、膝窩リンパ節の腫れと似たような見た目になる場合もあります。
ただし、リンパ節の腫れと異なり、ベーカー嚢腫は膝の屈伸で大きさが変わることがあり、比較的やわらかく弾力があることが特徴としてあります。当院では、膝関節のバランスや太もも裏の筋緊張の状態からもその違いを見極めて、適切な施術内容を検討しています。
深部静脈血栓症などの血管系疾患との見分け方
「片脚だけ急に腫れてきた」「触ると熱を感じる」「なんだか全体が重だるい」
このような症状がある場合、血栓(けっせん)の可能性も頭に入れておく必要があります。特にふくらはぎ〜膝裏の奥には太い静脈が走っており、血栓が詰まると急激な腫れや圧痛が出ることもあるため注意が必要です。
当院では、下肢の腫れや痛みに対して単なる筋疲労と決めつけず、圧痛の範囲や皮膚の色・温度差などを確認し、血流の停滞や浮腫との関連性も評価しています。必要な場合は、速やかに医療機関での検査を提案し、適切な対応をとるように心がけています。
半月板損傷や関節液貯留など整形外科的な関係も
膝裏の腫れや違和感は、関節内部のトラブルが関係していることも少なくありません。
たとえば、スポーツや日常の動作のなかで半月板にストレスがかかると、関節内で炎症が起こり、その影響で滑液が過剰に分泌されるケースもあります。これが膝裏に押し出されて、ふくらみとして現れることがあるのです。
当院では膝の動きの可動域や関節の引っかかり感、圧痛部位を細かく検査し、関節内の状態を間接的に評価しています。また、骨盤や股関節からの影響も視野に入れ、全体の動作改善を目的とした施術を行っています。
#膝裏の腫れの原因
#ベーカー嚢腫との違い
#血栓症との見分け方
#膝関節のトラブル
#膝窩の違和感を整体で評価
膝窩リンパが気になるときのセルフチェックとケア方法

まずは触ってみよう|しこりや熱感などの観察ポイント
「膝の裏がなんか腫れてるかも…」「しこりっぽい感触がある…」
そう感じたときに役立つのが、セルフチェックです。
触れるときは力を入れすぎず、指の腹でやさしく押すようにしましょう。
チェックするポイントは次の3つです。
- 大きさ:1cm以下であれば経過観察とされるケースもありますが、変化があれば要注意です。
- 動くかどうか:リンパ節のしこりは、比較的指で動く場合が多いといわれています。
- 熱感や赤み:熱を持っていたり、赤みがある場合は炎症が関係している可能性も考えられます
当院では、施術前に膝窩リンパだけでなく、ふくらはぎや太もも、骨盤周りの筋肉の緊張度、姿勢バランスなどもあわせて評価し、全体の状態から原因を探るようにしています。
やってみよう|簡単なリンパストレッチとケア
膝裏のリンパの流れを促すには、無理のないストレッチやセルフマッサージが有効だとされています。
例えば…
- 足首を動かすだけでも効果的:ふくらはぎの筋肉がポンプの役割を果たします。
- 膝裏をやさしくさする:円を描くように手のひらでさするだけでもOKです。
- 太もものストレッチ:太ももの裏側を伸ばすことで、膝裏への圧迫も緩和されやすくなります。
当院では、患者さまの状態に合わせて、ご自宅でできるケア方法や、負担の少ない姿勢で行えるエクササイズもアドバイスしています。
意外と見落とされがち|清潔と安静の重要性
「膝裏の違和感があるけど、動かしたらよくなるかも」と思って無理をすると、かえって悪化してしまうこともあります。
また、傷口があったり肌が荒れている場合には、感染を防ぐ意味でも清潔を保つことが大切です。
とくに、腫れが強いときや熱があるときは無理せず、安静を第一に考えるようにしましょう。
当院では施術だけでなく、そういった日常の工夫や再発予防の視点からもサポートしています。
#膝窩リンパセルフチェック
#しこりの確認ポイント
#リンパストレッチ
#清潔と安静のケア
#自宅でできるリンパ対策
病院に行くべきサインと、診察でよくある検査内容

「痛みが長引く」「熱がある」「動かないしこり」は要注意のサイン
「膝の裏が腫れてるけど、いつの間にか引くだろう」と放置していませんか?
たしかに、軽いリンパの反応であれば自然に引いていくこともありますが、以下のような症状がある場合には、医療機関に相談する目安になると言われています。
- 数日たっても痛みや腫れが引かない
- 押すと熱っぽく、じんわり痛む
- しこりが硬くて動かず、徐々に大きくなっている
これらの状態が続く場合、単なる筋肉の緊張やリンパの滞りだけではない可能性があります。当院でも、触診の結果から明らかに炎症反応や腫瘍性変化の可能性を感じた場合には、無理な施術は行わず、適切な専門機関の受診を提案するようにしています。
医療機関で行われる代表的な検査内容とは?
病院での検査では、まず視診・触診が行われたあと、状況に応じて以下のような検査が選択されることがあるようです。
- 超音波検査(エコー): しこりの正体や内部の構造を見るために用いられます
- 血液検査: 炎症反応や感染の有無、リンパの異常を調べる目的で行われることもあります
- MRIやCT: 周囲の組織や関節構造をより詳しく確認する必要がある場合に使用されま�す
これらの検査は状態に応じて行われるため、「必ず必要」というわけではありませんが、長引く違和感の背景を把握するための選択肢として活用されています。
整形外科?内科?相談先の選び方
「膝裏の腫れって、どこに相談すればいいの?」と迷う方は多いです。
一般的には、動作や関節の問題がある場合は整形外科、しこりの正体が不明で全身の不調がある場合は内科が選ばれる傾向にあります。
当院では、筋肉や関節の動き、全身のバランスを見たうえで、医療機関に行く必要性があるかどうかも一緒に判断しています。
「自分だけでは判断がつかない」「一度相談してから決めたい」という方は、当院での検査(触診)や動作評価をひとつの選択肢としてご活用ください。
#膝裏の腫れと病院へ行く目安
#リンパ節の痛みが続くとき
#しこりの検査内容
#整形外科と内科どちらに行く?
#整体からの判断とサポート
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

廣瀬 知志
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


