荒川院へのご予約
スタッフブログ

高齢者の足のむくみを即効で解消するには?原因から自宅でできる簡単ケアまで紹介
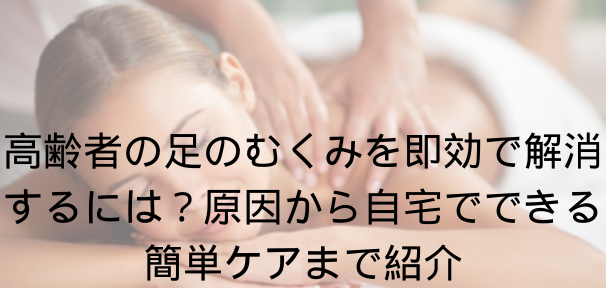
目次
1.なぜ高齢者は足がむくみやすいのか?|主な原因を解説

加齢による血流・リンパの流れの低下
「最近、足がパンパンに腫れてつらそうで…」
そんな高齢のご家族を見て、心配になることはありませんか?実は、加齢とともに血流やリンパの流れが鈍くなる傾向があり、これがむくみの大きな原因と考えられています。とくに下半身は心臓から遠く、重力の影響を受けやすいため、体の中でもむくみやすい場所といわれています。
また、血管の弾力が弱まったり、筋力の低下で血液を押し戻す力が弱くなることも一因になり得ます。当院(https://athletic.work)では、こうした循環の弱さに着目し、血流を妨げる体の歪みや筋肉の緊張を検査・調整することで、巡りをサポートする施術を行っています。
運動不足や長時間の座り姿勢
「座ってばかりで、あまり動かない生活をしているかも…」
そんな日常も、むくみを引き起こす原因のひとつです。筋肉は“第二の心臓”とも呼ばれており、特にふくらはぎの筋肉が動くことで、下半身から心臓への血流を助けるポンプの役割を果たしています。
ところが、テレビを見ていたり、外出が少なかったりすると、足がほとんど動かず、老廃物や水分が溜まりやすくなります。当院では、その方の体の状態に合わせて、無理のない範囲でできる足の運動や姿勢改善のアドバイスもお伝えしています。
心臓・腎臓・静脈の機能低下など疾患が隠れていることも
「むくみって、ただの疲れじゃないの?」と思われがちですが、実は心臓・腎臓・静脈の働きが弱っているサインである場合もあります。特に、片足だけがむくんでいる、押しても戻りにくい、熱感があるといった症状は注意が必要とされており、疾患が潜んでいるケースも考えられます。
当院では、体のチェックを通じて左右差や圧痛の有無、皮膚の状態なども丁寧に確認し、必要に応じて医療機関への相談をご提案することもあります。無理な判断や過剰な施術は行わず、安全性を重視した対応を心がけています。
#足のむくみ対策
#高齢者のケア
#血流改善アプローチ
#整体でできるむくみ対応
#家族ができるサポート
2.即効で足のむくみをやわらげる5つの方法

足を高くして寝る(重力を使う)
「寝ているときに、足を少し高くしてあげるだけで変わるんですか?」
はい、それだけでも巡りのサポートになると考えられています。むくみは重力の影響を強く受けるため、横になって足を心臓よりも高く保つことで、溜まった水分が上半身へ戻りやすくなるようです。クッションや毛布を足の下に敷くなど、簡単にできる方法としておすすめです。
当院では、就寝時の姿勢や枕・クッションの使い方も体の状態に応じてアドバイスしています。
ふくらはぎの軽いマッサージやさすり
「足をもむと楽になるって聞いたけど、やっていいのかな…」
そんなときは、無理のない範囲でふくらはぎを軽くさすってあげるだけでもOKです。特に、足先から膝方向に向かって、ゆっくりと手のひらでなでるように行うと、血液やリンパの流れがサポートされます。
当院でも施術前後にセルフケアとして取り入れることがあり、ご家族が行う場合も、力を入れすぎずリズムよく行うのがポイントです。
足首・つま先の軽い運動(座ったままでOK)
「動かすのがしんどいって言うんですが、何かいい方法ありますか?」
その場合は、椅子に座ったまま足首をゆっくり回したり、つま先を上下に動かすだけでも十分です。こうした小さな動きが、筋肉のポンプ作用を助けることにつながると言われています。
当院では、体力に合わせた運動提案や、痛みが出にくい動かし方の工夫もお伝えしています。
ぬるめのお風呂で足湯をする
「お風呂って全身じゃなくてもいいの?」
はい、むしろ足湯の方が手軽でおすすめされることもあります。ぬるめ(38〜40度くらい)のお湯で10〜15分、足を温めることで末端の血流をサポートし、リラックス効果も期待できます。
当院でも、冷えやむくみが強い方には足湯との組み合わせで施術効果が出やすくなるケースがあると考えています。
弾性ソックス・着圧ストッキングの活用方法
「着圧ソックスって苦しそうだけど、高齢者でも使えるの?」
商品選びと使い方さえ間違わなければ、高齢者にもやさしいサポートアイテムになり得ます。朝のむくみが少ないタイミングで着用し、長時間履きっぱなしにしないことがコツです。
当院ではサイズ選びや履く時間帯の工夫についても、個別にご提案することがあります。
#高齢者むくみ即効対策
#足を高くして寝る
#ふくらはぎマッサージ
#足首体操セルフケア
#着圧ソックス活用法
3.すぐできる!高齢者向けのむくみケアストレッチと体操

椅子に座ったままできる足首回し
「歩くのはしんどいけど、何か動かさないとダメかな…?」
そんなときにぴったりなのが、椅子に座った状態での足首回しです。片足ずつ足を軽く浮かせて、ゆっくり円を描くように足首を回してみてください。左右10回ずつ行うのが目安です。小さな動きでも、ふくらはぎの筋肉や足首周りの血流を促す効果が期待されます。
当院でも、足をあまり動かせない方にこの動きを取り入れることがあり、体に負担が少ない点が特徴だと考えています。
ふくらはぎのポンピング体操
「マッサージの代わりに、自分でできる運動はありますか?」
そんなときにおすすめされるのが、“かかと上げ”のようなふくらはぎポンピング運動です。イスに座ったまま、かかとを床からゆっくり持ち上げ、また戻す。この動きを10回程度くり返すだけでも、筋ポンプ作用を助ける働きがあるそうです。
当院では、施術と併用するセルフケアとして、個人の筋力に合わせてこの体操を提案しています。
寝たままできる足上げストレッチ
「横になってることが多いから、寝たままできるのがいいな」
そんな声に応えられるのが、寝たままできるストレッチ。仰向けになって片脚をゆっくり上げ、膝を軽く曲げた状態で深呼吸をしながら10秒キープ。脚をゆっくり戻して反対側も同様に行います。これを1日数セット繰り返すだけでも、足先の滞った血流を和らげる手助けになるとされています。
当院では、このような寝た姿勢でのストレッチを、個別の可動域に合わせて調整してお伝えしています。
【まとめ】
いずれの動きも「無理なく・毎日続けられる」ことが大切です。高齢者の方にとっては、体を動かす習慣そのものが、むくみの予防につながるとも考えられています。ご自身で行うのが難しい場合は、ご家族と一緒に行うのもおすすめです。
#椅子に座ったまま運動
#足首回しストレッチ
#かかと上げ体操
#寝ながらむくみケア
#高齢者向けセルフケア体操
4.むくみを放置するとどうなる?見逃したくないサインとは

皮膚のただれ・感染のリスク
「むくみって見た目の問題だけでしょ?」
実は、むくみが続くと皮膚のトラブルにつながることがあるようです。水分が皮膚の下に溜まった状態が続くと、皮膚が引き伸ばされて乾燥しやすくなったり、かゆみ・赤みが出てくることがあります。そのまま放っておくと、皮膚が傷つきやすくなり、そこから細菌が入り込んで炎症を起こす可能性もあると言われています。
当院では、皮膚のハリや色味の変化なども確認しながら、トラブルの予防につながるようケアの提案をしています。
血栓・深部静脈血栓症の可能性
「むくみが片足だけに出るってことはありますか?」
はい、特に片側だけの強いむくみには注意が必要だとされています。まれに、静脈の中に血のかたまり(血栓)ができる深部静脈血栓症という状態が隠れていることもあり、放置すると肺に血栓が飛ぶリスクがあるともいわれています。
痛みや熱っぽさ、皮膚の変色などを伴う場合は、早めに医療機関への相談が必要とされています。当院では、施術前にこういった危険サインがないかを丁寧にチェックしています。
片足だけのむくみや痛みは病院受診を検討
「むくみ=整体で何とかなる、と思ってました」
たしかに多くのケースで筋肉や血流の滞りが関係しているのですが、いつもと違う感覚や、左右差の大きいむくみが出たときは別の原因も考慮する必要があります。
当院では、見た目だけで判断せず、問診・触診・筋肉や関節の動き・血流の流れ方などを複合的に見て判断しています。「これは整体の範囲を超えるかもしれない」と感じた場合は、すぐに医療機関の受診をおすすめするようにしています。
「むくみがずっと続いているけど、大丈夫かな…」と気になっている方ほど、日々のちょっとしたサインに気づけるようになっておくことが大切かもしれません。ご本人だけでなく、ご家族の気づきも大きな支えになります。
#むくみ放置のリスク
#皮膚トラブルとむくみ
#深部静脈血栓症に注意
#片足だけのむくみは要チェック
#整体と医療の見極め
5.整体院や専門機関での対応は?家族や介護者ができること

整体ではどう対応するのか(血流改善・姿勢調整)
「むくみって整体でどうにかなるんですか?」
実際、多くの方が最初は半信半疑で来られます。でも、体の使い方や姿勢のクセが関係しているケースも多いんです。たとえば、骨盤や股関節の歪みがあると、血流やリンパの流れを妨げやすくなると考えられ、むくみの一因になることがあります。
当院では、足首や膝・股関節の可動域、立ち姿勢や座り方のクセなどを丁寧にチェックし、滞りやすいポイントを見極めます。そのうえで、血流の通り道を妨げないように、関節のアライメント調整や筋肉の緊張を緩めるアプローチを行っています。
医療との連携が必要なケースとは?
「整体と病院ってどう違うんですか?」
よくあるご質問ですが、私たちが対応するのは“機能的な問題”が中心です。たとえば、筋肉や関節の動き、体の使い方のクセなど。しかし、片側だけ極端にむくんでいたり、皮膚の色が左右で違う、押すと痛いなどの症状があれば、内科的な原因が隠れている可能性も考えられます。
その場合、当院では無理に施術を進めることはせず、必要に応じて専門医への受診をご提案させていただいています。整体と医療のバランスをとりながら、安全第一で対応しています。
日常の中で家族や介護者ができるサポートのポイント
「家族として何をしてあげたらいいのかわからなくて…」
そんなふうに感じる方も多いのではないでしょうか。むくみ対策は“続けること”が大切なので、ご本人が取り組みやすい環境をつくることが大きなサポートになります。たとえば、
- 椅子に座った状態で足を動かせるようなスペースの確保
- 足を高くできるクッションや枕の用意
- ぬるめのお風呂で足湯タイムを一緒に楽しむ
など、ちょっとした工夫がむくみの緩和につながることもあります。
また、当院ではご家族や介護者の方へも簡単なセルフケア指導を行っておりますので、「一緒にケアを覚えたい」という方もお気軽にご相談ください。
#整体でできるむくみケア
#体の歪みと血流の関係
#整体と医療の使い分け
#家族でできるむくみ対策
#高齢者のケアに寄り添う整体院
お悩みの方は、荒川区・文京区 整体oasisへ
なぜ当院で改善できるのか? その理由は、当院のアプローチ方法にあります。
「どこへ行っても改善しなかった…」そんな方こそ、一度ご相談ください。
お電話ならすぐにご予約の空き状況をご案内できます。
LINEからは24時間いつでもお気軽にお問い合わせできますので、ぜひご利用ください!


この記事を書いた人

瑞慶山 良二
荒川区・文京区にある整体oasis(オアシス)では、初めてのお客様に、当院にお身体をあずけられるか判断していただくため、初回のお試し価格をご用意しています。
どのコースを選べばよいか迷われる方は、お気軽にご相談ください。お身体の状態を確認し、改善までの期間や、費用感などもおうかがいしながら、最適な計画をご提案します。


